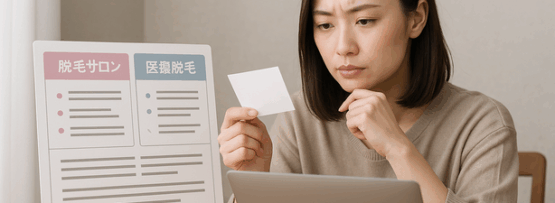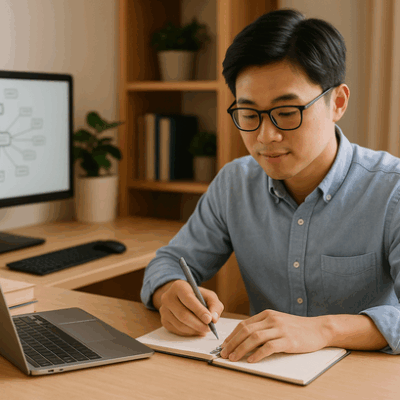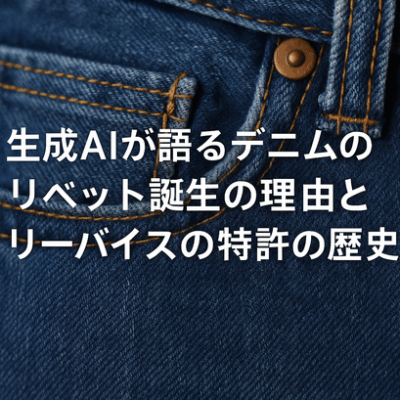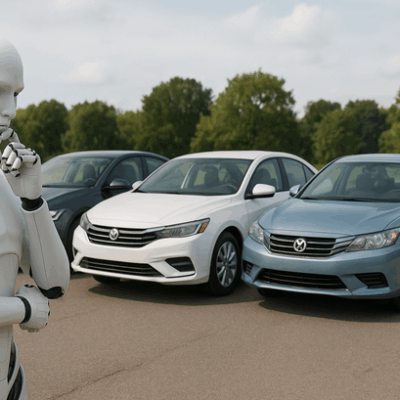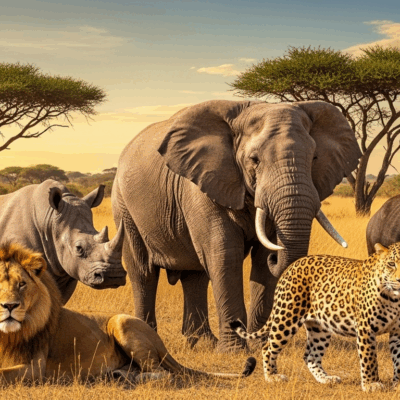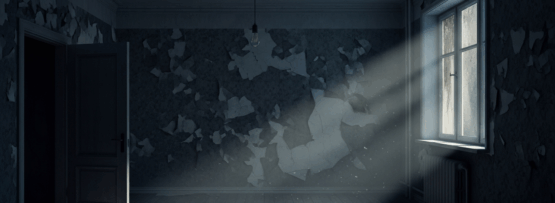AIによるメイクトレンド予測の現在地
SNSの画像・動画、ECのレビュー文、検索クエリの時系列、ランウェイのルックデータなどを横断的に学習したマルチモーダルAIが、メイクトレンドの変化点を高精度に捉えつつある。画像側ではセマンティックセグメンテーションが眉・まぶた・頬・唇などの領域別質感を識別し、テクスチャ(ツヤ/マット)、粒子感(グリッター/シマー)、発色濃度を指標化。テキスト側では感情分析と共起ネットワークにより色名や仕上がりに関する嗜好の傾向を抽出する。これらを時系列モデルに入力し、季節性と突発的バイラルの寄与を分離して予測するアプローチが主流で、ΔEや彩度Sの分布推移、投稿エンゲージメントの弾性値などが意思決定の基盤となっている。
近未来のメイクキーワードと質感の方向性
2025年前後は「質感の二極化の再統合」が進む見込みだ。ベースはスキンケア成分を内包したライトウェイト処方が標準化し、過度なグロウではなく皮膚本来の反射に近いデミマットが支持を得る。頬は血色の再現性が高いシアーブラッシュをレイヤリングし、骨格を強調しすぎないソフトスカルプトが台頭。目元はモノクローム配色を軸に微細パールで面を動かす設計が増え、ライナーはリフト角を意識した極細ラインか、あえて滲ませたスモーキーの二択が伸長する。差し色はペトロールブルーやマルベリーなど低明度・中彩度のニュアンスカラーが堅調。唇はブロッティッド(染めたような薄膜)とビニールシャインの二枚看板で、オーバーラインは粘膜境界を超えない範囲の自然拡張が主流になる。眉は毛流れを生かしたナチュラルテクスチャで、ラミネーション風の上向き固定も引き続き観測される。
パーソナルカラーの再定義とAIの貢献
従来の四季分類は簡便だが、現実の肌色は連続的で、明度(Value)、彩度(Chroma)、色相(Hue)、コントラストの相互作用で「似合う色」が決まる。AIは顔全体のLab値分布から皮膚の平均明度L*と赤み/黄みを示すa*/b*比を推定し、ITA角度(色温感の指標)で寒暖傾向を定量化する。同時に虹彩・毛髪の明度と肌とのコントラスト比を算出し、強いコントラストが映えるタイプか、低コントラストで調和させるべきかを判断する。加えて、皮脂量や毛穴の可視度といった質感情報を組み合わせることで、色だけでなくテクスチャ適合(セミマットかツヤか、微細パール許容量)まで最適化できる点が強みだ。
スマートフォンでの色解析を精度化する手順
屋外日陰または北窓の自然光下で、白紙を基準にホワイトバランスを取った状態で正面・左右の顔写真を取得する。メイクをオフにし、カメラの美肌補正やHDRを無効化するのが望ましい。AIは顔のランドマークを検出し、頬中央・フェイスライン・額の3点から肌色をサンプリングして平均化、L*a*b*空間でノイズを除去する。虹彩はリムと中心を別抽出し、毛髪はハイライト部とシャドウ部を分けて測色する。これにより環境光の偏りを最小化し、デバイス間の色差ΔEを許容範囲内に保つ。推定結果は「寒暖」「明暗」「清濁(くすみ耐性)」「コントラスト適性」の四象限で提示するとユーザーの理解が速い。
AIが導く色と質感のレコメンド設計
– ベースメイク: L*が高く皮脂量が少ない場合は光拡散の強いルースパウダーで面を整え、ハイライトは粒径の小さい微細パールを点で加える。L*が低くコントラスト高の顔立ちは、ツヤ下地で面の輝度差を緩和し、頬中心のみセミマットで引き締めるハイブリッド処方が適合する。
– チーク/ブロンザー: a*/b*が高く赤みが出やすい肌はサーモン〜アプリコットの低彩度で血色を補正。青み寄りの肌にはローズベージュやモーヴのシアー層で深みを足す。ブロンザーはITAが高い(明るくイエロー寄り)場合はオリーブニュアンス、低い場合はレッドブラウン寄りが自然に馴染む。
– アイ: 低コントラスト顔には同系トーンで明度差を1.0〜1.5段に抑えたグラデーションが効果的。高コントラスト顔は締め色の明度差を2段以上確保し、ライナーの不透明度を上げる。ニュアンスカラーはウォーム傾向ならテラコッタ/カーキ、クール傾向ならトープ/プルーンが基準軸になる。
– リップ: 唇のメラニンが少ない場合は黄みの補正が効くコーラル/ローズブラウンの半透明処方、輪郭がぼやける場合は粘膜色に近いMLBBの塗り分けで中心濃度を高める。歯の色温が低いときは青みを1ステップ上げると相対的に白く見える。
– ハイライト/シェーディング: 肌テクスチャが粗い部位はメタリックを避け、ソフトフォーカス系で面を整える。シェーディングはグレーがかると疲れて見える肌ではオリーブ系、澄んだ肌ではニュートラルトープを選択する。
具体的な色マップの例
ウォーム・ソフト(低コントラスト)傾向では、ベースはアイボリー〜ライトベージュ、チークはピーチ/サーモン、アイはキャメル/セージ、ライナーはブラウンのソフトマット、リップはコーラルベージュ/テラコッタの薄膜が安定する。クール・クリア(高コントラスト)傾向では、ベースはニュートラル〜ピンクトーン、チークはダスティローズ/ベリーピンク、アイはトープ/スレート、差し色にプルーンやネイビー、リップはブルーレッド/ワインの高発色か、クリアグロスでコントラストをコントロールする。ニュートラル帯では、黄青どちらにも偏らないトープ、ベージュ、モーヴグレージュを軸に、微細パールで光の質だけを変えるアプローチが汎用性を高める。
AR試着と実購買のギャップを埋める指標
バーチャル試着はディスプレイの色域や顔面の3D形状近似により実物と差が生じやすい。AIは環境光推定とトーンマッピングで誤差補正を行い、表示色と実色のΔEを可視化するほか、撮影時の光源種別(昼白色/電球色)を自動認識し、屋内照明下での見え方を別パネルで提示する。さらに、肌の動きに応じたテクスチャ破綻(口角・目尻のしわ寄り)を予測し、長時間後の崩れパターンをシミュレーションすることで、ECと実購買のギャップを縮小できる。
バイアスと衛生要件への配慮
トレーニングデータの肌色多様性が不足すると誤推定の温床になるため、フィッツパトリック尺度や独自の明度/色相グリッドでカバレッジを担保する設計が必要だ。撮影機器の違いも色再現に影響するため、標準色票による簡易キャリブレーションをアプリ側で案内し、端末ごとの補正プロファイルを適用する。個人データは顔特徴量や色解析結果を端末内で処理し、必要最小限のみ匿名化して送信するフェデレーテッド学習が望ましい。美容医療情報と異なり安全性上のリスクは低いが、アレルギーや香料感受性の情報を組み合わせたレコメンドで皮膚トラブルを未然に抑えることができる。
日常に落とし込む運用ガイド
季節や髪色の変化で似合う範囲は微移動する。ヘアカラーを1〜2トーン変えた場合、リップとアイのコントラスト設計を再計算すると整合性が高い。日中は自然光、夜は電球色の室内光で見え方が変わるため、同一色でもテクスチャを切り替える(昼はセミマット、夜はグロス)と破綻が少ない。AIはクローゼットやアクセサリーの色群とも相関分析が可能で、トップスの色相に対する補色/同系のどちらが好印象度を高めるかを履歴から学習する。最終的な選択は嗜好とシーン要件だが、数値化された指標を基に微調整することで、再現性の高い「似合う」を日常のスピードで達成できる。