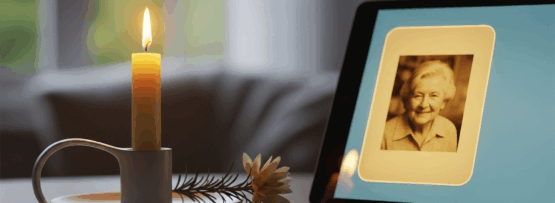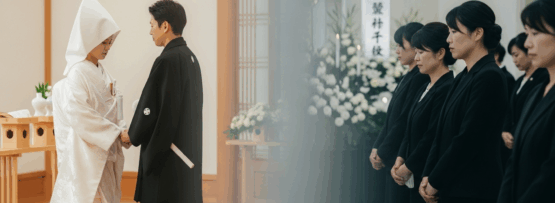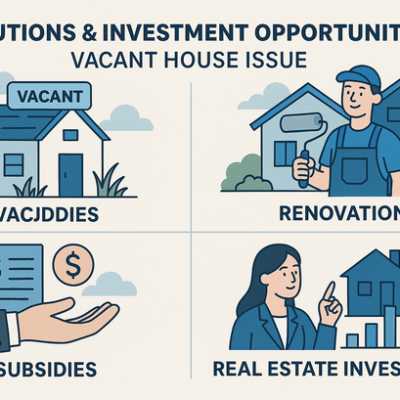SNSが日常になった今、冠婚葬祭の場で「どこまで写真を撮っていい?」「投稿しても大丈夫?」と迷う人が増えています。即時性のある発信は便利ですが、出席者のプライバシーや場の厳粛さ、主催者の意向を損なわない配慮が欠かせません。本稿では、日常の延長で守れるシンプルなルールと、シーン別の具体的なポイントをまとめました。難しい専門用語は避け、明日から使える実践的な指針としてご活用ください。
基本の3原則:同意・時機・場の尊重
- 同意:主役(新郎新婦・喪主など)と写り込む人の許可を取る。子どもの顔は原則ぼかす・非公開にする。
- 時機:式の最中はカメラをしまい、公式フォト公開後に投稿。弔事は当日リアルタイム投稿を避け、家族の了承を得る。
- 場の尊重:撮影禁止サインに従う。祭壇・御霊前・戒名などのクローズアップは避ける。フラッシュやシャッター音をオフに。
結婚式・披露宴のマナー
式場ごとに撮影ルールが異なるため、開式前に司会やスタッフへ確認を。挙式中はプロカメラマンの妨げにならない席で静かに。ドレスの全景や会場の雰囲気は、他のゲストの顔が特定されない角度で切り取ると安心です。キャプションは「素敵な一日をお裾分け」など、主役中心の表現に。ご祝儀や席次表、招待状のQRコードなど個人情報が写らないよう注意しましょう。
葬儀・お別れの会のマナー
弔事は「撮らない・急がない・言葉を選ぶ」が基本。会場や遺影、供花は原則SNSに上げない方が安全です。どうしても共有が必要な場合は、家族の明確な了承を取り、日付や会場名、参列者の顔は伏せる配慮を。表現は「ご冥福をお祈りします」「在りし日を偲び…」など簡潔で落ち着いた言葉を選び、スタンプや過度な絵文字は控えましょう。
お宮参り・七五三・成人式・長寿祝い
家族行事は微笑ましい投稿が多い反面、場所や時間が特定されやすいもの。位置情報はオフ、制服・通学路・ナンバーなどの写り込みに注意を。神社仏閣は御神体やご本尊、祭具の至近撮影を控え、参拝の妨げにならない短時間の撮影に留めます。集合写真は全員の掲載可否を確認し、顔出しNGの人は距離・角度・スタンプでケアを。
写真・動画の撮り方と投稿のコツ
- フレーミング:手元や後ろ姿、装花や会場の光など「雰囲気の切り取り」を意識。
- 情報管理:名札・社名・席札・QR・位牌の文字は写さない/ぼかす。
- 位置情報:自動タグ付け・地図リンクはオフ。後日まとめ投稿が安全。
- BGM・音声:式中の演奏や読経の音源は権利や宗教上の配慮から掲載を控える。
- ハッシュタグ:固有名詞より「#結婚式の記録」「#家族の節目」など抽象的に。
言葉づかいとキャプション例
- 慶事例:「心あたたまる一日。末永い幸せを祈って」「たくさんの笑顔に感謝」
- 弔事例:「静かに偲ぶ時間を過ごしました」「感謝の思いを胸に」
- 避けたい表現:内輪ノリのスラング、過度な自慢、速報的な煽り文句。
生成AI・加工の注意点
明るさ調整やトリミングは有効ですが、生成AIでの大幅な加筆修正は誤解を生みます。存在しない人や装飾を「足す」加工、宗教的シンボルを「消す」編集は避けましょう。肌や衣装のレタッチは控えめにし、AI補正を用いた場合は「一部画像補正あり」と明記すると透明性が保てます。顔ぼかしや背景の個人情報消去など、守りの加工を優先するのが賢明です。
投稿前30秒チェックリスト
- 主役と写り込む人の許可は取ったか
- 会場・宗教施設のルールに反していないか
- 個人情報・位置情報は含まれていないか
- 言葉づかいは場にふさわしいか
- 時間帯と公開範囲(限定公開・親しい友だち)は適切か
おわりに
SNSは「共有したい善意」と「守るべき敬意」の間に成り立ちます。迷ったら、主催者の意向と場の静けさを最優先に。写真はいつでも撮れますが、その瞬間の空気は戻りません。思い出を美しく残し、関係性をさらに大切にするための小さな配慮を、今日から一つずつ実践していきましょう。