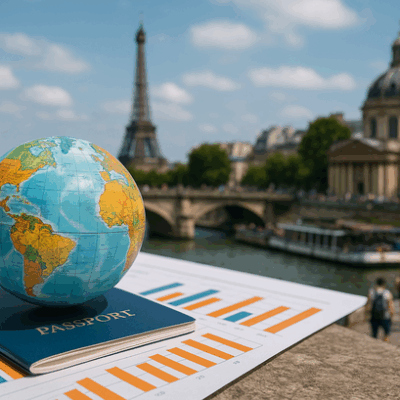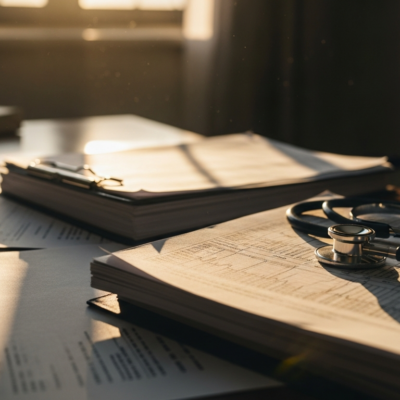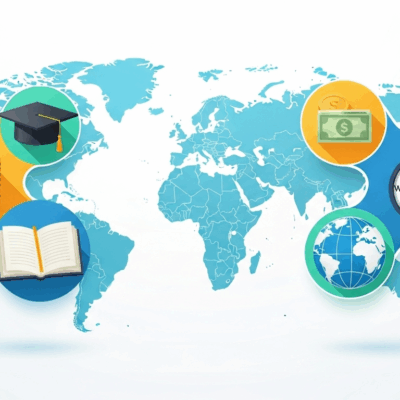症状が出たとき「今すぐ救急に行くべきか、様子を見るべきか」で迷う人は多く、夜間・休日は特に判断が難しくなります。むやみに我慢すると悪化のリスクがありますし、軽症で混雑を招くのも避けたいところ。そこで本稿では、一般の方が使いやすい受診の考え方と、家庭でできる初期対応の基本を整理します。専門用語はできるだけ使わず、「迷ったときに役立つ実践的な視点」をまとめました。
受診判断の基本の考え方
判断の軸はおおまかに3つです。
- 症状の強さ:普段の体調とかけ離れているか、我慢できないつらさがあるか
- 変化の速さ:急に悪化したか、短時間で広がる・繰り返すか
- 危険のサイン:意識がはっきりしない、動かしにくい部位がある、息苦しいなど
この3点のうち、当てはまる項目が多いほど、早めの受診や相談を検討しましょう。迷うときは無理に自己判断せず、相談窓口やかかりつけに連絡するのが安全です。
赤・黄・緑のめやす
- 赤(すぐ相談・受診を検討):急な強い痛みが続く、息がしづらい・ゼーゼーする、ろれつが回らない・手足がしびれる・力が入りにくい、意識がもうろう、顔や唇の強い腫れ、発熱でぐったりして反応が乏しい。
- 黄(当日〜翌日までに受診を検討):高めの熱が続く・ぶり返す、嘔吐や下痢で水分が取りにくい、転倒や打撲後に動かすと強い痛みが続く、広い範囲の発疹やかゆみが拡大する、排尿時の強い違和感がある。
- 緑(まずは家庭で様子見が可能):軽い咳や鼻水、軽い頭痛や肩こり、すり傷や小さな打撲、軽い胃もたれ。ただし長引く・悪化する場合は受診を。
同じ症状でも年齢や持病、妊娠中かどうかで判断は変わります。小児や高齢者、持病のある方は早めの相談を心がけましょう。
家庭でできる初期対応の基本
- 安全確保と安静:無理に動かず、楽な姿勢で休む。必要なら室温や衣服を調整。
- 水分補給:胃腸症状や発熱時は、少量をこまめに。経口補水液などを活用し、無理な一気飲みは避ける。
- 冷やす・温める:打撲や軽い捻挫はタオル越しに冷やして様子見。慢性的なこりは一時的に温めると楽になることも。
- 皮膚のケア:清潔を保ち、かきこわしを避ける。刺激の強い外用剤や民間療法は控えめに。
- 薬の使い方:市販薬は表示の用法・用量を厳守。既往歴や併用薬、アレルギーがある人は特に注意。
- 経過の記録:発症時刻、症状の流れ、体温や食事・水分量、使用した薬をメモしておくと受診時に役立ちます。
迷ったときの相談先
緊急性の判断に迷うときは、地域の電話相談を活用しましょう。多くの地域で「#7119(救急相談)」が設けられており、看護師等が症状に応じた受診先の目安を助言してくれます。子どもの場合は「#8000(小児救急相談)」も有用です。かかりつけ医や薬剤師への相談も、平日日中は心強い選択肢です。
子ども・高齢者で注意したいポイント
- 子ども:機嫌や顔色、尿や涙の量、呼吸の様子など「いつもと違う」変化を重視。短時間で状態が変わりやすいので、早めに相談。
- 高齢者:痛みを訴えにくい、熱が出にくいことがあります。「食欲低下」「いつもより動けない」「急にぼんやりする」など小さなサインを見逃さない。
- 持病・妊娠:持病の悪化や妊娠中の体調変化は、軽症に見えても注意が必要。早めに主治医へ連絡を。
受診前のミニチェックリスト
- 本人確認書類・保険証・お薬手帳
- 症状のメモ(発症時刻、経過、体温、飲食・水分量、使用した薬)
- 基礎疾患・アレルギー・妊娠の有無の情報
- 必要に応じて患部の写真(発疹や腫れの変化は共有すると有用)
まとめ
救急受診の判断は「強さ・速さ・危険サイン」の3軸でシンプルに考え、迷ったら早めに相談するのが基本です。家庭での初期対応は、安静・水分・清潔・適切な薬の使い方を土台に、無理をしないこと。いざという時のために、相談窓口の番号や持ち物リストを家族で共有しておくと安心です。