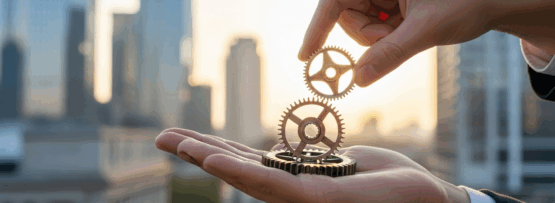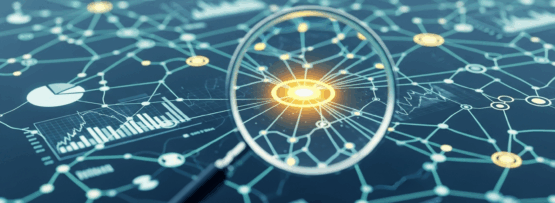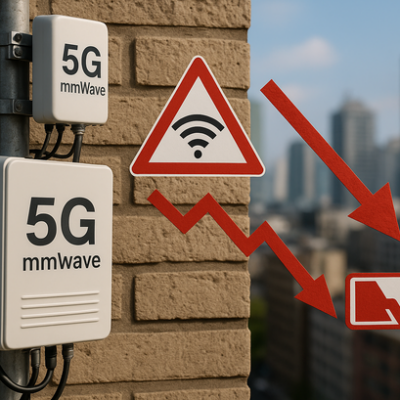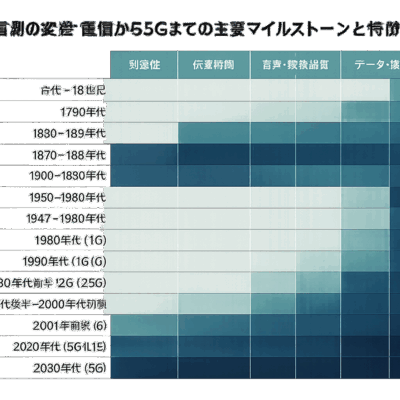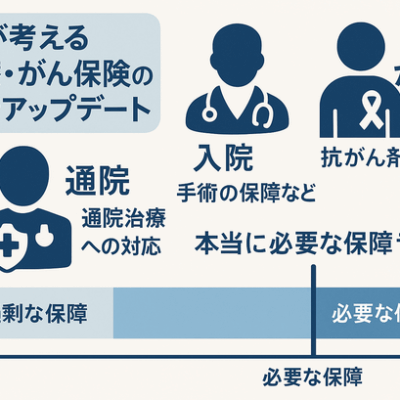「保険って、たくさんありすぎてどれに入ればいいのか分からない」「営業の人に勧められるがまま契約してしまったけど、本当にこれで合っているのかな?」
多くの人が、保険選びに対してこんな悩みを抱えているのではないでしょうか。人生の大きな買い物の一つでありながら、その複雑さからつい後回しにしてしまったり、深く考えずに決めてしまったりすることも少なくありません。
そこで今回は、今話題の生成AIに「自分に本当に必要な保険を見つける方法」について、率直に尋ねてみることにしました。特定の企業に属さない中立的なAIは、私たちにどんな答えを導き出してくれるのでしょうか。その興味深い回答を元に、保険選びの新しいアプローチを探っていきます。
生成AIが最初に教えてくれた「保険選びの地図」
「あなたに最適な保険はこれです!」と、いきなり具体的な商品を提示されるかと思いきや、生成AIの最初の答えは全く違うものでした。
「保険商品を探す前に、まずあなた自身の『現在地』と『目的地』を明確にすることが最も重要です。」
まるで人生のナビゲーターのような言葉です。AIが言うには、多くの人が「どの保険に入るか(手段)」から考えてしまうため、混乱してしまうとのこと。そうではなく、「なぜ保険が必要なのか(目的)」という根本的な問いから始めるべきだと教えてくれました。
その目的を明らかにするために、AIは具体的な3つのステップを提案してくれました。それは、まるで自分だけの「保険選びの地図」を作るようなプロセスでした。
ステップ1:自分の「リスク」を洗い出してみよう
AIが最初に提案したのは、「自分の人生における経済的なリスクを客観的に洗い出す」ことでした。
これは、自分のライフステージによって大きく異なります。
- 独身の方:一番に考えるべきは「自分が働けなくなった時のリスク」です。病気やケガで長期間入院したり、働けなくなったりした場合の収入減少にどう備えるか。具体的には、医療保険や就業不能保険が選択肢になります。
- 結婚している方(子どもなし):自分やパートナーに万が一のことがあった場合、残された側の生活水準を維持できるかがポイントです。お互いの収入や貯蓄額によっては、高額な死亡保険は不要なケースもあります。
- 子育て世代の方:最も保障を手厚く考えるべき時期です。自分に万が一のことがあった場合、子どもが独立するまでの教育費や生活費をどう確保するか。死亡保険(定期保険など)の必要性が高まります。また、一家の働き手の病気やケガによる収入減も大きなリスクです。
- 子育てが落ち着いた世代:子どもの独立で、高額な死亡保障は不要になることが多いです。むしろ、自分たちの老後資金や介護、病気への備えにシフトしていく時期。医療保険やがん保険、介護保険などを検討することになります。
このように、自分の今の状況と将来を想像し、「何が起こったら経済的に一番困るか?」を具体的に考えることが、保険選びのスタート地点だとAIは強調します。
ステップ2:公的保障という「最強の味方」を知る
次にAIが指摘したのは、多くの人が見落としがちな「公的保障」の存在です。
私たちは、民間の保険に入る前から、すでに国が運営する強力な保険に加入しています。それが、健康保険や国民年金、厚生年金といった社会保険制度です。
例えば、病気やケガで医療費が高額になっても、日本では「高額療養費制度」があるため、自己負担額には上限が設けられています。また、会社員の方が亡くなった場合には「遺族厚生年金」が、重い障害を負った場合には「障害年金」が支給されることもあります。
AIは、「民間の保険を検討する前に、まず公的保障でどれくらいカバーされるのかを知ることが大切です。不足する部分だけを民間の保険で補う、という考え方が無駄のない保険選びのコツです」と教えてくれました。すべてを民間の保険で準備しようとすると、保険料が過大になってしまうのです。
ステップ3:必要な保障額を「ざっくり」計算する
リスクを洗い出し、公的保障でカバーされる範囲を理解したら、いよいよ「どれくらいの保障が必要か」を考えます。ここでもAIは、複雑な計算式ではなく、シンプルな考え方を提示してくれました。
【万が一の時に必要なお金】 - 【公的保障や貯蓄で準備できるお金】 = 【民間の保険で備えるべき金額】
例えば、子育て世代の働き手に万が一のことがあった場合を考えてみましょう。
「子どもが独立するまでの生活費や教育費で合計いくら必要か」を考え、そこから「遺族年金で受け取れる額」や「現在の貯蓄額」を差し引きます。その不足分が、死亡保険で準備すべき金額の目安になる、というわけです。難しく考えすぎず、まずはざっくりとでもいいので、自分にとって必要な金額をイメージすることが重要です。
まとめ:AIとの対話で見えた、保険選びの新常識
生成AIに相談してみて分かったのは、AIは私たちに「思考の整理術」を教えてくれる素晴らしいパートナーだということです。特定の保険商品を勧めるのではなく、私たちが自分自身で最適な保険を見つけるための「考え方のフレームワーク」を示してくれました。
「なんとなく不安だから」「みんな入っているから」という理由で保険を選ぶ時代は終わりつつあるのかもしれません。まずはAIが教えてくれたステップに沿って、自分自身の人生と向き合い、本当に必要な備えは何かを考える。その上で、具体的な商品選びに迷った時にファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談すれば、より納得感のある保険選びができるはずです。
保険選びは、未来の自分と家族への大切なメッセージです。この機会に、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。