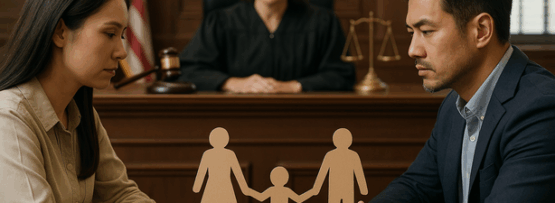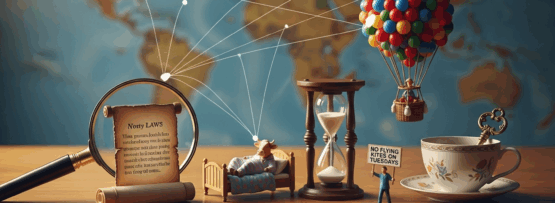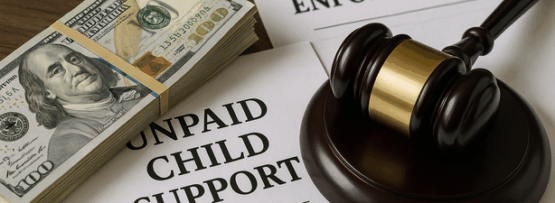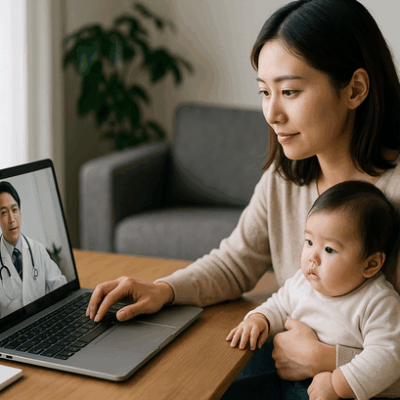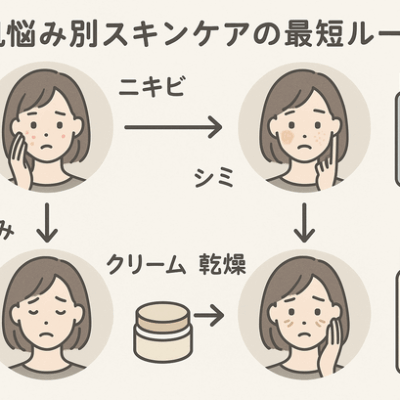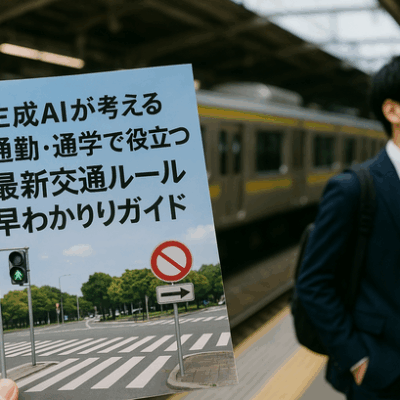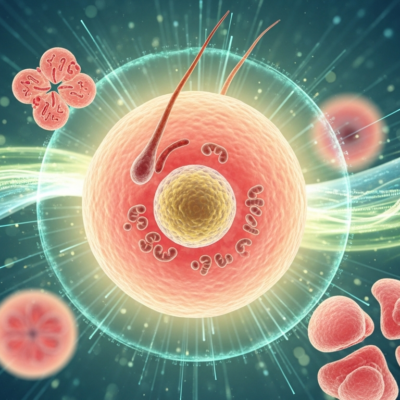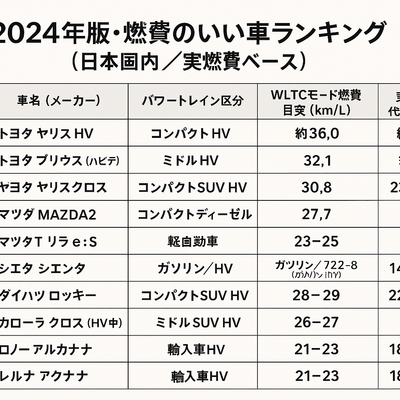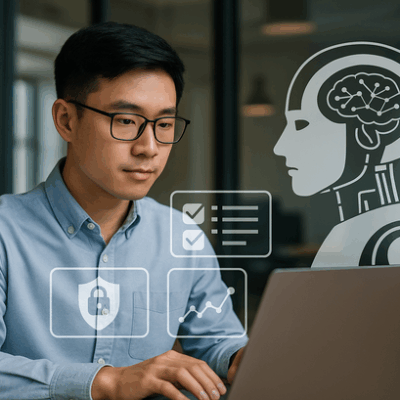歩行者・自転車・車が同じ道を使う時代。スマホ利用の増加、新しいモビリリティの登場、時間に追われる移動など、昔の常識だけでは対応しきれない場面が増えています。本稿では、最新の視点で「どこで」「どう譲り」「どう合図するか」をQ&A形式で整理します。難しい専門用語は避け、誰でも今日から実践できるヒントをまとめました。なお、交通法規は地域や改正で細部が変わるため、最終的にはお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
歩行者Q&A:横断と見られ方のコツ
Q. 横断歩道はどう渡るのが正解?
A. 横断歩道は歩行者優先です。渡る意思を運転者に伝えるため、いきなり飛び出さず、立ち止まって車列の動きを確認し、手を軽く上げる・目線を合わせるなどの合図が有効です。夜間や雨天は明るい服や反射材が安全に役立ちます。
Q. 信号のない横断歩道では?
A. 多くの地域で、車は「渡ろうとしている歩行者」にも一時停止義務があります。歩行者側も無理な横断は避け、車が完全に止まったことを確認してから渡りましょう。
Q. イヤホンやスマホ操作は?
A. 音や気配に気づきづらくなります。横断時はイヤホンを外す・画面を見ないなど、「見る・聞く」の感度を上げるのが安心です。
自転車Q&A:車道が原則、歩道は例外
Q. 自転車はどこを走る?
A. 原則は車道の左側通行。自転車レーンや自転車道があればそこを優先して利用します。歩道走行が認められている場面でも「歩行者優先・徐行」が大原則です。
Q. 夜間のライトとベルの使い方は?
A. 夜間は前照灯を必ず点灯し、被視認性を高めます。ベルは「注意喚起用」で、安易に鳴らすのではなく、声かけや減速と組み合わせた丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
Q. スマホ片手・傘さし・並走は?
A. どれも危険で多くの地域で禁止・規制対象です。スマホは停車して操作、悪天候時はレインウェアで視界と両手を確保。基本は一列走行です。
Q. 交差点で気をつけることは?
A. 直進・左折でも死角が増えます。減速してアイコンタクト、手信号や視線で意思表示を。右折は無理せず、安全な場所で降りて横断する方法も有効です。
自動車Q&A:歩行者優先と「見つける運転」
Q. 横断歩道に近づいたら?
A. 減速して、渡ろうとする歩行者がいれば必ず止まる。停止後も左右・後方を確認し、対向車側の歩行者にも注意を払います。
Q. 右左折時のポイントは?
A. 早めの合図と十分な減速。自転車の直進、横断歩道の歩行者、ベビーカーや高齢者の動きに目を配り、無理な進入は避けます。
Q. ながら運転と車間距離は?
A. スマホ注視は重大なリスク。停車中に操作するのが鉄則です。天候や見通しに応じて車間を広めに確保し、急ブレーキを避けられる余裕を持ちます。
新モビリティQ&A:電動キックボード等の基礎
Q. どこを走れて、速度や年齢は?
A. 地域や区分でルールが細かく異なります。通行区分(車道・自転車道・歩道の可否)、最高速度、ヘルメットや年齢条件、ライト・ベルの装備義務などを、提供事業者と自治体の最新案内で必ず確認しましょう。
Q. 走行時のマナーは?
A. 合図と徐行が基本。歩行者の多い場所は速度を落とし、見通しの悪い角では一時停止に近い減速を。スマホ操作や2人乗りは厳禁です。
「ルール」と「思いやり」を両立する3原則
- 見える工夫:ライト点灯、反射材、明るい服、早めのウインカーで「気づいてもらう」。
- 伝える工夫:手信号、目線、合図、軽いベルや声かけで「意思を共有」。
- 余裕の確保:速度・車間・時間に余白を持ち、「譲れる余地」を常に残す。
アップデートに強くなるチェックリスト
- 自治体・警察の公式サイトで最新の改正点を確認する。
- 通勤・通学ルートの危険箇所(見通し・段差・混雑時間)を地図にメモ。
- 新モビリティのシェアサービスはアプリ内のルール表示を毎回確認。
- 子ども・高齢者と共有する「家庭内ルール」を短く具体的に。
交通ルールは「守る」だけでなく、「互いにわかりやすく伝える」ことで、いっそう効果を発揮します。今日の移動から、合図と余裕のひと工夫を試してみてください。小さな配慮の積み重ねが、街全体の安心につながります。