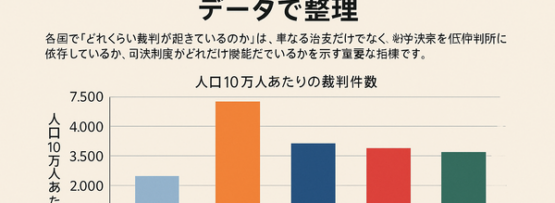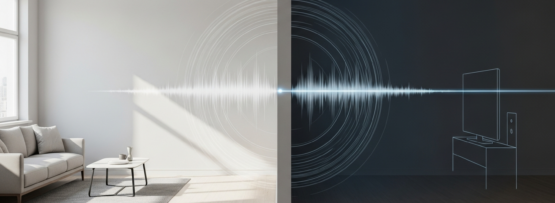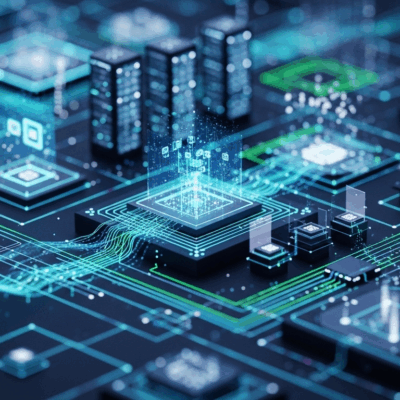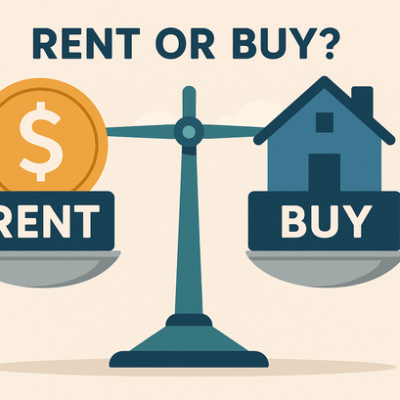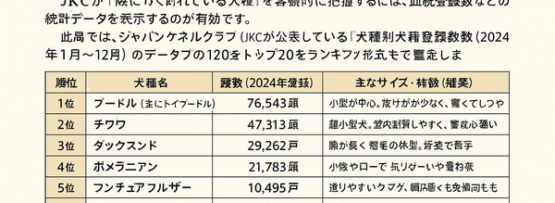SNSは私たちの生活に欠かせないコミュニケーションツールとなりました。誰もが気軽に情報発信できるようになった一方で、たった一つの投稿がきっかけで激しい誹謗中傷の的となる「SNS炎上」も後を絶ちません。心無い言葉が拡散され、個人の尊厳や社会的な信用が著しく傷つけられる「名誉毀損」にまで発展するケースも少なくありません。「もし自分が被害に遭ってしまったらどうすればいいのか」「どうすれば加害者にならずに済むのか」。この問題は、もはや他人事ではありません。今回は、SNS炎上と名誉毀損をテーマに、いざという時のための法的対応策と、自分を守るための心構えを分かりやすく解説していきます。
SNS炎上と「名誉毀損」は何が違うのか?
まず、「炎上」と「名誉毀損」の違いを正しく理解することが、適切な対応への第一歩です。この二つはよく混同されがちですが、意味合いは大きく異なります。
SNS炎上とは、特定の投稿に対して、インターネット上で批判や非難が殺到し、拡散されていく「現象」そのものを指します。これは必ずしも法的な問題に直結するわけではなく、単なる意見の対立や道徳的な批判も含まれます。
一方、名誉毀損は法律上の問題です。具体的には、「不特定多数の人が知ることができる状況で、具体的な事実を挙げて、他人の社会的評価を低下させる行為」を指します。たとえ書かれている内容が真実であっても、相手の社会的評価を下げるものであれば名誉毀損は成立する可能性があります。
例えば、「あの店のラーメンは味が薄くて好みじゃなかった」という感想は、個人の意見の範囲内でしょう。しかし、「あの店は、客の食べ残しを使いまわしている」といった具体的な事実(それが嘘であっても)を書き込めば、店の社会的評価を著しく低下させるため、名誉毀損に該当する可能性が非常に高くなります。この違いを認識することが、冷静な判断の基礎となります。
名誉毀損が成立する3つのポイント
では、どのような投稿が法的に「名誉毀損」と判断されるのでしょうか。難しい法律用語を抜きにして、成立するための3つの重要なポイントを見ていきましょう。ご自身のケースが当てはまるかどうかの参考にしてみてください。
ポイント1:公然と(不特定多数の人が見られる場所で)
SNSや掲示板、ブログなど、誰でも閲覧できるオープンな場所での投稿であることが前提です。鍵付きのアカウントであっても、フォロワーが複数人いれば「公然」と見なされる可能性があります。
ポイント2:事実を摘示して(具体的な事柄を挙げて)
「あの人は前科がある」「彼は職場で不正行為をしている」など、内容の真偽は別として、具体的な事実が示されていることが必要です。ちなみに、単に「バカ」「キモい」といった具体的な事実に基づかない悪口は、名誉毀損ではなく「侮辱罪」という別の犯罪に該当する場合があります。
ポイント3:人の社会的評価を低下させたか
その投稿によって、対象となる人物や企業の信用、名声といった社会的な評価が客観的に見て低下したと言えるかどうか、という点です。読んだ人がその人に対して悪いイメージを抱くような内容であることがポイントになります。
この3つのポイントが揃うと、法的に名誉毀損と判断される可能性が高まります。
もし被害に遭ってしまったら?法的対応の3ステップ
もしあなたが誹謗中傷の被害に遭い、名誉毀損の可能性があると感じたら、パニックにならず冷静に行動することが重要です。ここでは、取るべき具体的な3つのステップをご紹介します。
ステップ1:証拠を保全する
何よりもまず、証拠を残しましょう。問題の投稿は削除されてしまう可能性があります。投稿内容だけでなく、URL、投稿日時、アカウント名などがすべて写るように、PCやスマートフォンの画面全体をスクリーンショットで撮影してください。ウェブページを保存する「魚拓」といったサービスを利用するのも有効です。証拠がなければ、その後の手続きを進めることは非常に困難になります。
ステップ2:削除を依頼する
次に、投稿の削除を目指します。まずは、X(旧Twitter)やInstagramといったSNSの運営会社に対し、利用規約違反(誹謗中傷やプライバシー侵害など)を理由に削除依頼を申請します。各プラットフォームには通報フォームが用意されています。投稿者本人に直接削除を求める方法もありますが、相手を逆上させ、さらなる被害を招くリスクもあるため、慎重に判断しましょう。
ステップ3:専門家(弁護士)に相談する
投稿が削除されても心の傷が癒えない、経済的な損害を受けた、あるいは投稿者を特定して責任を追及したい、という場合は、速やかにインターネット問題に詳しい弁護士に相談してください。弁護士は、「発信者情報開示請求」という法的手続きを通じて、匿名で投稿した人物の氏名や住所を特定することができます。この手続きには時間と費用がかかりますが、損害賠償請求や刑事告訴を検討する上で不可欠なステップです。
知らないうちに「加害者」にならないために
ここまで被害者側の対応策を見てきましたが、同時に私たちが「加害者」にならないための心構えも非常に重要です。正義感や軽い気持ちからの投稿が、誰かを深く傷つけ、法的な責任を問われることにもなりかねません。
投稿する前に、一呼吸おいて自問自答してみてください。
- その投稿は、誰かを不必要に傷つける内容ではないか?
- 根拠の不確かな噂や情報を、事実であるかのように断定していないか?
- 怒りや嫉妬といった、一時的な感情に任せて書き込んでいないか?
また、他人の悪意ある投稿を安易にリツイート(リポスト)したり、「いいね」したりする行為も注意が必要です。内容によっては、誹謗中傷に賛同し、拡散に加担したとみなされ、共同で責任を問われる可能性もゼロではありません。SNSは便利なツールですが、その言葉は現実世界と同じ重みを持つことを常に意識しましょう。
SNSでのコミュニケーションが当たり前になった今、法的な知識は自分を守るための「お守り」になります。被害に遭ったときは泣き寝入りせず、加害者にならないためには想像力を持つこと。この二つを心に留めて、賢く、そして思いやりをもってSNSを活用していきましょう。