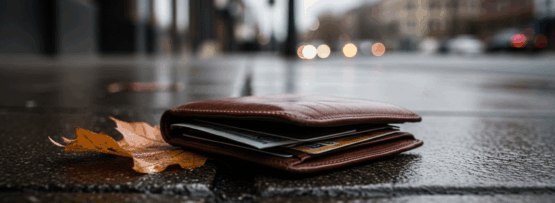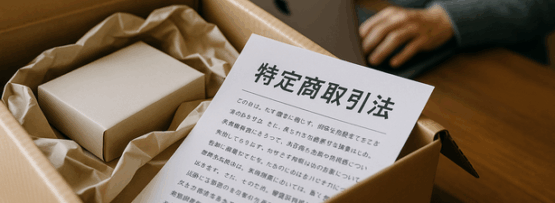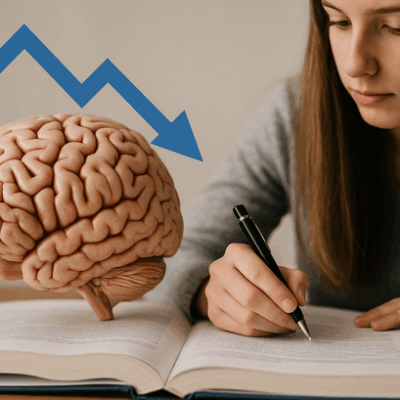「自分は交通ルールをしっかり守っている」――多くの人がそう思っていることでしょう。しかし、スマートフォンの普及や新しい乗り物の登場など、私たちの生活スタイルが変化する中で、交通ルールも複雑化し、知らず知らずのうちに違反を犯してしまう「落とし穴」が増えています。今回は、生成AIにも協力を仰ぎながら、日常に潜む意外な交通ルールの落とし穴を紐解き、誰もが安全に道路を利用するためのヒントを探っていきます。
スマホの「ながら運転」、信号待ちはセーフ?
運転中のスマートフォン操作が厳罰化されたことは、もはや常識です。しかし、その認識には意外な落とし穴があります。多くの人が「赤信号で停止していれば、スマホを操作しても大丈夫」と考えているのではないでしょうか。
実は、これは大きな誤解です。道路交通法では、運転中の「携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視すること」を禁止しています。たとえ車両が完全に停止していても、運転の一環である「信号待ち」中の操作は「ながら運転」と見なされ、取り締まりの対象となります。青信号に変わったことに気づかず発進が遅れ、後続車とのトラブルの原因になることも少なくありません。
カーナビとしてスマートフォンをホルダーに固定して使用する場合も、2秒以上の画面注視は「違反」と判断される可能性があります。運転中に操作が必要になった場合は、必ず安全な場所に停車してから行うようにしましょう。「ちょっとだけ」の油断が、大きな事故と重い罰則につながることを忘れてはいけません。
音楽を聴きながらの自転車はOK?イヤホンの落とし穴
通勤や通学、あるいはサイクリング中に、イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っている人をよく見かけます。風を切って好きな音楽を聴くのは気持ちが良いものですが、これも交通違反になる可能性が高い行為です。
多くの都道府県では、公安委員会規則(道路交通規則)によって、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態」での車両の運転を禁止しています。これには自転車も含まれます。具体的にどの程度の音量からが違反になるかという明確な基準はありませんが、パトカーのサイレンや救急車の警音、他の車両のクラクション、歩行者の声などが聞こえない状態は極めて危険です。片耳イヤホンなら大丈夫、と考える人もいますが、自治体によってはイヤホンの種類(両耳か片耳か)を問わず、使用自体を禁止している場合もあります。
罰則の対象になるだけでなく、何よりも事故のリスクを著しく高める行為です。自転車に乗るときは、周囲の音に注意を払える状態を保つことが、自分と周りの人の安全を守る上で不可欠です。
「歩道は自転車もOK」という思い込みの危険性
自転車に関するもう一つの大きな落とし穴が、走行場所のルールです。日本では歩道を自転車が走っている光景が当たり前になっていますが、大原則を忘れてはいけません。道路交通法上、自転車は「軽車両」であり、車道を通行するのが原則です。
もちろん例外もあります。「自転車通行可」の標識がある歩道や、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合、また、車道が工事中などで通行が危険な場合には歩道を通行できます。しかし、その場合でも「歩行者優先」が絶対のルールです。歩行者の通行を妨げるような速度で走ったり、ベルを鳴らして道を空けさせようとしたりする行為は違反となります。歩道を通行する際は、車道寄りをすぐに止まれる速度で徐行しなければなりません。
また、車道を走る際は、自動車と同じく左側通行が義務付けられています。逆走(右側通行)は、正面から来る自動車や自転車との衝突事故を引き起こす非常に危険な行為です。自転車は便利な乗り物ですが、自動車と同じ車両の一員であるという意識を持つことが大切です。
横断歩道、「歩行者がいなければ」止まらなくていい?
「横断歩道は歩行者優先」――これは運転免許を持つ人なら誰もが知っている基本中の基本です。しかし、実際の道路では、横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず、一時停止せずに通過していく車が後を絶ちません。
ここで見落としがちなのが、「横断しようとしている歩行者」の判断です。横断歩道の手前で待っている人が、本当に渡る意思があるのかどうか分かりにくい、と感じるドライバーも多いでしょう。しかし、法律上は「横断し、又は横断しようとする歩行者等があるとき」は、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならないと定められています。
つまり、渡るかどうか迷っているように見える人がいる場合でも、ドライバーは「渡るかもしれない」と予測し、停止する義務があるのです。歩行者がいるにもかかわらず停止しない「横断歩行者等妨害等」は、れっきとした交通違反であり、罰金だけでなく違反点数も科されます。思いやりの心を持ち、横断歩道の手前では速度を落とし、常に歩行者の安全を最優先する運転を心がけましょう。
そのクラクション、実は違反かも?
危険を知らせるために重要な役割を果たすクラクション(警音器)ですが、その使い方にもルールがあります。本来、クラクションは「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上などを通行する際に、危険を防止するために鳴らすものです。
しかし、日常では違う使われ方をすることがあります。例えば、前の車が青信号になっても発進しないときに催促で鳴らしたり、道を譲ってもらったお礼として軽く鳴らす「サンキュークラクション」もその一つです。これらの行為は、本来の目的とは異なる使用であり、「警音器使用制限違反」に該当する可能性があります。
不必要なクラクションは、他のドライバーや歩行者を驚かせ、トラブルの原因にもなりかねません。感謝の気持ちは、クラクションではなく、軽く会釈をする、ハザードランプを数回点灯させるなどの方法で伝えるのがスマートです。クラクションは、本当に危険な時だけに使用する「最後の手段」と心得ておきましょう。