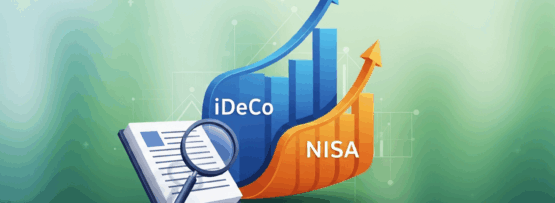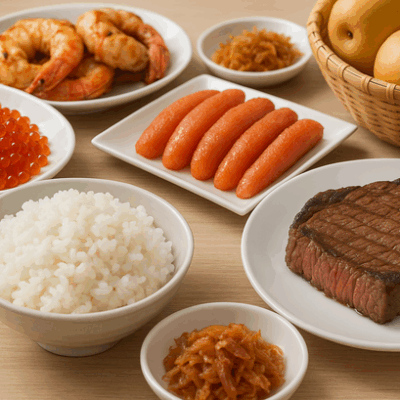教育費を計画的に用意したいと考えると、「学資保険」と「つみたてNISA」で迷う人は多いもの。堅実に貯めたい一方、物価上昇にも負けたくない。結論から言えば、二者択一ではなく「役割分担での併用」が現実的です。本稿では、両者の違いを分かりやすく整理し、家計や目標時期に合わせた賢い使い分けを提案します。
学資保険とつみたてNISA、まず何が違う?
- 学資保険:保険と貯蓄のハイブリッド。満期や学資年金として計画的に受け取りやすく、契約者に万一があった際の「払込免除」で備えにもなる。一方で、途中解約に弱く、返戻率は低めでインフレに対しては相対的に弱い。
- つみたてNISA:投資信託で長期・分散・積立。運用益が非課税でインフレには比較的強い可能性。いつでも売却でき柔軟だが、元本保証はなく価格変動リスクを伴う。
要は「確実性と使途の固定化」なら学資保険、「成長期待と柔軟性」ならつみたてNISAが得意分野です。
こんな人に学資保険が向いている
- 教育費に用途を限定して、確実に積み立てたい
- 途中で手を付けにくい仕組みで強制力がほしい
- 親に万一のことがあった場合も学費を確保したい(払込免除)
- 受け取り時期(入学進学時など)がほぼ決まっている
こんな人につみたてNISAが向いている
- 物価上昇に備え、長期で資産を増やす可能性を取りたい
- 家計の変動に合わせて積立額を止めたり再開したりしたい
- 受験・進学まで10年以上の時間がある(時間分散が効きやすい)
- 用途を教育費に限定せず、将来の選択肢を広く持ちたい
両立の考え方:使い分け3ステップ
- 目標額の見える化:公立・私立、通学・下宿などで幅があります。まず「最低限ここまでは確実に」という安全ラインを設定。
- 土台づくりは学資保険:安全ラインに相当する部分を学資保険で。途中解約の弱さを理解しつつ、満期時期を進学スケジュールに合わせるのがコツ。
- 成長余地はつみたてNISA:上乗せ分を長期・分散で積み立て。目標時期が近づくにつれ、段階的にリスクを下げていく運用(現金・預金への振替)を意識。
受け取り時期に合わせた取り崩し戦略
つみたてNISAは「時間が味方」。ただし、使う直前までリスク資産のままだと相場次第でブレます。目安として、入学3年前から定期的に売却し、現金や預金へ移すと変動リスクをならしやすくなります。学資保険は受取時期が決まっているため、そのタイミングを基準にNISA側の取り崩し計画を重ねるイメージが有効です。
よくある誤解と注意点
- 「学資保険は必ず得する」わけではない:返戻率は商品や金利環境で変わります。医療特約の上乗せで実質利回りが下がることも。
- 「つみたてNISAなら短期でもOK」ではない:数年内に使う資金には値動きが重く、短期偏重は不向き。時間分散とリスク調整が前提。
- 解約・途中停止の柔軟性:学資保険は途中解約の元本割れリスクが大きめ。NISAは売買・積立停止は柔軟だが、相場次第で損失の可能性。
- 税制・制度は変わり得る:非課税枠や保険料控除の扱いは将来変更の可能性があるため、最新情報の確認を。
- まずは生活防衛資金:6〜12カ月分の生活費を現金で確保してから、学資保険・NISAの配分を考えると安心感が増します。
賢い配分のヒント
- 児童手当などの定期収入は「原資」に:全額または一部を自動積立に回すとブレにくい。
- 期間別の役割分担:小学・中学は学資保険中心、高校・大学の上乗せはNISAなど、時期で強みを生かす。
- 見直しの年を決める:毎年の学年始めや誕生日に、返戻率、積立達成度、進学方針を点検。
まとめ:正解は「家計×目的」の最適化
学資保険は「確実に、用途を絞って貯める」土台。つみたてNISAは「インフレに備え、柔軟に増やす」上乗せ。二つの強みを組み合わせ、目標額と時期から逆算して配分すれば、迷いは小さくなります。商品選びでは、返戻率や手数料、受取方法、解約条件を必ず比較。最終的には「続けられる仕組み」と「ぶれない目的設定」が、教育資金づくりの最大の武器です。