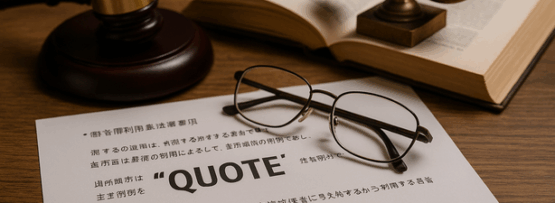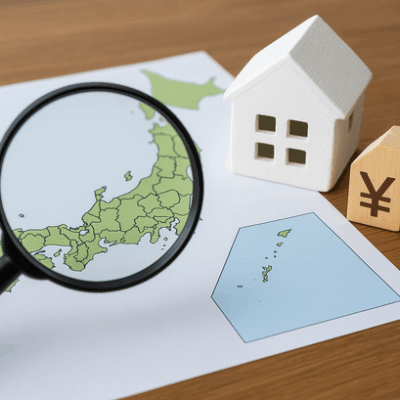街を歩けば、スーッと静かに走り抜けていく電動キックボード。手軽で便利な新しい移動手段として、私たちの日常に急速に浸透しつつあります。しかし、その一方で「どこを走るのが正解なの?」「歩行者としては少し怖い…」「自転車との距離感が難しい」といった声が聞こえてくるのも事実です。この新しい乗り物の登場は、これまでの歩行者、自転車、自動車という交通社会の秩序に、新たな問いを投げかけています。今回は、交通ルールの専門家として、そして最先端の生成AIと共に、これからの時代の「交通の新常識」について考えてみたいと思います。
電動キックボードの登場で生まれた「新たな緊張関係」
これまで、私たちの身近な交通空間は、主に「歩行者」「自転車」「自動車」という3つのプレイヤーで構成されていました。それぞれに大まかな役割分担と暗黙のルールがあり、それによって秩序が保たれてきたのです。しかし、そこに電動キックボードという、これまでのどれとも少し違う性質を持つ新しいプレイヤーが加わりました。この変化が、新たな「緊張関係」を生み出しています。
歩行者から見れば、電動キックボードは「静かすぎる脅威」に映ることがあります。背後から音もなく近づき、気づいた時にはすぐ横を通り過ぎていく。特に子供や高齢者にとっては、予測が難しく、接触事故への不安を感じるでしょう。自転車利用者にとっては、同じ車道や自転車道を走る仲間である一方、その機敏さや速度差に戸惑う場面もあります。追い越すべきか、待つべきか、その判断が新たなストレスになっているのです。
一方で、電動キックボードの利用者自身も悩みを抱えています。法改正によりルールは明確化されましたが、「特定小型原動機付自転車」という新しい区分はまだ社会に浸透しきっていません。どこを走れば周囲に迷惑をかけないのか、どこに停めればいいのか、常に周囲の視線を気にしながら利用している人も少なくないでしょう。この三者三様の戸惑いが、道路上での見えない緊張感につながっているのです。
生成AIが指摘する「ルールの隙間」と「意識のズレ」
この複雑な問題を、膨大なデータから傾向を読み解くのが得意な生成AIに問いかけてみると、興味深い2つのキーワードが浮かび上がってきました。それは「ルールの隙間」と「意識のズレ」です。
まず「ルールの隙間」について。AIは、自転車のルールが長い年月をかけて社会に浸透してきた歴史を例に挙げます。ヘルメット着用の努力義務化や、傘差し運転の禁止など、自転車に関するルールも、事故の発生や社会の変化に応じて少しずつ更新され、時間をかけて私たちの常識になってきました。電動キックボードのルールは、いわば“生まれたて”の状態です。法律で大枠は決められても、狭い路地でのすれ違い方や、歩行者が多い場所での振る舞いといった、日常生活に即した細かなマナーまではカバーしきれていません。この「隙間」を埋めるのは、法律の追記だけでなく、社会全体の成熟が必要だとAIは分析します。
次に「意識のズレ」です。生成AIは、利用者側の「乗り物としての自覚」の欠如を指摘します。手軽さゆえに、まるで歩行の延長線上のような感覚で乗ってしまい、自分が「車両」を運転しているという意識が薄れがちになる傾向があるのではないか、というのです。また、歩行者や自転車側にも、電動キックボードを「仲間はずれ」にしてしまう無意識の壁が存在する可能性も示唆します。未知のものへの警戒心から、過度に危険視したり、走行空間から排除しようとしたりする意識が働いてしまう。このお互いの意識のズレが、円滑な共存を妨げている一因となっているのです。
未来の交通風景を描くための3つの新常識
では、私たちはこの新しい時代の交通社会とどう向き合っていけば良いのでしょうか。生成AIの分析も踏まえ、交通の専門家として3つの「新常識」を提案します。
1. 「シェア・ザ・ロード」から「コミュニケーション・ザ・ロード」へ
「道を分け合いましょう」という「シェア・ザ・ロード」の精神は重要ですが、これからは一歩進んで、お互いに意思疎通を図る「コミュニケーション・ザ・ロード」という意識が不可欠になります。これは、アイコンタクトや会釈、手信号といった、ごく簡単な非言語コミュニケーションのことです。電動キックボードの利用者は、曲がる前に少し後方を確認する、歩行者の横を通過する際は少しスピードを落として距離をとる。歩行者や自転車は、キックボードが来そうなことを察知したら、少し進路を譲る。こうした小さな思いやりと意思表示の積み重ねが、お互いの信頼感を生み、事故を未然に防ぎます。
2. 速度で空間を使い分ける「意識のゾーニング」
道路を物理的に完全に分離するのは難しいですが、私たち一人ひとりが「ここはゆっくり走るゾーン」「ここは少しスピードを出しても良いゾーン」といった意識を持つことで、交通はもっとスムーズになります。例えば、商店街や住宅街の細い道は、歩行者が主役の「低速ゾーン」。ここでは電動キックボードや自転車は、いつでも止まれる速度で走行する。一方で、自転車ナビラインなどが整備された広い道路は、乗り物が主役の「中速ゾーン」と意識する。このように、場所の特性に応じて自分の振る舞いを変える「意識のゾーニング」が、これからの新しい交通マナーの基本となるでしょう。
3. テクノロジーによる「見えないルール」の支援
私たちの意識やマナーだけでは限界がある部分を、テクノロジーで補うことも重要です。例えば、AIを活用した「ジオフェンシング」という技術。これは、GPSを使って仮想的な境界線を作り、特定のエリアでの乗り物の挙動を制御するものです。学校の周辺や歩行者専用道路に入ると、電動キックボードが自動的に減速したり、アシストが停止したりする。利用者が意識しなくても、テクノロジーが安全な利用をサポートしてくれるのです。また、スマートフォンのアプリを通じて、リアルタイムで危険箇所や推奨ルートを通知するシステムも有効です。AIが交通データを分析し、事故が起きやすい交差点を予測して警告するなど、技術は私たちの「見守り役」になってくれます。
電動キックボードの普及は、私たちに新しい便利さをもたらすと同時に、これまでの交通安全意識をアップデートする絶好の機会を与えてくれました。新しいルールをただ覚えるだけでなく、なぜそのルールが必要なのかを考え、歩行者、自転車、そして電動キックボード利用者が、お互いを尊重し、思いやりを持って道を使う。そんな温かい「新常識」を、社会全体で育てていくことが、未来の安全で快適な交通社会を築く鍵となるはずです。