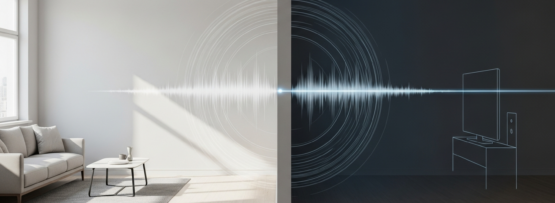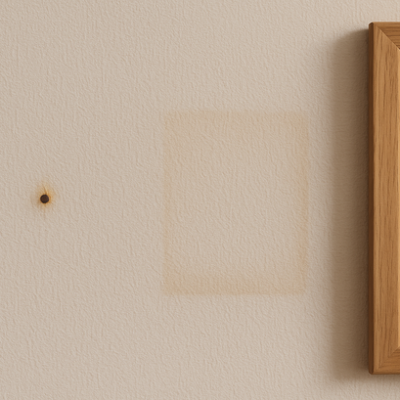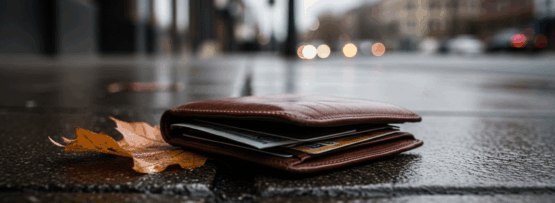家庭裁判所の手続きは「難しそう」「費用が読めない」「どれくらい時間がかかるの?」という不安がつきものです。本稿では、申立て・調停・審判の基本的な流れと費用感を、できるだけやさしい言葉で整理します。事前に全体像をつかむことで、ムダな往復や準備漏れを減らし、心の余裕を確保するのがねらいです。
家庭裁判所で扱う主なテーマと全体像
家庭裁判所では、離婚や親権・養育費、面会交流、財産分与、相続・遺産分割、後見などを扱います。多くのテーマは「まず調停」で話し合いを試み、合意できなければ審判(家庭裁判所が判断)や、離婚の場合は訴訟へ進む流れです。手続きは原則非公開で、月1回程度のペースで進みます。
申立て前に整えること
- 目的と優先順位の整理(例:子どもの生活安定が最優先、次に面会交流の具体化 など)
- 事実のタイムライン作成(いつ、何が、どのように起きたか)
- 資料の集約(戸籍・住民票、収入や支出のわかる書類、子の生活状況がわかる資料など)
- 管轄の確認(相手方または子どもの住所地の家庭裁判所が多い)
申立ての流れ
- 申立書の作成:裁判所サイトの書式を参考に、希望内容と理由を簡潔に。
- 必要書類の添付:戸籍謄本や収入資料など、案件ごとに異なります。
- 手数料の納付:収入印紙+郵便切手(後述)。
- 受付後、期日通知:初回は1~2か月先が目安。
書式や必要書類は裁判所ごとに少し違うことがあるため、公式サイトや窓口で最新の案内を確認しましょう。
調停の進み方(多くの事件で“まず調停”)
- 調停委員との個別面談:相手と顔を合わせない運用が一般的。事情を丁寧に聴取。
- 交互に話を聴き、合意点を探る:月1回ペースで2時間前後が目安。
- 合意成立なら調停調書を作成:法的効力のある合意書に。
- 不成立の場合:親権や監護などは審判へ移行することがあり、離婚は地方裁判所での訴訟へ進む道が一般的です。
調停は「言い負かす場」ではなく「合意形成の場」。希望(結論)だけでなく、その理由と代替案を準備すると前進しやすくなります。
審判に進むケースとポイント
面会交流の方法や監護者の指定、親権者の変更、遺産分割などは、合意できない場合に家庭裁判所が資料や調査を踏まえて審判します。子の福祉や生活の安定が重視され、学校や保育状況、養育環境、当事者の関係性などが総合考慮されます。
期間の目安
- 申立て~初回期日:おおむね1~2か月
- 調停の総期間:3~6か月が多いが、争点が多いと6~12か月超のことも
- 審判:事案により幅が大きく、数か月~1年程度
進行は裁判所の混雑や資料提出の速度、当事者の合意可能性に左右されます。
費用のめやす(裁判所に納める実費)
- 収入印紙:調停・審判とも多くは数百~数千円台(例:離婚や養育費等の調停は1,200円程度が目安)。
- 郵便切手:連絡・送達用に数千円程度(裁判所ごとに定額セットが異なる)。
- 書類取得・写し交付:数百~数千円。
- 調査・鑑定がある場合:別途数万円規模が発生することあり。
これらは「裁判所へ支払う実費」です。弁護士へ依頼する場合の費用(着手金・報酬金・日当・実費)は別枠で、事案の難易度や地域によって大きく異なります。
準備のコツとつまずき対策
- 論点を分けて整理:子ども、住まい、お金(養育費・財産)、面会交流などに分解。
- 「証拠化」を意識:主張はメモや資料で裏づけ。感情より事実と客観資料。
- 代替案を用意:面会交流は回数・時間・方法(オンライン含む)など複数案を。
- 連絡は丁寧に:期日変更や資料不足は早めに相談。小さな遅れが全体の長期化に。
まとめ:不安を“見通し”に変える
家庭裁判所の手続きは、申立て→調停→(必要に応じて)審判という段階で進み、費用は「裁判所実費は比較的少額、時間は数か月単位」が一般的なイメージです。大切なのは、事前準備で論点と資料をそろえ、合意形成のための代替案を持つこと。最新の書式・費用・必要書類は、必ず各家庭裁判所の公式案内で確認するとスムーズです。