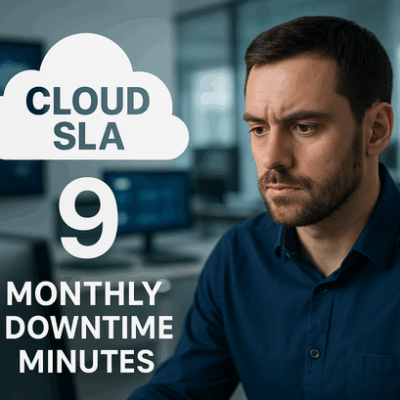私たちの暮らしにテクノロジーが深く浸透する現代、大切な方とのお別れの形もまた、大きな変化の時を迎えています。遠方に住んでいてお葬式に駆けつけられない、体調が優れず参列が難しい、といった声を聞く機会は増えました。また、故人がSNSやブログ、無数のデジタル写真といった「デジタルな足跡」を遺すことも当たり前になっています。こうした中で、「故人を心から偲ぶ」という大切な想いを、どうすれば時代に合わせて形にし、未来へつないでいけるのでしょうか。今回は、生成AIをはじめとする新しい技術が、私たちのお別れの文化にどのような可能性をもたらすのか、「オンライン追悼」と「デジタル遺産整理」という二つの側面から考えてみたいと思います。
いつでも、どこからでも故人を偲ぶ「オンライン追悼」という選択肢
「オンライン追悼」と聞くと、少し冷たい印象を受ける方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その本質は、物理的な距離や時間の制約を超えて、より多くの人が故人を偲ぶ機会を作ることにあります。例えば、故人の写真や動画、思い出の音楽などを集めたオンラインの「メモリアルサイト」を想像してみてください。
そこでは、生前の故人を知る人々が世界中からアクセスし、それぞれの思い出や感謝のメッセージを書き込むことができます。遠くに住む親戚や、高齢で外出が難しいご友人、海外赴任中の同僚も、時間や場所を気にすることなく、故人との思い出を分かち合うことができるのです。これは、従来の葬儀では難しかった、新しい形の「つながり」と言えるでしょう。
ここに生成AIが加わることで、追悼の形はさらに豊かになります。例えば、遺族が選んだ写真や動画を基に、AIが故人の生涯を振り返る感動的な追悼ムービーを自動で作成してくれたり、参列者から寄せられた多くのメッセージをAIが整理し、故人の人柄が伝わる一冊の美しい追悼文集としてまとめてくれたりします。さらには、故人の遺した文章や音声データを学習したAIが、遺族に向けてパーソナルな慰めのメッセージを生成するといった技術も研究されています(もちろん、これには深い倫理的な配慮が不可欠です)。テクノロジーは、悲しみに暮れる遺族の心に寄り添い、故人を偲ぶ作業を温かくサポートする道具となり得るのです。
故人のデジタルな足跡を未来へつなぐ「デジタル遺産整理術」
次に、見過ごされがちですが非常に重要なのが「デジタル遺産」の問題です。デジタル遺産とは、故人がインターネット上に遺したSNSアカウント、ブログ、オンラインストレージの写真や動画、ネットバンクの口座など、形のないデジタルデータの総称です。これらを放置すると、アカウントが乗っ取られたり、個人情報が流出したりするリスクがあるだけでなく、ご遺族がパスワードが分からず途方に暮れてしまうといった精神的な負担にもつながります。
ここでも、生成AIは大きな助けとなります。まず、膨大なデジタルデータの中から、AIが重要な書類や思い出の写真を自動で分類・整理してくれます。何万枚とある写真の中から、AIが家族の笑顔の写真だけをピックアップしてアルバムを作成してくれる、といったことも可能になるでしょう。これにより、遺族はデータの海に溺れることなく、故人との大切な思い出を効率的に見つけ出すことができます。
また、「デジタル終活」のサポート役としても期待されています。生前のうちに本人がAIアシスタントと対話しながら、「このSNSアカウントは閉鎖する」「このブログは記念として残す」といった意思をデジタル形式で記録しておくのです。これにより、遺族は故人の意思を尊重しながら、スムーズに手続きを進めることができます。さらに、故人が遺したブログ記事やSNSの投稿をAIが解析し、その人柄や哲学が詰まった一冊の本やウェブサイトとして再構成することも可能です。これは、故人の生きた証を、新しい形で未来の世代へと語り継ぐ、現代ならではの素晴らしい方法ではないでしょうか。
新しいテクノロジーと、変わらない「偲ぶ心」の調和
もちろん、こうした新しい形に対して、「温かみがないのでは」「儀式が簡素化されすぎるのでは」といった懸念の声があることも事実です。しかし、大切なのは、テクノロジーが「主役」になるのではなく、あくまで「故人を偲び、遺された人々の心を癒す」という目的を達成するための「手段」であるということです。
お葬式という伝統的な儀式を大切にしながら、それに参列できない方のためにオンライン追悼の場を併設する「ハイブリッド型」も一つの答えです。大切なのは、画一的な形にこだわるのではなく、故人らしさやご遺族の想いに寄り添い、最もふさわしいお別れの形を柔軟に選択できることだと考えます。
生成AIをはじめとするテクノロジーは、私たちの「お別れの文化」を無機質にするものではありません。むしろ、これまで物理的な制約で叶わなかった想いを実現させ、お別れの形をよりパーソナルで、温かく、そして多くの人が心を通わせられるものへと進化させる可能性を秘めています。変わらない「偲ぶ心」を真ん中に置きながら、新しい時代の技術と上手に手を取り合っていくこと。それが、これからの時代に求められる新しい弔いの姿なのかもしれません。