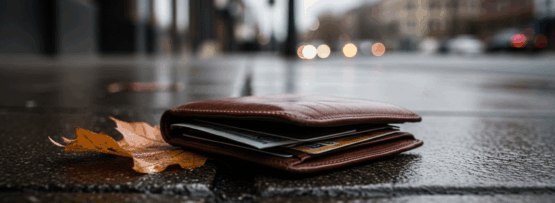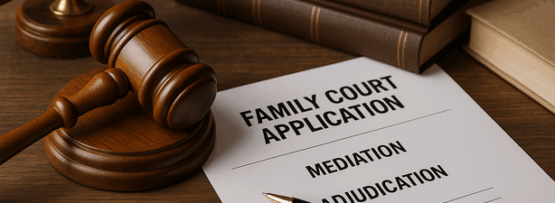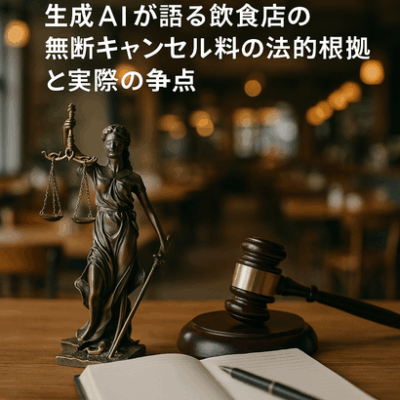少額訴訟は「少額の未払いをスピーディーに解決したい」人の味方ですが、いざ使おうとすると費用の見積もりや証拠の揃え方、当日の進み方が分かりづらいのが実情です。ここでは、初めてでも迷いにくいように、費用感・勝ちやすい準備・当日の流れを一気に整理します。専門用語はなるべく避け、実務で役立つ要点に絞って解説します。
少額訴訟とは?向いているケースの見極め
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを簡易裁判所で原則1回の期日で終わらせる制度です。未払い代金、家賃、敷金、修理費など、事実や金額が比較的シンプルな争いに向いています。スピード重視で、裁判官から和解(分割払いなど)が提案されることも多いのが特徴です。
注意点は、相手が強く争う姿勢を示したり、事案が複雑と判断されると通常訴訟へ移行することがある点。また、控訴はできず、相手方は一定期間内の「異議申立て」で通常訴訟へ切り替えられる可能性があります。
かかる費用の目安と節約のコツ
主な費用は次のとおりです。
- 収入印紙代:請求額に応じて発生(例:10万円→1,000円、30万円→3,000円、60万円→6,000円程度)
- 郵便切手代:裁判所ごとの指定額(概ね3,000〜6,000円)
- 書類作成・コピー代:数百〜数千円
弁護士を依頼しなければ、基本的にこれらの実費のみ。印紙は郵便局等で購入できます。証拠はモノクロで十分な場合が多く、必要部数のみ印刷して節約を。部数は「裁判所用+相手方用」を基本に、窓口の案内に従ってください。
勝ちやすくする準備のコツ
- 主張は3点に絞る:「いくら」「なぜ発生」「払われていない」の骨子を明快に
- 時系列を1枚に:出来事を日付順に簡潔に並べると説明がブレません
- 証拠の見せ方:契約書・請求書・領収書・メール/チャット・写真などを番号付けし、誰が・いつ・何を示すかを付記
- 金額の根拠:計算式(単価×数量、遅延損害金の起算日など)を書面化
- 反論の先回り:相手が言いそうな点をQ&Aで用意。「〇月〇日に受領」「この合意は書面あり」など事実で返す
- 収集は適法に:違法・不適切な方法で得た情報には頼らない
さらに、和解の代替案(例:分割払いや支払い期日)を考えておくと、当日の提案に乗りやすくなります。
手続きの流れと当日のイメージ
申立ては、相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ。少額訴訟用の書式に「請求の趣旨・原因」「時系列」「証拠一覧」を添えて提出します。期日が決まると、裁判所から相手へ書類が送達され、当日を迎えます。
当日の一般的な進行は、(1)事実関係の確認、(2)原告・被告の主張、(3)証拠の確認、(4)和解の打診、(5)判決という流れ。所要は30〜60分程度が目安です。話す時間は短いので、要点メモをA4一枚にまとめ、番号を振った証拠と対応付けておくとスムーズ。服装は清潔なビジネスカジュアルで、開始10分前には到着を。持ち物は印鑑、身分証、提出書類の控え、筆記具など。
判決後の対応と回収の考え方
判決や和解が成立すれば、内容に従って支払いが行われます。支払いがない場合は、預金や給与の差押え等の強制執行を検討します(別途費用が必要)。相手の勤務先や取引銀行など、回収の見通しにつながる情報は、事前にわかる範囲で把握しておくと有利です。なお、被告が期限内に異議を申し立てた場合は通常訴訟へ移行し、手続は長期化します。
迷ったときの使い分けと最後のヒント
文書でのやり取りが整っていて争いが少ないなら、まずは支払督促という選択肢も。話し合いで解決できる余地があるなら、内容証明郵便での最終催告から入ると費用を抑えられます。少額訴訟を選ぶ際は、「請求額が60万円以下」「主張と証拠がシンプル」「早期解決を重視」の3点を満たすかで判断すると失敗しにくいでしょう。
本稿は一般的な情報提供です。個別事情で結論は変わり得るため、迷う点があれば最寄りの法テラスや専門家への相談も検討してください。