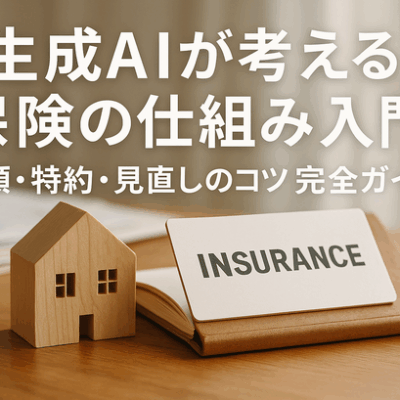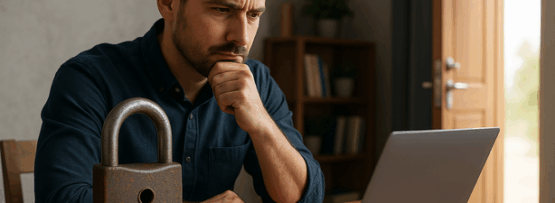眠りたいのに、頭の中のタスクがぐるぐるして目が冴える——そんな夜は珍しくありません。カフェインやスマホ、忙しさの余韻が重なり、気持ちは疲れているのに体は休めない。この課題に対しての提案はシンプルです。寝る直前の「心の静けさ」を自分でつくること。そのための道具として、マインドフルネスを短く、やさしく取り入れます。特別な知識は不要。今夜から試せる小さな習慣に落とし込んでいきましょう。
課題の整理:眠れない本当の理由は“興奮の残り”
眠りを邪魔するのは「ストレスそのもの」よりも、寝る頃まで残っている心身の興奮です。脳が次の動作に備えていると、寝床に入っても加速をやめられません。だからこそ、眠る前にブレーキを踏む合図をつくることが大切。マインドフルネスは、その合図を呼吸や感覚に移す練習です。
マインドフルネスと睡眠の関係:注意の置き場所を変える
「眠れないかも」という不安に注意が貼りつくと、さらに目が冴えます。マインドフルネスは、注意の置き場所を「考え」から「いまの感覚」へ静かに移すこと。深く上手に呼吸しようと頑張る必要はありません。うまくやるより、やさしく戻ることがコツです。
今夜からできる3分ルーティン
- 1分・ながめる呼吸:横になり、3回だけゆっくり吐く。胸やお腹の上下を「見物する」気持ちで。コントロールは不要。
- 1分・からだのスキャン:つま先→ふくらはぎ→もも→お腹→肩→顔の順に、内側の重さや温度を順番に感じる。「あるものを、そのまま」確かめるだけ。
- 1分・思考の置き場所:「考えが浮かぶのは自然」と認め、心の中に“メモ置き場”をイメージしてポンと置く。戻ってきてもOK、また置く。
合計3分。途中で眠くなったらそのままでかまいません。最後に、姿勢を5%だけゆるめるつもりで肩とあごを軽くほどきます。
日中に仕込む30秒の下ごしらえ
- 起床後:窓際で自然光を30秒浴びながら「今日やることを一行だけ」心で唱える。夜の迷いを減らします。
- 午後の一息:席を立たずに背中を伸ばし、2回長めに吐く。「ふー、ふー」。それだけで十分。
- 夕方の区切り:作業を終える前に机を10秒整える。視界の静けさは夜の静けさの予告編です。
デジタルと光を“静けさ仕様”にする
- 画面の終業時刻:就床の60分前に「通知を切る」。完全に見ないのが難しければ、音だけでもオフ。
- 光のグラデーション:部屋の明かりを段階的に落とす。明るい→暖色→間接照明の順で、目に“夜だよ”と知らせます。
- ベッドの役割を一本化:寝床は「休む場所」。動画や作業は椅子で。脳にわかりやすい合図になります。
続けるコツ:うまくやるより、わずかにやる
- ハードルは低く固定:「毎日3分できたら成功」。長くやれた日はラッキー扱いに。
- トリガーとセット:歯みがき→照明を落とす→3分ルーティン、の順を毎回同じに。
- 効果の観察は週単位:その日に「眠れた/眠れない」で判断しない。1週間で気分や朝の体感を振り返る。
よくあるつまずきと優しい対処
- 考えが止まらない:止めなくていい。“気づいたら戻す”が正解。戻す回数が練習です。
- 呼吸が浅い:吐くほうを長めに。カウントは「吐く4・吸う自然」で十分。
- 中断される:中断のたびにリセットではなく、続きから再開。継ぎ目のある練習でOK。
まとめ:静けさは「作れる」スキル
眠りはコントロールできませんが、眠りの入り口にある“静けさ”はつくれます。マインドフルネスは、その静けさを自分で用意する小さな技。完璧さより継続、長さより頻度。今夜の3分が、明日の体と心の余白になります。まずは今日、照明を少し落として、呼吸を三度、長めに吐く。そこから始めてみましょう。