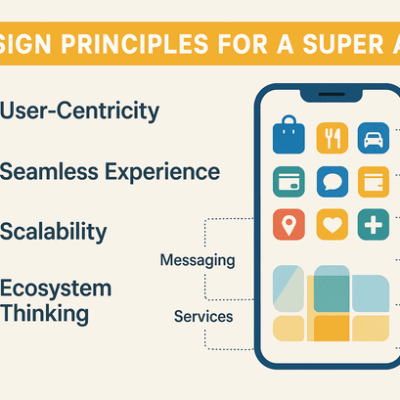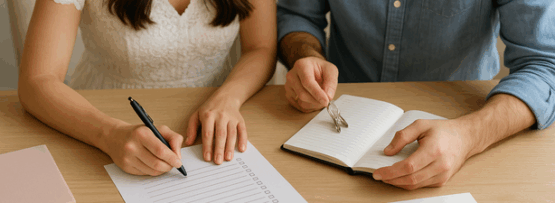「就職で得なのは英語か中国語か?」という問いは、業界や職種、働き方のイメージによって答えが変わります。大切なのは「自分にとっての得」を定義し、求人の母数、年収の伸びしろ、海外機会、学習コストのバランスで選ぶこと。本稿では、その考え方と実践の指針をわかりやすく整理します。
前提整理:「得」をどう定義するか
就職での「得」は次の4観点で測ると判断しやすくなります。
- 求人の母数と選択肢の広さ
- 年収とキャリアの天井(海外・管理職の可能性)
- 転職のしやすさ(汎用性・業界横断性)
- 学習コスト(到達までの時間と投資)
英語が有利なシーン
英語は「世界の共通語」です。IT・SaaS、コンサル、金融、研究開発、グローバル広報・マーケなど、国際プロジェクトが前提の仕事では英語がほぼ必須。求人の母数も圧倒的に広がり、海外拠点との連携や異動のチャンスも得られます。
メリット
- 業界横断の汎用性が高く、転職時に武器になる
- 最新情報・ツールへのアクセスが早い(技術・ビジネス動向)
- リモートワークや国際チームでの働き方と相性がよい
注意点
- 競争相手が多く、会議運営や交渉まで踏み込む運用力が差になる
- 「読む・書く」だけでなく「話す・聞く」の壁を越える必要がある
中国語が有利なシーン
製造業の調達・品質管理、半導体・電子部品のサプライチェーン、商社・越境EC、観光・小売のインバウンド対応など、アジア市場と結びつく仕事では中国語が即戦力になりやすいです。中国本土に加え、台湾や東南アジアの華人コミュニティとも接点が生まれます。
メリット
- 現場・交渉の場で信頼を得やすく、役割が明確に増える
- 国内勤務でも需要があり、若手でも「唯一性」を出しやすい
- 漢字文化圏の利点で、語彙の定着に有利な面がある
注意点
- 需要が地域・業種に偏ることがある(製造・観光・EC中心)
- 簡体字・繁体字、ビジネス慣習の違いに慣れる必要
学びやすさと到達コスト
英語は教材やコミュニティが豊富で、学習環境の整備がしやすい。一方でスピーキングの壁が最後まで残りがちです。中国語は声調・発音が最初のハードルですが、日本語話者は漢字の意味推測が効くため、中級以降の語彙拡張は比較的スムーズに進むこともあります。いずれも「使う前提」で学ぶと到達が早まります。
おすすめの学び方
- 英語:業界ニュースの多読+オンライン会議で週1回発話の実戦
- 中国語:ピンイン・声調の集中トレーニング+定型フレーズの対話反復
働き方トレンドと翻訳ツールの影響
国際的なリモート案件は英語が軸になりやすい一方、訪日需要やアジア調達の回復で中国語の現場価値も上昇。翻訳ツールは読み書きを強力に補助しますが、会議運営・関係構築・交渉設計は人の役割が残ります。最も差がつくのは「ツールで補いきれない運用力」です。
選び方の実践チェックリスト
- 目指す業界はIT・コンサル・外資系か?→英語優先
- 製造・商社・サプライチェーンに関心が強いか?→中国語優先
- 海外転職や長期駐在を狙うか?→英語で選択肢が広がる
- 国内で「代替されにくい役割」を早期に得たいか?→中国語で差別化
- 迷ったら「英語を土台+中国語を重点」や、その逆の二刀流も可
結論:目的に合わせて選ぶ、迷ったら順番で攻める
汎用性と求人の広さで見るなら英語、アジア現場での即戦力を狙うなら中国語。どちらが「絶対に得」ではなく、キャリア設計との相性がポイントです。迷う場合は「英語で土台を作りつつ、中国語で差別化」または、現在の業務に沿って逆の順番を選ぶのが現実的。まずは90日で「週1回の実戦(会議・会話)」「業界記事の要約発信」「面接で語れる成功事例化」を目標に、小さく始めて積み上げましょう。