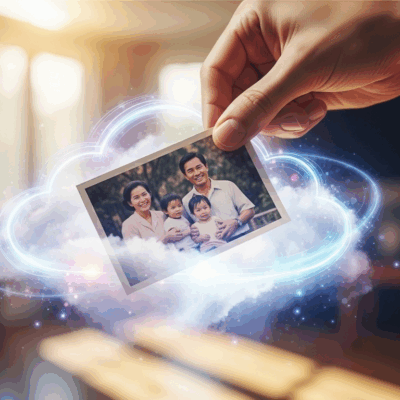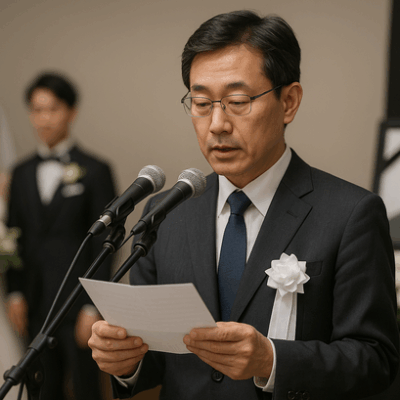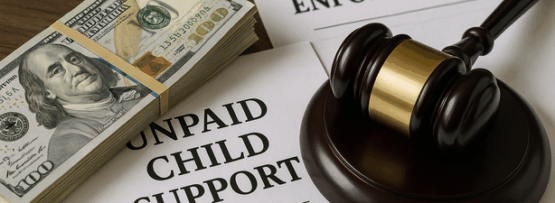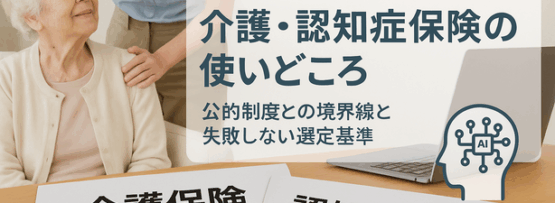「旅行好きが多い国」を語るとき、SNSの写真や出国者数だけでは実態がつかみにくいのが悩みどころです。そこで本稿では、住民が海外で使う「国際観光支出」と、そもそも海外に出られる前提となる「パスポート保有率」に注目。双方を手がかりに、生成AIの視点で“旅に出やすい・出たい”気持ちが強い国を推定するランキングを提示します。もちろん完全な答えではありませんが、旅文化や制度の違いを読み解くヒントになるはずです。
指標と考え方:二つのレンズで「旅しやすさ」を測る
前提とする指標は次の2点です。1) 住民の国際観光支出(海外での消費額)は「どれだけ外でお金を使い、旅を楽しんでいるか」の表れ。2) パスポート保有率は「海外旅行への心理的・制度的なハードルの低さ」を示す目安。これらを総合して、地理や文化・休暇制度も加味しながら、生成AIが総合判断した順位を作成しました。なお、直近年の統計差やパンデミック後の回復度合いで数値はぶれます。あくまで傾向をつかむ“参考ランキング”としてご覧ください。
生成AIが考える旅行好きが多い国ランキング:TOP10
- シンガポール:高いパスポート保有率、短距離で多様な渡航先、所得水準の高さが後押し。年に何度も近隣国へ出かける文化が根づく。
- ルクセンブルク:高所得かつ欧州域内移動の利便性が抜群。短期の周遊旅行が日常的で、支出も厚い。
- スイス:休暇をしっかり取る慣習と高所得。周辺国への越境旅行がしやすく、支出・保有率ともに高水準。
- ノルウェー:物価高ゆえ海外での消費に向かいやすく、長期休暇の文化も後押し。遠距離旅行への抵抗が小さい。
- アラブ首長国連邦:世界的ハブ空港を活用した外遊が盛ん。所得の高さと航空ネットワークの強さが目立つ。
- オランダ:休暇を旅に使う意識が強く、近隣欧州を頻繁に周遊。航空・鉄道の選択肢も豊富。
- イギリス:伝統的に海外旅行志向が強く、観光支出も大きい。多方面へ直行便が飛ぶ地の利も大きい。
- オーストラリア:近場でも長距離になる地理条件が、旅行計画を後押し。パスポート保有率も高めで外遊文化が根強い。
- 韓国:若年層を中心に海外志向が強く、近距離アジアへの週末旅行が一般化。パスポート保有率も高水準。
- 日本:国内旅行の活発さに比べパスポート保有率は相対的に控えめだが、円安下でも近隣アジアへの短期渡航は堅調で支出も底堅い。
見えてくる傾向:所得、制度、地理がカギ
- 所得と休暇制度:可処分所得が高く、有給やバカンスを取りやすい国ほど海外に出やすい。
- 地理とネットワーク:近場に国境が多い欧州や、ハブ空港を持つ国は、短期で頻度高く旅に出られる。
- パスポートの「心理的コスト」:取得の手間や費用、更新頻度の高さが、実際の渡航行動に影響。
このランキングの限界と、より公平に測るための案
国際観光支出は為替や物価で大きく変動し、パスポート保有率も国内旅行の豊かさを映しません。より公平に測るには、次の補助指標が有効です。
- 成人1人当たりの年平均出国回数(仕事・観光の切り分けつき)
- 国内旅行の延べ宿泊数や観光支出(「旅好き」を国内にも拡張)
- 有給消化率・連続休暇取得日数
- LCC路線密度や直行便の充実度(アクセスの良さ)
読者への実用ヒント:旅を「出やすく」するコツ
- まずパスポートの有効期限を確認・更新。早割・閑散期を狙うと費用対効果が高い。
- 直行便に固執せず、ハブ空港経由を使うと選択肢と価格が広がる。
- 3〜4日の短い休みでも近距離で満足度の高い都市を選べば、旅の回数は増やせる。
- 旅費の一部を「定額積立」にして、思い立ったときに動ける準備を。
指標はあくまで地図。あなたの「行きたい!」が目的地です。データを味方に、小さく軽やかに次の一歩を。