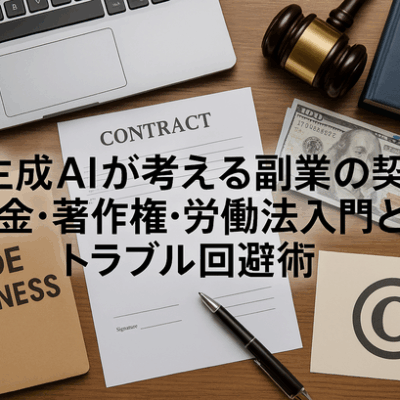ジーンズの右前にある小さな“あのポケット”。正式な名前も使い道も人それぞれで、「なくても困らないのに、なぜ残っているの?」という素朴な疑問がよく挙がります。本稿では、その由来や役割の変化を整理しつつ、現代のライフスタイルに合わせた使い方や、もし改良するならどんなアイデアがあるかを考えてみます。歴史の断片をたどると、あの小さな布地には、意外な物語が縫い込まれていました。
懐中時計のための“巣”から始まった
コインポケットの原型は、19世紀後半のアメリカ西部で働く人々が愛用した懐中時計を守るための「ウォッチポケット」。ジーンズが労働着として進化するなかで、時計の鎖が引っかかったり本体が傷ついたりしないように、小さく深めのポケットが追加されました。ベルトループが一般化する以前、サスペンダーで吊った作業ズボンに懐中時計を収めるスペースは、まさに実用上の必需品だったのです。
呼び名と用途の移り変わり
やがて腕時計が普及し、懐中時計の需要は減少。小さなポケットは「コインポケット」と呼ばれるようになり、硬貨や切符、ライター、ギターピック、指輪など、細かな持ち物のための“定位置”になっていきます。スマホ中心の時代になっても、小さな必需品を固定しておけるスペースとしての価値は意外に高く、出し入れが少なく落としたくない物を入れるニッチな役割を担い続けています。
タフさを支える作りの工夫
コインポケットは、負荷がかかりやすい開口部の角を補強するためにリベットやカンヌキ止め(太い糸で縫い固める手法)が使われます。本体ポケットの内側に重ねる構造のため、布が二重三重になり、摩耗に強いのが特徴。形状は角ばったもの、丸みのあるもの、やや斜めに開くものなどブランドによって差があり、この“違い”こそが各社のアイデンティティの一部になっています。
なぜ今も残るのか—デザインの記号として
実用一辺倒の時代を過ぎても、コインポケットが廃れないのは「ジーンズらしさ」を構成する記号のひとつだから。五つのポケット(ウォッチポケットを含む「5ポケット」)という語感や、見慣れた配置がもたらす安心感は、日常着の文化遺産といってよいほど定着しています。歴史の継続性を感じさせる小さなディテールは、着る人にとっての楽しみでもあるのです。
現代に合う使い方とミニ改良アイデア
キャッシュレス時代でも、コインポケットは活躍の余地あり。たとえばワイヤレスイヤホンの片側、予備の自転車鍵、常備薬の小袋、交通系ICのホルダー(ケースに入れて)など、なくすと困る小物に向いています。もし改良するなら、内側に薄い滑り止め素材を縫い付ける、小さなループで落下防止ストラップを留められるようにする、縁に反射糸を使って夜間の視認性を高める、といった“足し算”が考えられます。逆に、深さを2〜3ミリ浅くして指先が届きやすくする“引き算”も有効です。
ビンテージを楽しむ人への小さな手がかり
- 開口部のリベット有無や位置:年代・モデルの差異が出やすい部分。
- 口布のステッチ本数や糸色:ブランドの時期ごとの仕様変更が表れます。
- セルビッジ生地の耳が見えるか:一部モデルでは内側に赤耳がのぞくことも。
これらはあくまで目安で、同年代でも生産ロットや工場で差がある点にはご注意を。
小さなポケットに宿る“大きな物語”
コインポケットは、ただの飾りではありません。働く人の道具を守るために生まれ、時代ごとに役目を変え、いまは伝統と便利さを両立させるディテールとして息づいています。デザインの背景を知ると、毎朝ジーンズに手を通す動作にも少し温度が宿るはず。今日のあなたは、そこに何を入れますか?