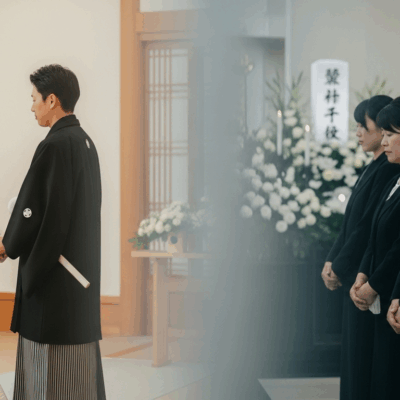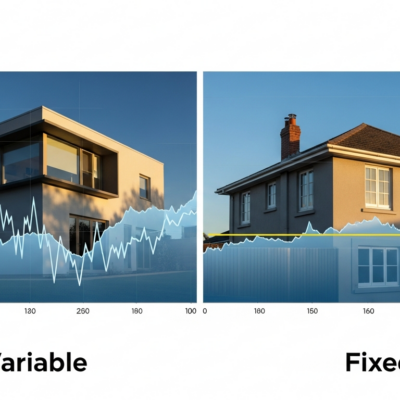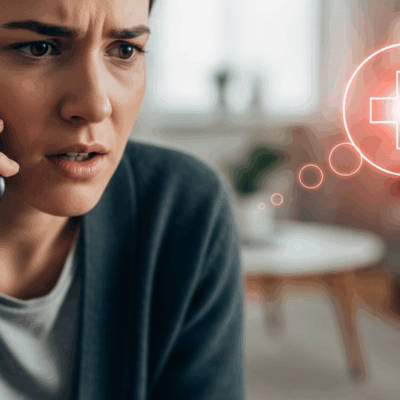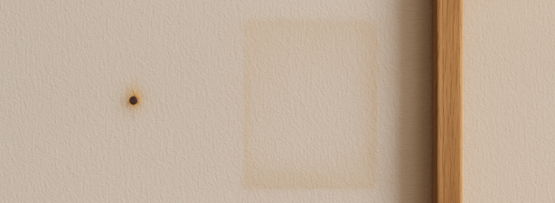動画が途切れる、オンライン会議が急に固まる──そんな時に限ってキッチンでは電子レンジが稼働中。実はこの「あるある」、理由があります。本稿では、なぜ電子レンジがWi‑Fiと干渉するのか、その背景にある2.4GHzという周波数の事情をわかりやすく整理し、家庭で実践できる簡単な対策を提案します。難しい設定を増やさず、今日からできる“つながりやすさ”の改善ヒントをまとめました。
なぜ電子レンジとWi‑Fiがぶつかるのか
電子レンジは食品中の水分を効率よく温めるため、2.45GHz付近を使います。この帯域は「ISMバンド」と呼ばれ、免許なしで使える代わりに家電や通信が共存しています。一方、Wi‑Fiの2.4GHz帯も同じ周波数を利用。レンジの動作中には広い帯域にノイズが出やすく、完全に遮蔽されていても近くでは微弱な電波ゆらぎが生じ、Wi‑Fiの受信感度が下がります。結果として、スループット低下や再送増加が起こり、体感として「遅い」「途切れる」になります。
それでも2.4GHzが使われ続ける理由
2.4GHz帯は回り込みやすく、壁越しでも届きやすいという長所があります。省電力に向き、IoT機器やスマート家電、Bluetooth機器なども多数がこの帯域を利用。つまり「混雑しやすいけれど、便利で手放しにくい」のが現実です。だからこそ、うまく付き合うための使い分けと配置がカギになります。
家庭で起きがちな“干渉のサイン”
- 電子レンジ稼働中だけ動画がカクつく、音声通話がプツプツ途切れる
- キッチン付近を通るとWi‑Fiが弱くなる、速度測定の数値が不安定
- Bluetoothスピーカーの音が歪む、マウスやキーボードがもたつく
今日からできる実践的な対策
- 距離と配置を見直す:ルーターや中継機を電子レンジから2〜3m以上離し、高い位置に設置。金属棚やレンジの真横・背面は避ける。
- 5GHz(または6GHz)を積極活用:対応端末は高速で干渉の少ない5GHz/6GHzへ。SSIDを2.4GHzと分け、主要端末は高速帯に常時接続させる。
- 2.4GHzのチャンネル最適化:1/6/11のいずれかに固定し、帯域幅は20MHzに。自動設定で不安定なら手動で混雑の少ないチャンネルを選ぶ。
- メッシュWi‑Fiで動線を最適化:キッチンを電波の“中継点”にしない。ノードを回遊導線から外し、電子レンジと別の経路で家中に配る。
- 有線をうまく併用:在宅勤務PCや据え置きゲーム機はLANケーブルや電力線アダプターを検討し、無線の混雑を減らす。
- 同居機器の整理:2.4GHzを使うスマート家電・ベビーモニター・古い無線機器が多いと混雑しやすい。必要な機器だけ稼働させる。
- 機器の更新を検討:古いルーターは干渉耐性や制御機能が弱い場合あり。Wi‑Fi 5以降(できればWi‑Fi 6/6E)対応への更新は効果的。
簡単チェックで“原因の切り分け”
スマホの速度測定アプリやWi‑Fiアナライザーで、電子レンジのオン/オフ時の速度や信号強度を比べてみましょう。レンジ稼働と同時に速度が落ちるなら、2.4GHzの干渉が疑われます。対策後に再測定すると、改善度合いが把握しやすく、次の手も打ちやすくなります。
まとめ:使い分けと配置で“静かな電波環境”に
電子レンジと2.4GHz Wi‑Fiが同居するのは、便利さと引き換えの必然です。だからこそ、距離・配置・帯域の使い分けという基本を抑えるだけで体感は大きく変わります。まずは「レンジから離す」「主要端末は5GHzへ」「2.4GHzは1/6/11に固定」の三点セットから。小さな工夫の積み重ねが、家中のつながりやすさを底上げします。