「親しい友人にお金を貸したけれど、返済の約束を忘れられているみたい…」「もう何年も前の話だし、今さら請求できるのかな?」そんな、人間関係が絡むお金のトラブルは、非常にデリケートで悩ましい問題ですよね。親しい仲だからこそ強く言えず、時間が経つにつれて諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、貸したお金を返してもらう権利には「時効」という期限があることをご存知でしょうか。この時効を知らないままでいると、本来返してもらえるはずのお金を取り戻せなくなるかもしれません。一方で、正しい知識と手順さえ踏めば、時効の進行を止めたり、リセットしたりすることも可能です。
今回は、そんな悩ましいお金の貸し借りについて、最新の生成AIに『時効と正しい請求手順』を尋ねてみました。その回答を基に、法律雑学の専門家として、誰にでも分かりやすく解説していきます。
貸したお金の時効はいつ?意外と知らない基本ルール
まず最初に、最も重要な「時効」について見ていきましょう。かつては、貸した相手が個人か会社かによって時効期間が異なるなど、少し複雑なルールでした。しかし、2020年4月1日に民法が改正され、ルールがよりシンプルで分かりやすくなっています。
【2020年4月1日以降の貸し借り】
新しい民法では、時効期間は以下のいずれか早い方と定められました。
- 権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
個人の間でお金を貸す場合、貸した側は「返してもらえる権利があること」を当然知っていますよね。そのため、基本的には「5年」が時効期間になると考えておけば問題ありません。
では、この「5年」はいつから数え始めるのでしょうか?
- 返済期限を決めていた場合:その返済期限の翌日から5年
- 返済期限を決めていなかった場合:お金を貸した日の翌日から5年
例えば、「2021年5月1日に貸して、返済期限は2022年4月30日」という約束だった場合、時効は2022年5月1日から5年間、つまり2027年4月30日が経過すると完成する可能性があります。
【2020年3月31日以前の貸し借り】
もし、お金を貸したのが民法改正前だった場合は、古いルールが適用されます。この場合の時効期間は、原則として「10年」です。ただし、相手が会社や個人事業主といった「商人」である場合は、商事時効が適用されて「5年」となります。ご自身のケースがどちらに当てはまるか、お金を貸した日をしっかり確認しましょう。
「もう時効かも…」と諦めるのは早い!時効をストップ&リセットする方法
「計算してみたら5年が過ぎてしまいそう…」と焦った方もいるかもしれません。でも、ご安心ください。時効は、ただ時間が経てば自動的に成立するわけではありません。相手が「時効なので払いません」と主張(これを「時効の援用」と言います)して初めて効果が生まれるのです。
そして、こちら側からアクションを起こすことで、時効のカウントを一時停止させたり、リセットしてゼロから数え直しにさせたりすることができます。これを「時効の完成猶予」と「時効の更新」と言います。
【時効の更新(リセット)】
時効がリセットされ、新たにカウントが始まる強力な方法です。
- 裁判上の請求:訴訟を起こしたり、支払督促を申し立てたりすること。裁判で判決が確定すれば、そこから新たに時効期間が10年となります。
- 相手の承認:相手に「借金がある」と認めさせることです。これが最も現実的で効果的な方法です。「少しでいいから返してほしい」と伝えて一部でも返済してもらったり、「支払いを少し待ってほしい」といった内容の念書を書いてもらったりすれば、その時点で時効はリセットされます。口約束だけでなく、書面やメール、LINEのやり取りなど、証拠に残すことが非常に重要です。
【時効の完成猶予(一時停止)】
時効の完成を一時的にストップさせる方法です。
- 内容証明郵便による催告:「〇月〇日までに貸したお金を返してください」という内容の請求書を、内容証明郵便で送ります。これにより、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。ただし、これはあくまで一時的な措置なので、その6ヶ月の間に裁判などの法的な手続きを進める必要があります。
専門家が教える!貸したお金を請求する正しい3ステップ
では、実際に貸したお金を返してもらうには、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。感情的にならず、冷静に段階を踏んでいくことが大切です。
ステップ1:まずは証拠の確認と穏やかな話し合い
いきなり法的な手段に出るのではなく、まずは冷静に話し合いましょう。その前に、貸し借りを証明できる証拠が手元にあるか確認します。借用書がなくても、銀行の振込履歴や、「お金を貸してくれてありがとう」といった内容のメールやLINEのやり取りも有効な証拠になります。
その上で、「以前貸したお金の件なんだけど、そろそろ返してもらえるかな?」と穏やかに切り出してみましょう。相手が単に忘れているだけの可能性もあります。
ステップ2:内容証明郵便で正式に請求する
話し合いに応じてもらえなかったり、約束を破られたりした場合は、次のステップに進みます。ここで有効なのが「内容証明郵便」です。これは、いつ、誰が、どのような内容の手紙を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
「〇月〇日までに返済がない場合、やむを得ず法的な手続きを検討します」といった内容を記載して送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与え、本気度を示すことができます。前述の通り、これは時効の完成を6ヶ月間ストップさせる効果もあります。
ステップ3:簡易裁判所での手続きを検討する
内容証明郵便を送っても反応がない場合は、いよいよ法的な手続きを検討します。弁護士に依頼する本格的な訴訟はハードルが高いと感じるかもしれませんが、個人でも利用しやすい制度があります。
- 支払督促:書類審査のみで、裁判所から相手に支払いを命じてもらう手続きです。相手が異議を申し立てなければ、強制執行(給料や預金の差押えなど)が可能になります。
- 少額訴訟:請求額が60万円以下の場合に利用できる、原則1回の期日で判決が出るスピーディーな裁判手続きです。
これらの手続きは比較的費用も安く、手続きもシンプルなので、最終手段として検討してみましょう。もちろん、手続きに不安がある場合や、請求額が大きい場合は、弁護士などの専門家に相談するのが最善の道です。
お金の貸し借りは、信頼関係の証でもありますが、時としてその関係を壊す原因にもなり得ます。大切なのは、問題を先送りにせず、正しい知識を持って冷静に対応することです。もし悩んでいるなら、まずはこの記事を参考に、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。



















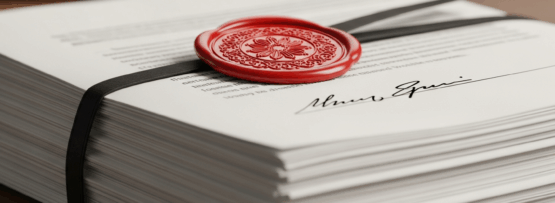

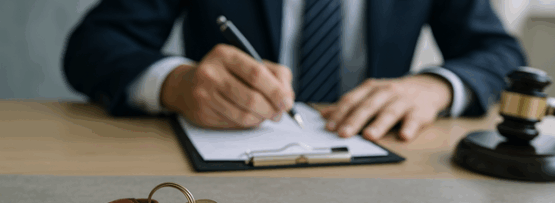

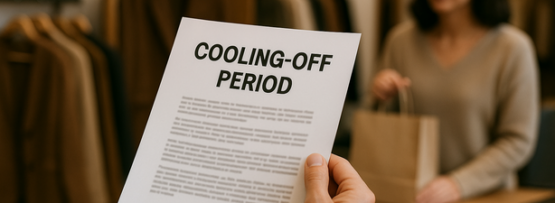
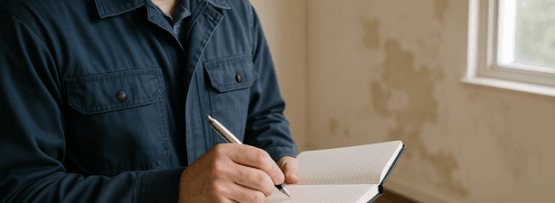


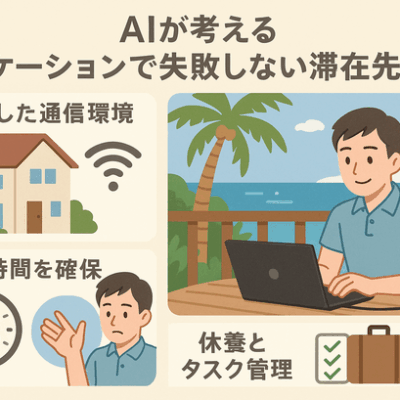

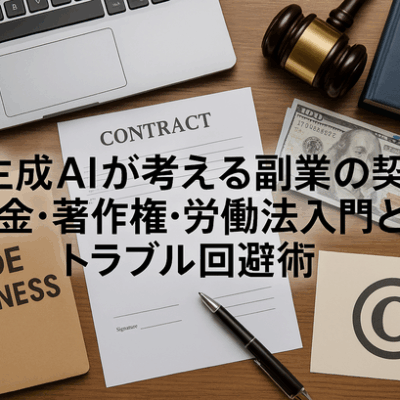
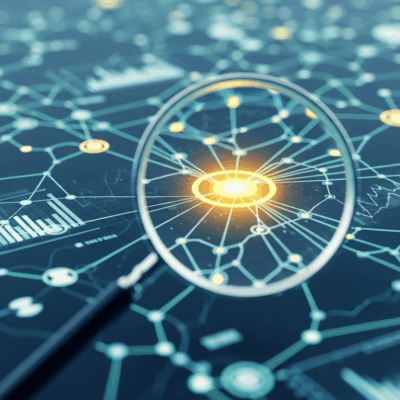

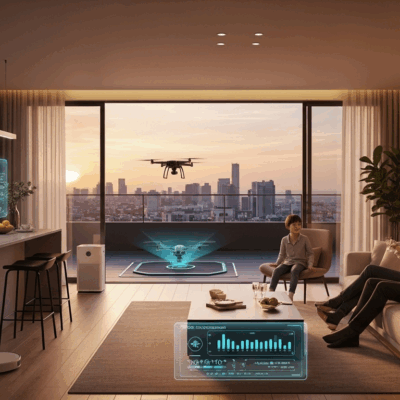
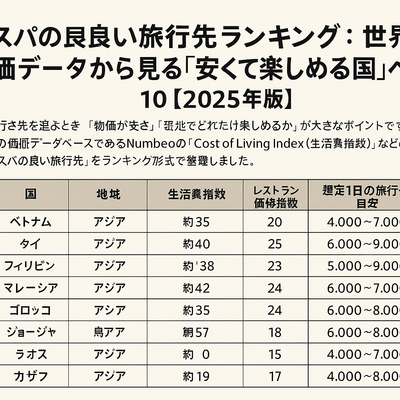







この記事へのコメントはありません。