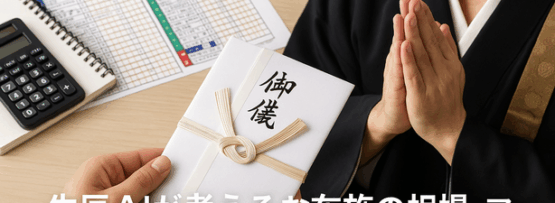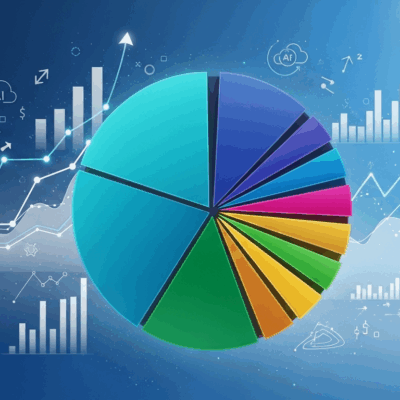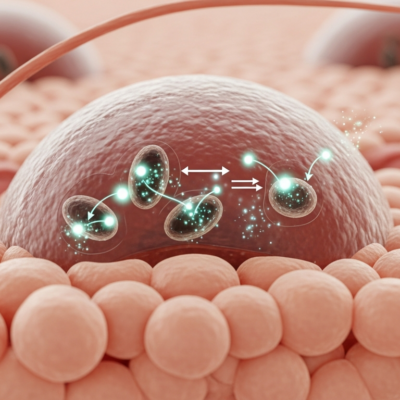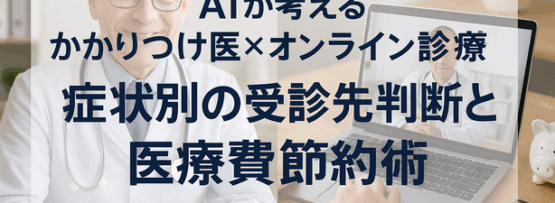「お葬式」と聞くと、多くの方が「突然のことで何から手をつけていいかわからない」「費用がいくらかかるのか不安」といった漠然とした悩みを抱えるのではないでしょうか。かつては地域や家の慣習に沿って行われるのが当たり前でしたが、家族の形や価値観が多様化する現代において、お葬式のあり方も大きく変化しています。一体、今の時代に合ったお葬式とはどのようなものなのでしょうか。
今回は、最新の技術である生成AIに「現代のお葬式トレンドと費用を抑える新常識」について尋ねてみました。専門家である私の視点も交えながら、AIが導き出した答えを紐解き、これからの時代のお葬式を考えるヒントをお届けします。
「小さく、心温まる」が主流に?生成AIが示すお葬式のトレンド
生成AIに現代のお葬式のトレンドを尋ねると、まずキーワードとして挙がってきたのが「小規模化」と「多様化」です。これは、私が現場で感じている実感とも非常に近いものです。
・家族葬や一日葬の一般化
かつては一般葬と呼ばれる、ご近所の方や会社関係者なども広く招くお葬式が主流でした。しかし現在では、ごく近しい親族や親しい友人だけで故人を送る「家族葬」や、お通夜を省略して告別式と火葬を一日で行う「一日葬」を選ぶ方が圧倒的に増えています。これには、核家族化や地域のつながりの希薄化といった社会背景に加え、新型コロナウイルスの影響が大きく関係しています。多くの人が集まることを避ける風潮が、小規模なお葬式のスタイルをさらに後押ししたのです。
・形式にとらわれない「無宗教葬」
特定の宗教儀礼に則らず、自由な形式で故人を見送る「無宗教葬」も注目されています。故人が好きだった音楽を流す「音楽葬」や、思い出の写真を飾り、食事をしながら語り合う「お別れ会」のようなスタイルです。これは、「堅苦しい儀式よりも、故人らしさを大切にしたい」「自分たちの言葉で感謝を伝えたい」という、遺族の想いの表れと言えるでしょう。
・オンライン参列という新しい選択肢
遠方に住んでいたり、高齢や病気で移動が難しかったりする方のために、お葬式の様子をインターネットでライブ配信する「オンライン参列」も登場しました。物理的な距離を超えて、大切な人との最後のお別れに参加できるこの方法は、現代ならではの優しい選択肢として広がりつつあります。
賢く費用を抑える!AIが提案する3つの新常識
お葬式で最も気になることの一つが費用です。生成AIは、費用を賢く抑えるための「新常識」として、非常に合理的で実践的な3つのポイントを挙げてくれました。
新常識①:葬儀社は「比較して選ぶ」時代
「お葬式は突然のことだから、急いで決めなければならない」というのは、もはや過去の常識かもしれません。今は、多くの方が元気なうちに「事前相談」を利用し、複数の葬儀社から見積もりを取っています。実は、同じような内容のお葬式でも、葬儀社によって費用が数十万円単位で変わることは珍しくありません。事前に内容と費用を比較検討することで、冷静に、そして納得のいく葬儀社を選ぶことができます。
新常識②:「当たり前」のオプションを見直す
お葬式の見積もりには、祭壇のグレード、返礼品、通夜振る舞いの食事など、様々な項目が含まれています。ここで大切なのが、「これは本当に必要だろうか?」と一つひとつ見直す視点です。例えば、立派な生花祭壇も素敵ですが、故人の好きだったお花や思い出の品々を飾る手作りの祭壇でも、温かい雰囲気は作れます。参列者の人数を考え、過剰な飲食や返礼品を避けることも、費用を抑える大きなポイントになります。
新常識③:公的な補助金を忘れずに活用する
意外と知られていないのが、公的な補助金の存在です。国民健康保険や社会保険の加入者が亡くなった場合、申請すれば「葬祭費」や「埋葬料」として数万円(自治体や組合によって金額は異なります)が支給されます。自動的に支払われるものではないため、自分で申請する必要がありますが、手続きは決して難しくありません。こうした制度をしっかりと活用することも、賢く費用を抑えるための重要な知識です。
大切なのは「故人を想う気持ち」と「家族の納得」
生成AIが示したトレンドや新常識は、現代社会の変化を的確に捉えたものでした。お葬式は、豪華さや規模を競うものではありません。大切なのは、遺された家族が「故人らしい、良いお見送りができた」と心から思えることです。
費用を抑えることは、決して故人への想いを軽んじることにはなりません。むしろ、無駄な出費をなくすことで、心に余裕が生まれ、より深く故人を偲ぶ時間を持つことにつながるのではないでしょうか。
これからの時代のお葬式は、「こうでなければならない」という固定観念から解放され、より自由に、よりパーソナルなものになっていくでしょう。今回ご紹介したAIの視点を参考に、ぜひ一度、ご家族と「自分たちらしいお別れの形」について話し合ってみてはいかがでしょうか。