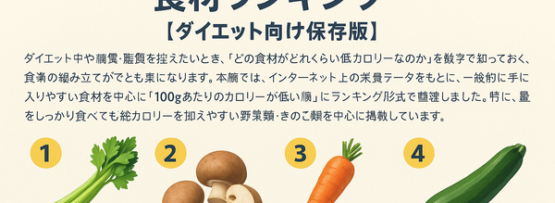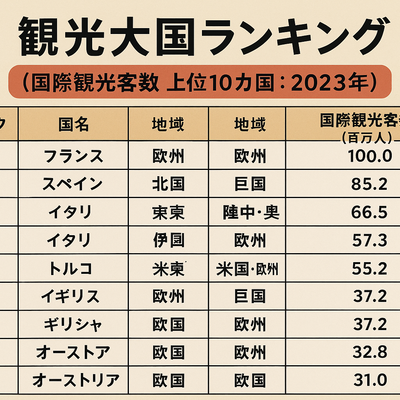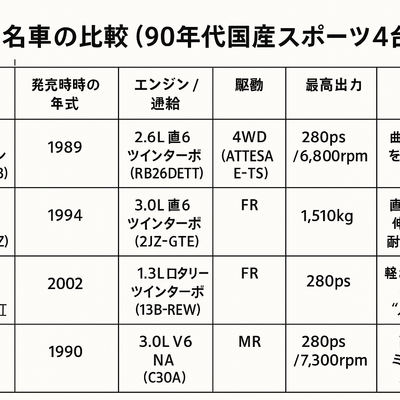皆さん、こんにちは!普段はパスタやピッツァ、イタリア各地の郷土料理についてお話しすることが多い私ですが、今日は少し趣向を変えてみたいと思います。最近、世間を賑わせている「生成AI」。料理の世界でもレシピ開発などで活用され始めていますが、このAIに「食文化」について尋ねたら、どんな答えが返ってくるのでしょうか?
料理人としての好奇心から、今回は「日本と韓国の家庭料理の共通点」という、私にとっては専門外ながらも非常に興味深いテーマをAIに投げかけてみることにしました。地理的には近い両国ですが、料理のスタイルは似ているようで大きく異なります。果たしてAIは、その食文化の根底に流れる共通項をどのように分析するのでしょうか。イタリア料理を愛する私の視点も交えながら、AIが導き出した答えを一緒に見ていきましょう。
生成AIに聞いてみた:日本と韓国の家庭料理、その意外な共通点とは?
早速、いくつかの生成AIに「日本と韓国の家庭料理に見られる共通点を、具体的な例を挙げて教えてください」と尋ねてみました。すると、驚くほど整理された、的確な答えが返ってきました。AIが挙げた主な共通点は以下の通りです。
- 主食が米であること
- 発酵食品を多用する文化
- だし(出汁)を料理のベースにすること
- 食卓に汁物が欠かせないこと
- 野菜や海産物を活かした副菜が豊富なこと
なるほど、確かにどれも頷けるものばかりです。AIは膨大なデータの中から、これらの共通項を見事に抽出してみせました。では、これらのポイントをもう少し深掘りしながら、私なりの考察を加えてみたいと思います。
主食はやっぱり「お米」!食文化の土台
まずAIが指摘したのが、両国とも「米」を主食としている点です。これは最も基本的で、そして最も重要な共通点と言えるでしょう。イタリアではパスタやパンが主食のイメージですが、北部ではリゾットなどお米もよく食べられます。しかし、日本と韓国におけるお米の存在は、単なるエネルギー源にとどまりません。
一粒一粒が輝く炊き立てのご飯を中心に、おかずや汁物をどう組み合わせるか。この「ご飯をおいしく食べる」という発想が、両国の家庭料理の献立を形作っています。キムチチゲも、肉じゃがも、その先にはいつも白いご飯がある。この感覚は、両国の食文化の根幹を成すものであり、AIが最初にこれを指摘したのは非常に的を射ていると感じました。
旨味の秘訣!「発酵」と「だし」の文化
次にAIが挙げた「発酵」と「だし」。これは料理の味の根幹を支える、いわば両国の「魂」とも言える部分です。
日本の家庭に味噌や醤油が欠かせないように、韓国の家庭にはテンジャン(韓国味噌)やカンジャン(韓国醤油)、そしてコチュジャンがあります。どちらも大豆を主原料とした発酵調味料であり、料理に深いコクと旨味を与えてくれます。また、日本の「漬物」と韓国の「キムチ」も、野菜を発酵させて保存性を高め、食卓に彩りと風味豊かなアクセントを加えるという点で共通しています。イタリアにもチーズやサラミ、ワインといった素晴らしい発酵食品がありますが、大豆をベースにしたアジアの発酵文化の奥深さには、いつも驚かされます。
そして「だし」。日本料理では昆布や鰹節が、韓国料理では煮干しや昆布、野菜などがよく使われます。この「だし」で素材の旨味を最大限に引き出すという考え方は、イタリア料理における「ブロード」(野菜や肉からとる出汁)の役割と非常によく似ています。美味しいスープや煮込み料理のベースには、必ず丁寧にとられた出汁がある。これは世界中の美味しい家庭料理に共通する「黄金律」なのかもしれませんね。
食卓を彩る名脇役たち:汁物と豊富な副菜
日本の食卓に「味噌汁」があるように、韓国の食卓には「チゲ」や「クッ(スープ)」があります。温かい汁物が一つあるだけで、食卓は豊かになり、心も体も温まる。これもまた、AIが的確に指摘した共通点です。
さらに、主食と主菜の他に、たくさんの副菜が並ぶのも特徴です。日本では旬の野菜を使った「おひたし」や「和え物」、韓国では「ナムル」がその代表格でしょう。たくさんの小皿がテーブルに並ぶ光景は、見た目にも楽しく、栄養バランスも自然と整います。これは、イタリア料理で食事の始まりに様々な小皿料理を楽しむ「アンティパスト」の文化にも通じるものがあります。限られた食材を工夫して、食卓を豊かにしようという、家庭料理ならではの知恵と愛情が感じられる部分です。
AIの分析から見えてくるもの、そしてその先へ
今回、生成AIに日本と韓国の家庭料理について尋ねてみて、その分析能力の高さに正直驚かされました。食材、調理法、食文化の形式といった客観的なデータを整理し、共通点を抽出する能力は、人間以上かもしれません。
しかし、AIの回答を眺めながら、一つだけ足りないものを感じました。それは、家庭料理の背景にある「想い」です。なぜ、たくさんの副菜を作るのか。それは家族に色々なものを食べて健康でいてほしいという願いの表れです。なぜ、手間をかけてだしをとるのか。それは、素材の味を大切にし、食べる人に「美味しい」と感じてほしいという愛情です。
AIは「一汁三菜という形式がある」と教えてくれますが、その根底にある「家族を想う心」や、旬の食材を前に「今日は何を作ろうか」と考える楽しみ、そして食卓を囲む家族の笑顔といった、情緒的な文脈までは語ってくれません。
生成AIは、食文化を理解するための強力なツールです。しかし、そのデータや分析の先にある「人の営み」に想いを馳せることが、本当の意味で文化を理解することに繋がるのではないでしょうか。日本と韓国、そしてイタリアも。国や文化は違えど、大切な人のために作る家庭料理の根底に流れる温かい想いは、きっと世界共通なのだと、AIとの対話を通じて改めて感じさせられました。