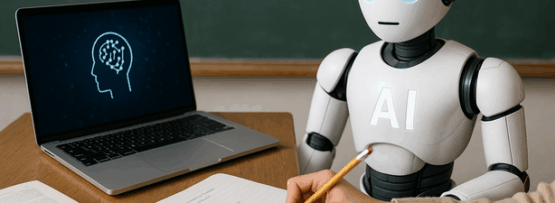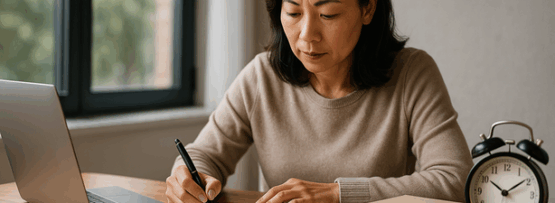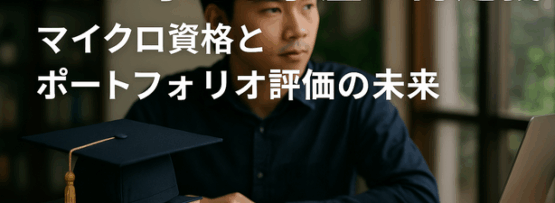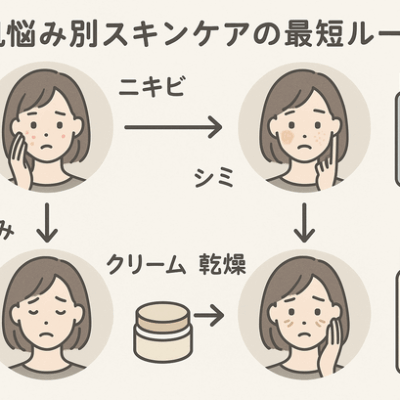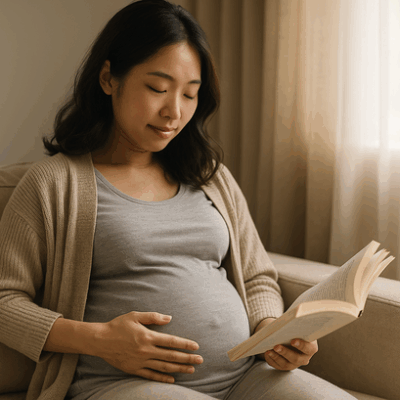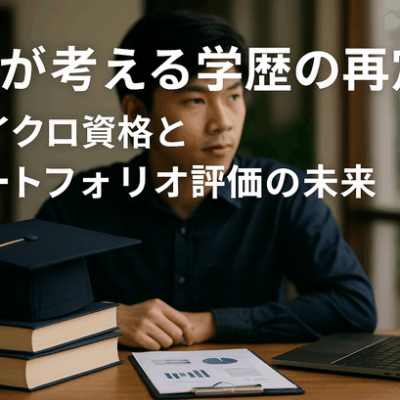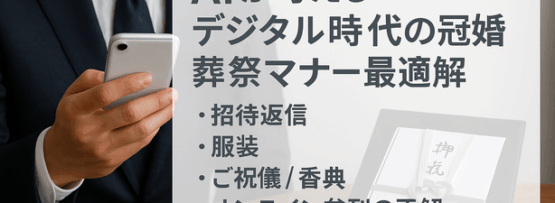「胎教」という言葉には、良かれと思っても何をどうすればよいか分からない戸惑いと、神話のような期待が混ざりがちです。本稿では、妊娠期の親子が心地よく過ごすために役立つ、科学的に納得できる考え方とシンプルな実践を整理します。結論から言えば、特別な“裏ワザ”よりも、無理のないリラックスと日々のコミュニケーションが鍵です。
なぜ「胎教」は誤解されやすいのか
「特定の音楽でIQが上がる」「英語のCDで語学力がつく」などの主張は魅力的ですが、決定的な根拠は乏しいのが実情です。胎児はお母さんの体を通じて外界の音をぼんやりと感じますが、直接的に能力が“上がる”と断言できる研究は限られています。過度な期待は、できなかったときの不安や罪悪感を生みやすく、むしろ逆効果になりかねません。
科学が示す「できること・できないこと」
妊娠後期になると、低めの音やリズム、声の抑揚などを感じ取るようになります。特に、お母さんの声や心拍、呼吸のリズムは日常的な“音の環境”として胎児に届きます。ただし、音や教材で性格や将来の能力が決定されるわけではありません。確かなのは、親が落ち着いて過ごせる時間をつくることが、結果として赤ちゃんにも穏やかな刺激をもたらす、というシンプルな事実です。
毎日のシンプルな実践アイデア
- 短い語りかけ:今日あったことを1~2分、やさしい声で話す。内容は天気や食べたものなどで十分。
- 音楽は“自分が心地よい”を基準に:好きな曲を小さめの音で。歌いたくなったら鼻歌でもOK。
- 呼吸と姿勢:深呼吸で肩の力を抜き、楽な姿勢で数分ぼんやりと過ごす“ゆったりタイム”をつくる。
- 生活のリズム:無理のない散歩や軽いストレッチ、ぬるめの入浴、画面オフの時間など、心身が整う習慣を優先。
- 家族の参加:パートナーも短く語りかけたり一緒に音楽を聴いたり。共有体験が安心感を育てます。
やりすぎないための注意点
お腹に直接イヤホンを当てたり、大きすぎる音を長時間流すのは避けましょう。教材を増やし続けるより、少ないことを気楽に続ける方が効果的です。SNSで見かける“これをしないと遅れる”といった断定には距離を置き、自分のペースを大切に。心配ごとが続くときは、身近な専門職に相談して安心材料を増やすことが、結果的に良い環境づくりにつながります。
家族で育む環境づくりとまとめ
胎教の核心は、特別な訓練ではなく、日常の安心を積み重ねることにあります。完璧を目指さなくて大丈夫。うまくいかない日があっても、次の日に短い語りかけや深呼吸を一回できれば十分です。親が心地よく過ごす時間が増えるほど、家族の空気は自然とやわらかくなり、その“空気”こそが赤ちゃんへの最良のメッセージになります。情報に振り回されず、自分たちにとって無理のないやり方で、穏やかな毎日をデザインしていきましょう。