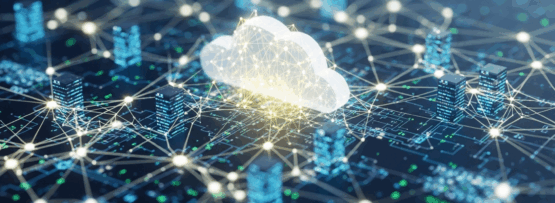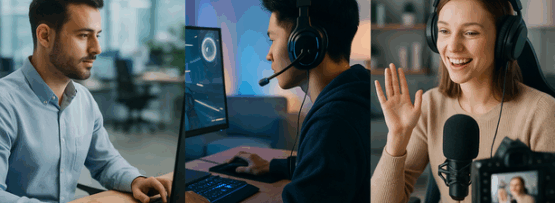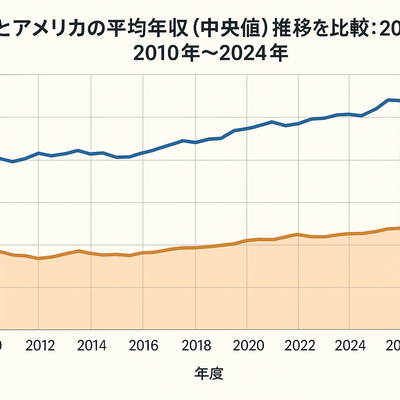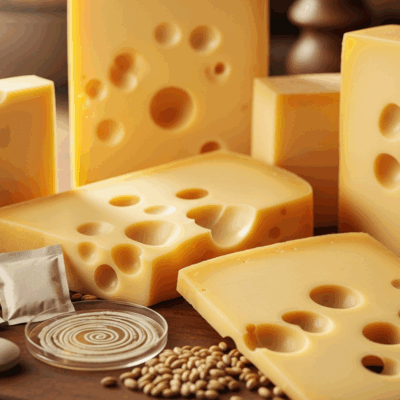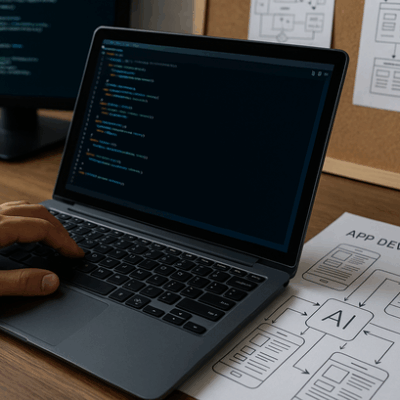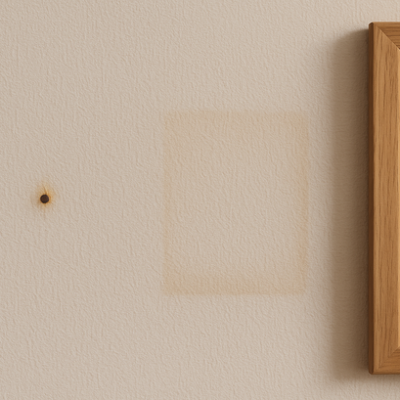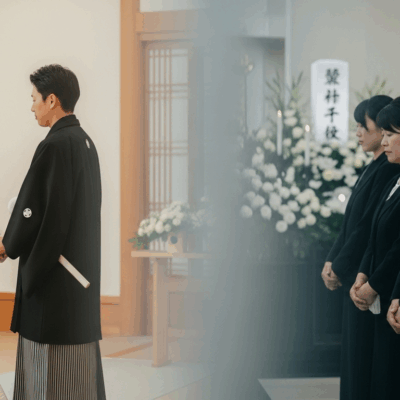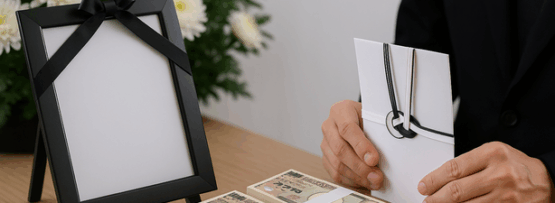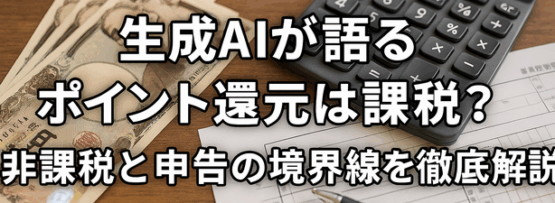クラウドのインフラ設計は、便利さと引き換えに「いつの間にか複雑」「運用が手作業だらけ」「コストが読めない」という課題を抱えがちです。本稿の提案はシンプルです。目的から逆算し、最小構成で始めて自動化と観測で育てる。信頼性とコスト、セキュリティを“あと付け”ではなく設計に埋め込み、変化に強い基盤をつくることです。
目的を先に言語化する ― 何を守り、どこで妥協するか
まず「どのくらい止められないのか(目標の稼働・復旧時間)」「ピークはいつ来るのか」「扱うデータの機密性はどの程度か」を一枚にまとめます。ここで決まるのは技術そのものではなく、優先順位です。可用性が最優先なら冗長化を厚く、コスト重視ならシンプルさと自動停止を重視、といった判断の軸がぶれなくなります。
最小構成から始めて、水平に伸ばす
最初から“将来のための大規模設計”を入れ込むと、運用負荷とコストが先に膨らみます。最小限のネットワーク、コンピュート、ストレージで始め、負荷に応じて横に増やす(スケールアウト)方針にします。アプリはできるだけ状態を持たず、セッションやファイルは共有ストレージやマネージドサービスに逃がすと伸ばしやすくなります。
信頼性は「分散」と「自動復旧」でつくる
単一の場所や機器に依存しないことが基本です。複数のゾーンに分散し、ヘルスチェックと自動切替で故障時の復旧を機械に任せます。更新時は一度に全体を変えず、段階的な切替(ブルーグリーンや小さな段階的リリース)でリスクを局所化します。
コストは設計で決まる ― 見える化と自動オフ
使った分だけ請求されるため、見えない無駄が増えがちです。サイズの適正化(小さめで開始、必要に応じて拡大)と、自動停止・自動スケールを標準にします。保存期間に応じてストレージ階層を分け、外部へのデータ転送など“見落としがちな費用”も定期的に見直します。
セキュリティはデフォルト閉じる
最初から「許可しない」を基本に設計します。必要最小限の権限付与、ネットワークの分離、秘密情報は専用の保管サービスに置く、通信と保存の暗号化を標準にする、といった基礎を徹底します。監査ログは必ず集約し、誰が何をしたかを後から追えるようにします。
観測可能性を仕込む ― 見えないものは直せない
ログ、メトリクス、トレースを最初から集め、アプリとインフラを同じダッシュボードで眺められるようにします。「どの指標が利用者の体験に直結するか」を決め、目標値とアラートの閾値を合わせます。障害対応の手順書(ランブック)を用意し、定期的に見直します。
変更は怖くない仕組みに ― 設定はコードで管理
手作業の変更はミスと差分の温床です。インフラの状態をコードで記述し、レビューしてから反映する流れを整えます。テスト用・本番用の環境を分け、同じ手順で再現できるようにしておけば、変更のスピードと安全性が両立します。
マルチクラウドは手段 ― 持ち運べる単位を決める
複数クラウドの併用は万能ではありません。目的が冗長化なのか、コスト最適化なのかを明確にし、「どこまでを共通化するか」を決めます。コンテナや共通のデプロイ手順で“持ち運べる単位”を作り、データベースなど移しづらい部分は慎重に選びます。
小さく試し、学び続ける運用へ
計画だけでは分からないことが多いため、定期的にテスト故障や訓練を行い、手順と設計の穴を見つけます。振り返りは責任追及ではなく、仕組みの改善に結び付けます。こうした小さな学びの積み重ねが、止まりにくく、支えやすいクラウド基盤を育てます。
まとめ ― “あと付け”ではなく“最初から”埋め込む
信頼性、コスト、セキュリティ、観測、そして自動化。これらを最初から設計に埋め込むことが、シンプルで強いクラウド基盤をつくる近道です。最小構成で始め、数値で見て、痛みが出たところから賢く伸ばす。この地味な反復こそが、実践的なインフラ設計の肝です。