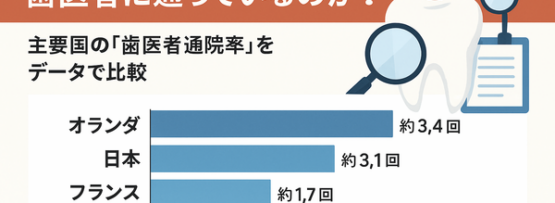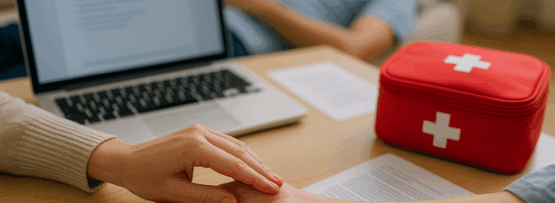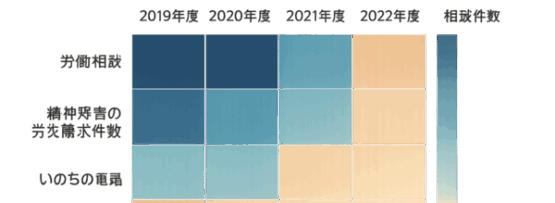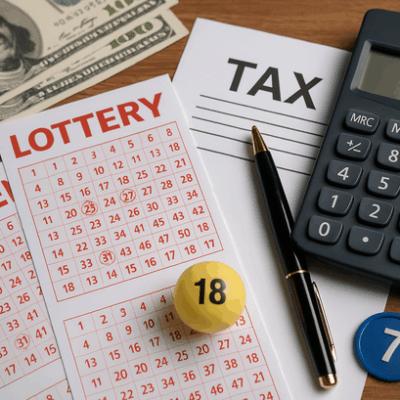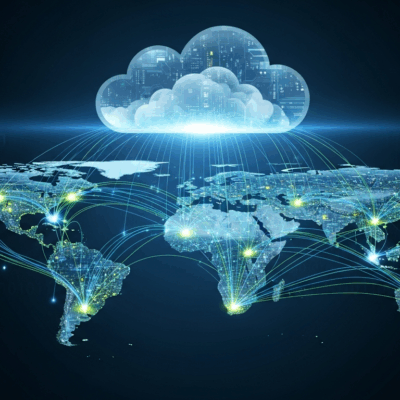病院で突然「コードブルー」「コードレッド」という館内放送が流れると、何が起きているのか不安になります。ドラマで耳にした言葉でも、実際の現場では病院ごとのルールや運用が異なることも少なくありません。本稿では、一般の来院者や患者さんの目線で、この2つのコードの大まかな意味と、落ち着いて行動するためのヒントをわかりやすく整理します。過度に専門的にならず、誤解を防ぐことを目的とした内容です。
なぜ病院は色の「コード」を使うのか
病院では、状況を手短に正確に伝えるために「色+コード」を使うことがあります。これは、詳細を言い換えるよりも素早く共有でき、かつ院内で不必要な混乱や不安を広げないための工夫です。スタッフ同士が共通認識で動けるようにする、いわば合図のような役割を果たしています。
コードブルーとは?
一般的に「コードブルー」は、患者さんの容体が急激に悪化し、至急の医療チーム招集が必要な状況を指すことが多い用語です。テレビドラマの影響で救急ヘリや高度救命のイメージが先行しますが、実際には院内での緊急対応を迅速に開始するための合図という位置づけが中心です。来院者や患者さんに求められるのは、慌てず職員の指示に従い、通路をふさがないなど場を整える協力です。専門的な判断や処置は、すべて医療スタッフが担います。
コードレッドとは?
「コードレッド」は、多くの施設で火災や煙の発生など、施設の安全に関わる事象を示す合図として使われます。施設によっては、防火シャッターの作動やエレベーターの制限、避難経路の確保などが同時に進みます。来院者は、職員や案内表示の指示に従い、落ち着いて行動することが最も大切です。状況の撮影や通路の占有は、対応の妨げになるため避けましょう。
病院や地域で運用が違うことに注意
色コードの意味や使い方は、国・地域・病院ごとに異なる場合があります。近年は、一般の人にもわかりやすい「平易な言葉での館内放送」に切り替える施設も増えています。初めて訪れる病院では、案内板に掲載されている非常時のルールを確認するか、受付で質問しておくと安心です。
一般の人が知っておくと役立つポイント
- 放送が入ったら、まず立ち止まって内容を聞く。わからない時は近くの職員に尋ねる。
- 通路やエレベーターを塞がない。移動指示がなければその場で待機。
- 撮影や実況はしない。個人情報や安全確保の観点から控える。
- 家族・付き添いの方は、連絡が必要なら簡潔に。混線を避けるため電源や音量にも配慮を。
- 避難経路と非常口の位置を、来院時にざっくり把握しておく。
ドラマとの違いを知っておく
映像作品では、緊迫感を高めるために「コードブルー」「コードレッド」が象徴的に登場します。しかし現場では、落ち着いた連携と、病院ごとの手順に沿った動きが重視されます。ドラマのイメージで判断せず、実際の施設の案内・職員の指示に従うことが大切です。
まとめ:合図の意味を知り、落ち着いて協力する
「コードブルー」は医療チームの至急招集、「コードレッド」は施設の安全に関わる事態を告げる合図として使われることが多い——この大枠を知っておくと、不安が少し和らぎます。とはいえ詳細は病院によって異なるため、最優先は職員の指示に従い、通路確保や静粛など基本的な協力をすること。合図の意味を知ることは、慌てず行動するための小さな備えになります。