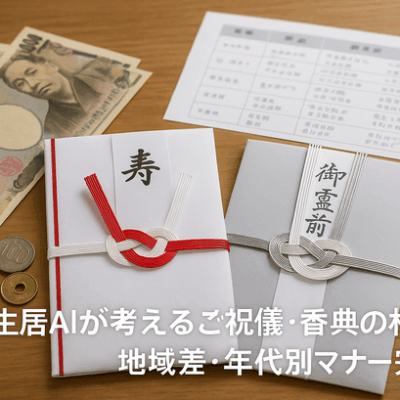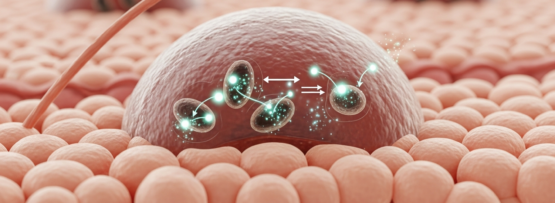空港の三文字コードは、旅の予約や荷物タグで毎回目にするのに、意味や由来は意外と知られていません。LAXは分かるけれど、なぜニューヨークではJFKとEWRが並ぶの?という素朴な疑問に答えつつ、例外だらけの背景を「読み解くコツ」と「実用的な活用法」に整理してみます。課題は三つです。1) ルールが分かりづらい、2) 例外が多い、3) 検索や乗継での思い違いが起きがち。この三点を、身近な例で解きほぐします。
三文字コードの正体と前提
一般に使う三文字はIATAコード(例:HND, NRT, LAX)。航空管制などで使う四文字はICAOコード(例:RJTT, RJAA, KLAX)で別物です。さらに都市圏をまとめる「都市コード」(例:東京=TYO、ロンドン=LON、ニューヨーク=NYC)もあり、予約検索では空港コードと都市コードが混在します。ここを押さえるだけで、検索ミスの多くが減ります。
例外だらけの由来を楽しむ
三文字は「都市名の略」だけではありません。歴史や地名、軍用飛行場の名残、言語の違いが入り混じります。
- Xが付いた都市:LAX(ロサンゼルス)は二文字時代のLAに、三文字化の際“X”を足した名残。
- 旧称の影:ORD(シカゴ・オヘア)は、かつてのオーチャード・フィールドが由来。MCO(オーランド)はマッコイ空軍基地の名から。
- EWRの謎:ニューアークがNEWにならないのは、NEWがニューオーリンズ・レイクフロント空港に割り当て済みだったため。そこでEWRが採用されました。
- カナダのY:YYZ(トロント)、YVR(バンクーバー)、YUL(モントリオール)の“Y”は、鉄道・無線局の識別や気象観測所の名残とされます。
- 言語差の反映:FCO(ローマ・フィウミチーノ=イタリア語名)、MUC(ミュンヘンの独語名München)、CPH(CopenHagen)、ZRH(Zürich)など。
- 旧地名の継承:PEK(北京=Peking)、CAN(広州=Canton)、BOM(ムンバイ=Bombay)、MAA(チェンナイ=Madras)、CCU(コルカタ=Calcutta)、SGN(ホーチミン=Saigon)、RGN(ヤンゴン=Rangoon)、CMB(コロンボ)。
- 日本の分担:HND(羽田)、NRT(成田)。大阪はKIX(関西)とITM(伊丹)。名古屋はNGOが小牧から中部国際空港へ引き継がれ、都市に紐づく面が強いことを物語ります。
- コードの“引っ越し”:イスタンブルのISTは、アタテュルク空港から新空港へ移管。閉鎖や用途変更でコードが再配置されることもあります。
由来を見抜く3ステップ
- 旧名を想像する:都市や空港が昔どう呼ばれていたか(例:Peking、Bombay、Madras)。
- 地元語を当てる:英語ではなく現地語の綴りを思い出す(例:München→MUC、Genève→GVA)。
- 国ごとの癖を知る:カナダは“Y+地名”、米国は軍・旧飛行場の名残が多め、イタリアは空港固有名(FiumicinoやMalpensa)が出る、など。
検索と乗継で迷わないコツ
- 都市コードと空港コードを使い分ける:目的が「都市全体」ならTYO/NYC/LONで検索、空港指定ならHNDやJFKなどを指名。
- 経由地の見落とし防止:同都市に複数空港がある場合、到着と出発のコードが揃っているか確認(例:LHR到着なのにLGW発は不便)。
- 荷物タグの確認:タグの三文字が目的地と一致しているかを見るだけで、ロストバゲージの初動リスクを下げられます。
“謎解き”としての楽しみ方
三文字は、地図帳には載らない都市の記憶装置です。LAXのX、ORDの果樹園、YYZの無線塔、PEKのPeking……。旅行前にコードの由来をひとつ調べるだけで、到着した街の見え方が変わります。もし不可解なコードに出会ったら、旧名・現地語・国の癖の三点から推理してみてください。きっと、その土地の歴史や交通の層が立ち上がってきます。
これからの三文字コード
空港の新設や改称に伴い、コードの移管や新規付与は今後も続きます。三文字は固定の答えではなく、都市の変化とともに更新される“短い物語”。旅の計画だけでなく、街の過去と現在をつなぐ読み札として、これからも付き合っていきたいものです。