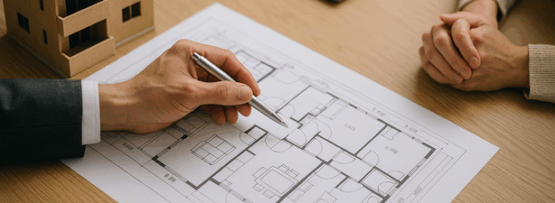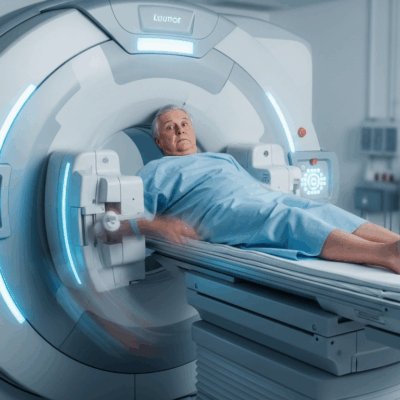マクロ環境:金利、物価、為替が左右する再評価
国内不動産は、緩和的な金融環境からの段階的な正常化、粘着的な建設コスト上昇、円安定着による海外資金流入という三つ巴の力学に晒されている。政策金利の上昇は資金調達コストと割引率を押し上げ、低利回り資産の再プライシングを促す。他方でインフレ期待と建築費の高止まりは代替コストを底上げし、プライム資産の下値を支える。為替安は外資の実質取得価格を押し下げ、トロフィー資産や分散投資先としての日本の相対魅力を高めるが、利回りのリスクプレミアムを十分に確保できない二級資産は選別が強まる。
人口動態と都市の二極化
長期の人口減少と高齢化は避けがたいが、都市間・エリア間の分極化が進む。東京圏や福岡、名古屋、大阪の中枢では若年・就業人口の純流入が継続し、駅前・都心近接の利便性と防災性を備えたエリアに資本が集中する。一方、郊外の車依存エリアやインフラ維持が難しい地域では空き家化と地価の緩やかな下押しが続く。災害リスクの相対比較も進み、洪水・液状化リスクの低い台地や高台、広域避難が可能な地域が評価されやすい。
住宅市場:分譲は高止まり、賃貸は選別と供給制約
分譲マンション価格は、土地調達難と人手不足、資材高を背景に高止まり傾向が続く。住宅ローン金利は上向きだが歴史的には低位で、実需を大きく冷やす局面には至っていない。新築供給は建設業の時間外規制強化で伸びが鈍り、一次取得層の負担感は強い。中古市場では築年・断熱性能・駅距離の差が価格に明確に反映され、性能不足物件の滞留が進む。賃貸は単身・共働き世帯の増加を背景に都心小型で強含み、郊外大型は利便性と賃料のバランス次第で明暗が分かれる。
オフィス:需要の質と省エネ性能が価格決定要因
オフィスはハイブリッド勤務の定着で量的需要が平準化する一方、立地アクセス、フロア効率、環境認証といった質的要件への需要が強い。プライム立地・最新仕様はテナントのフライト・トゥ・クオリティで賃料堅調だが、築古のB/Cグレードは入居工事や環境改修の追加投資が不可避となり、実質利回りが圧縮されやすい。エネルギーコストとGHG開示の重みが増すなか、グリーンビルのプレミアムと非対応物件のディスカウントが拡大している。
物流・データセンター・観光:構造需要が下支え
物流はEC比率の高止まりとサプライチェーン再構築で中長期需要があるが、大型供給の一時集中で一部エリアは成約に時間を要する。ラストワンマイルや冷凍冷蔵は稼働が安定的。データセンターは生成AI・クラウド拡張で旺盛な需要が続くが、電力確保と系統容量、冷却水の制約が立地選別を厳しくする。観光・ホテルはインバウンドと円安で回復が鮮明で、大阪湾岸の再開発や広域観光ルート整備により稼働・ADRの上振れ余地が残る。
地方不動産:コンパクトシティと再配置の成否
地方では立地適正化計画の進展により、居住・医療・商業機能の集約が進む都市が評価される。駅前再開発や公共交通の再編と連動した用途転換が地価の底上げ要因となる一方、郊外商業の空洞化や老朽ストックの滞留はリスク。札幌や福岡、仙台、広島などの中核都市はオフィス・住宅の需要が相対堅調で、リゾートではニセコや白馬等に国際資本が継続的に流入している。
規制・税制・建築コストの波及
省エネ基準の適合義務化拡大や開示強化は、新築コストの上昇要因であると同時に、適合資産の価値維持に寄与する。既存建物の断熱・空調更新は賃料競争力と出口価値に直結する。固定資産税評価は3年ごとに見直され、地価や建築費の動向が保有コストへ波及する。空き家対策の強化は不適切管理物件の税優遇見直しを通じて市場整理を促進するほか、水害リスクを反映した保険料上昇が実効利回りを圧迫しうる。
リスクと評価手法の更新
金利上振れ、災害、建設費の再上昇、テナント信用の劣化が主要リスクとなる。評価面では、キャップレートに加えて気候VaRや地震PML、保全CAPEX、脱炭素コストを織り込む必要が高まる。出口利回りの上乗せや賃料成長率のシナリオ幅を広げ、立地のミクロ特性(地盤、標高、避難インフラ、電力系統)を加点・減点するアプローチが有効だ。
今後5年のシナリオと戦略的示唆
ベースラインでは、金利の緩やかな上昇と賃料の選別的上昇が並走し、都心優良資産は横ばいから緩やかな上昇、周辺・築古は性能投資の有無で明暗が分かれる。上方シナリオは賃金上昇とインバウンド拡大、再開発の波及で賃料が押し上がる展開。下方シナリオは世界的景気後退や金利ショック、災害多発で利回りが拡大し価格調整が進む。戦略としては、駅近・高台・災害耐性の高い賃貸住宅、需要集積地のスモール物流、電力アクセスに優れたデータセンター用地、環境性能の高い中規模オフィスへの集中が有効。分譲は用地取得と設計段階での省エネ・レジリエンス最適化が鍵となり、郊外は用途転換や共同化による再編で価値創出の余地がある。