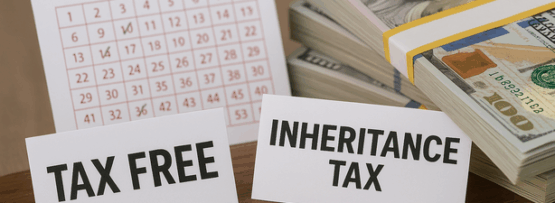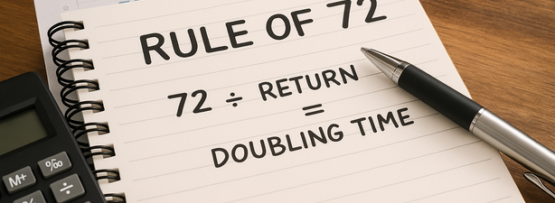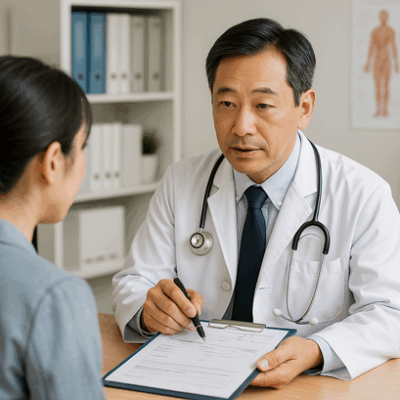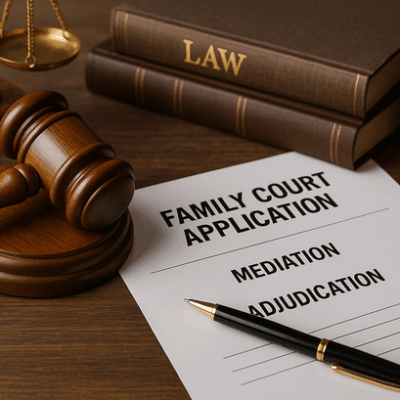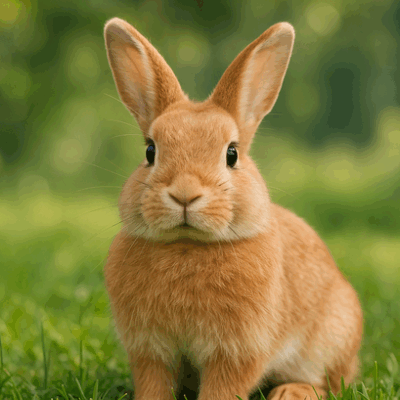「預金は1,000万円まで守られる」とよく聞きますが、実は“いつでも誰でも”という万能の盾ではありません。口座の種類や名義の持ち方、金融機関の区分や商品によって、保護の枠や扱いが変わります。本稿では、基本の仕組みと見落としがちな落とし穴、知っておくべき例外、そして今日からできる実践策を整理します。
1,000万円保護の基本をざっくり把握
預金保険の基本は「同一人・同一金融機関ごとに、円建ての預金(普通や定期など)の元本と破綻時点までの利息を合算し、1,000万円まで保護」という考え方です。複数の支店に分けても、同じ銀行であれば合算されます。
一方、「決済用預金(当座預金など、無利息・要求払いで決済機能があるもの)」は全額保護の対象です。大きな振込や引落しに使う資金を一時的に置く場所としては有力です。
よくある勘違い・落とし穴
- 支店やインターネット支店を分けても同じ銀行なら合算。支店数で保護枠は増えません。
- 同じブランドでも法的に別会社なら別枠、逆に別サービス名でも同じ銀行なら同枠。公式の「対象金融機関名」で確認を。
- 外貨預金、投資信託、保険、株式、暗号資産、電子マネー残高などは預金保険の対象外。別の保護スキームやリスクになります。
- 証券会社の預り金やスイープは、提携先銀行の預金になる場合と別の保護制度になる場合があり、確認が必須。
- 屋号付き個人口座(個人事業主)は本人と同一の扱いで合算。法人名義は別人格として別枠。
- 共同名義(連名)口座は、持分に応じて各名義人へ按分され、それぞれの1,000万円枠に組み込まれます。
- 高金利の「決済用預金」は存在しません。利息が付くと“決済用”の全額保護から外れる点に注意。
知っておきたい例外・特例
- 決済用預金は全額保護。ただし「無利息」「要求払い」「決済サービスに使える」という要件を満たす必要があります。
- 合併・破綻の局面では、経過措置により一時的に取扱いが変わることがあります。金融機関や預金保険機構からの案内を必ず確認しましょう。
- 旧姓や通称など名寄せの結果、同一人物と判断されれば合算。名義の付け方で枠が増えるわけではありません。
守りを固める実践チェックリスト
- 1,000万円を超える見込みの資金は、法的に別会社の複数銀行へ分散する。
- 大口の決済予定資金は「決済用預金」を活用する(要件を満たす商品かを確認)。
- 家計簿の棚卸しを年1回:各口座について「金融機関名」「商品種別(普通・定期・決済用など)」「残高」を一覧化。
- 証券会社のスイープ口座や“◯◯ウォレット”の行き先(どの銀行に預けられるか/預金保険の対象か)を仕様書で確認。
- 個人と法人、家族の名義は区別して管理。連名口座は按分ルールを理解して運用。
- 外貨や投資商品は、預金保険とは別のリスクとして位置づけ、分散全体でコントロール。
もし金融機関が破綻したら
破綻が発表されると、預金保険機構や受皿金融機関から手続きの案内が出ます。一般預金は合算のうえ1,000万円までとその利息が払い戻し対象に。超過分は破綻金融機関の整理手続きの中で配当される可能性があります。決済用預金は全額が保護対象です。急いで引き出すより、正式な案内に沿って行動するのが基本です。
まとめ:ルールを知れば怖くない
1,000万円保護は強力ですが、対象資産・名義・金融機関の区分で結果が変わります。守りのコツは「複数銀行への分散」「決済用預金の使い分け」「対象外資産の把握」というシンプルな三点。年に一度、口座リストを更新し、疑問点は各金融機関の「預金保険の対象・範囲」ページで確認する。これだけで、いざというときの安心感はぐっと高まります。