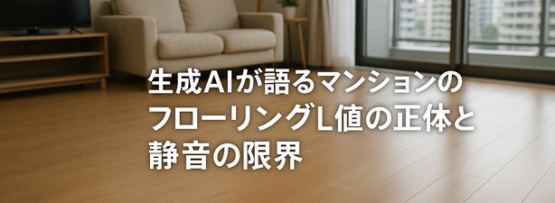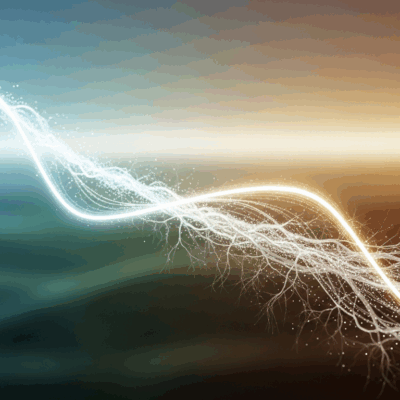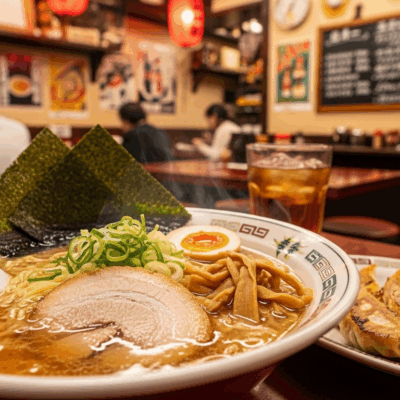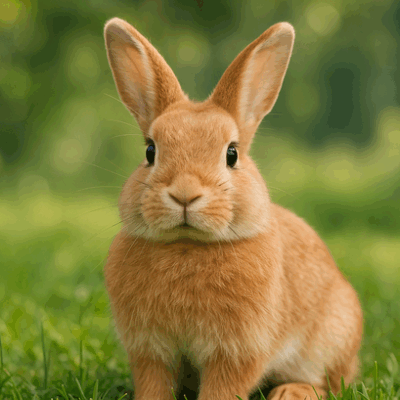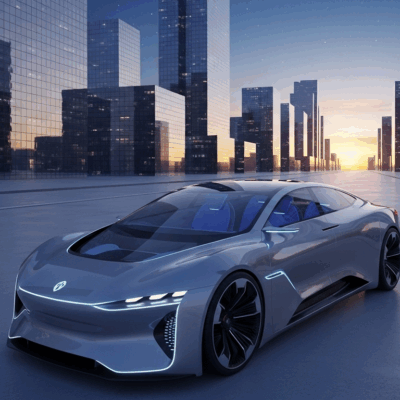同じ「6帖」でも実は広さが違う──賃貸探しでこんな経験はありませんか。畳の大きさは地域で差があり、「帖」や「m²」の表記方法にもルールや慣習が混在します。結果、「思ったより狭い」「家具が入らない」といったミスマッチが起こりがちです。本稿では、畳サイズの地域差と広さ表示の落とし穴をやさしく整理し、内見や問い合わせで使える具体的な見抜き方を提案します。
畳のサイズは全国共通ではない
畳1枚の大きさは地域や建物のタイプで異なります。代表的な目安は次のとおりです(おおよその寸法)。
- 京間(関西間・本間):約191×95.5cm(約1.82㎡)
- 中京間:約182×91cm(約1.66㎡)
- 江戸間(関東間・五八間):約176×88cm(約1.55㎡)
- 団地間:約170×85cm(約1.45㎡)
同じ「6帖」でも、京間なら約10.9㎡、江戸間なら約9.3㎡で、差は1.6㎡前後。ベッド1台分に相当する違いです。間取り図の帖数だけで広さを判断すると、地域差ゆえに体感がズレやすくなります。
「帖」表示の落とし穴
和室だけでなくフローリングでも「洋室6帖」などと表記されますが、これは畳を敷いたら何枚分か、という目安に過ぎません。さらに注意したいポイントは以下です。
- 換算基準の揺れ:広告では目安として「1帖=約1.62㎡」で換算される場合がありますが、実際の畳寸法や測り方と一致しないことがあります。
- どこまで含むか:帖数は柱の出っ張り、収納、梁下の凹みなどの扱いが不統一。表示者の基準で数値が前後することがあります。
- 小数切り上げ・切り捨て:5.9帖を6.0帖と丸めるなど、体感より広く(狭く)感じる場合があります。
帖は「体感の目安」、実際の家具配置は「内寸」で判断するのが安全です。
m²表記でも生じるズレ:「壁芯」と「内法」
面積の基準には主に2種類あります。
- 壁芯(かべしん):壁の中心線までを面積に含める方法。数値は大きめに出やすい(実際に使える面積より+数%~1割程度になることも)。
- 内法(うちのり):内側の仕上げ面で測る方法。実際に使える面積に近い。
分譲の広告は壁芯が多く、登記や契約書では内法が用いられるのが一般的です。賃貸広告は混在しやすいので、「これは壁芯ですか、内法ですか?」と確認するだけで、体感とのギャップをかなり減らせます。
内見での「見抜き方」チェックリスト
- 帖とm²の両方を確認:帖は目安、m²は測定基準を質問(壁芯 or 内法)。
- 実寸を測る:メジャーやスマホ計測アプリで「有効幅×奥行」を採寸。ベッド・ソファの寸法と照合。
- 凹凸の把握:柱の出、梁下、出窓、クローゼットの開閉範囲を図形としてメモ。
- 家具導線:玄関~居室、居室~ベランダの最狭通路幅を測る(60cm、70cmの家具が通るか)。
- バルコニーや専用庭:専有面積に含まないのが基本。広告のm²に入っていないか確認。
- 図面の注記:図面と現況が異なる場合は現況優先、という注記の有無と差分の説明を求める。
よくある誤解を減らす小ワザ
- 「6帖=約9.7㎡」と思い込まない:地域や換算で1㎡以上ブレる可能性あり。
- LDK表記は「最低面積基準」がある:地域団体の広告規約で定義が異なるため、数字の根拠を確認。
- 収納を含めない帖表示も:洋室の帖数にクローゼットが入っていないことがある。内寸で確認。
- 床暖や設備の占有:床下機器や段差が実効面積を減らすことも。境界部分を確認。
まとめ:数字より「測り方」を問う
畳の地域差と測定基準の違いは、同じ「6帖」や同じ「25㎡」でも体感が変わる主因です。物件比較では、数字そのものより「その数字は何をどう測ったものか」を必ず確認しましょう。内見での実測、壁芯か内法かの質問、凹凸の把握。この3点を押さえるだけで、家具が入らない・思ったより狭いといった後悔をぐっと減らせます。最後は、暮らし方に合う「使える面積」で判断することが、満足度の高い住まい選びの近道です。