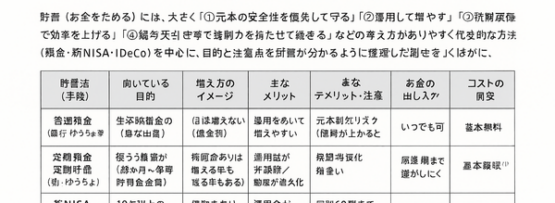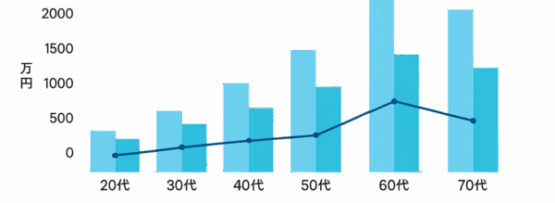「1円玉を作るコストが1円を超える」──そんな原価逆転の話題を耳にしたことはないでしょうか。エネルギーや素材の価格変動、現金需要の変化が重なり、年によっては実際に起きます。一方で、小売の値付けやつり銭の都合、会計単位としての「1円」はまだ生活に根づいています。本稿では、原価逆転の仕組みと影響をやさしく整理し、現実的な対策や今後の選択肢を提案します。
1円玉の「原価逆転」とは何か
原価逆転は、硬貨1枚をつくる総コストが額面(1円)を上回る状態を指します。コストには、アルミ地金の価格、電力・燃料などのエネルギー、製造や検査の人件費、輸送や保管、梱包などが含まれます。市況や為替の影響を受けやすく、原材料やエネルギーが高騰すると発生しがちです。
通常、硬貨には「発行益(シニョリッジ)」と呼ばれる収益が生まれます。額面から製造コストを引いた差額が国の収入になる仕組みです。しかし原価逆転が起こると、この差額がマイナスになり、財政的な負担が生じることになります。
発行益の仕組みと誰の収入?
日本では硬貨は政府が発行し、発行益は国の収入(非税収)になります。一方、紙幣は日本銀行が発行し、紙幣の発行益は主に日銀が保有する資産の運用益として帰属します。つまり、1円玉の原価逆転は政府側の収支に直接影響します。
なぜ今、原価が上がるのか
- 素材価格の変動:アルミ相場や為替がコストに直結。
- エネルギー高:溶解・圧延などエネルギー多消費工程の負担増。
- 固定費の割高化:キャッシュレス普及で発注量が減ると、1枚あたり固定費が重くなる。
- 物流・人件費:輸送や検査、セキュリティまで含めると地味に効く。
それでも1円が必要とされる理由
消費税を含む総額表示で1円単位の価格が一般的になり、現金決済ではつり銭に1円が欠かせません。会計単位としての「1円」は電子決済でも残ります。また、貨幣には法的な位置づけがあり、急にやめるには制度や実務の広範な見直しが伴います。
現実的な対策:コストを抑え、使い勝手を保つ
- 回収と再流通の強化:余剰硬貨を滞留させず、店舗・銀行・当局の間で循環を高め新規鋳造を抑制。
- 再生材と省エネ:再生アルミの活用比率を高め、製造工程の省エネ・自動化で1枚あたりコストを圧縮。
- 発注の平準化:需要の季節変動をならし、ロット最適化で固定費を薄める。
- 価格設定の工夫:税込価格の端数を抑える値付け(例:◯◯8円→◯◯0円/◯◯5円)で現金つり銭需要を軽くする。
- キャッシュレス活用:少額でも手数料と体験のバランスを見直し、小銭需要のピークを和らげる。
- 丸めルールの検討:海外のように「現金支払いに限り5円単位で丸める」仕組みは、制度設計次第でコストを大きく下げうる(実施には法制度や周知が必要)。
海外事例に学ぶポイント
カナダなどでは1セント硬貨を廃止し、現金支払いに限って合計額を5セント単位に丸める方式を採用しました。電子決済は1セント単位のままなので、会計の正確性を保ちつつ現金の取り扱いコストを削減しています。日本でも、現金とデジタルのルールを分ける設計は選択肢になりえます。
今後の見通し:二兎を追う設計へ
当面、1円玉は急になくならないでしょう。だからこそ、回収・再流通の徹底、再生材や省エネの導入、需要に見合った発注などの足元対策が重要です。一方で、価格設定の工夫やキャッシュレスの活用、必要なら丸めルールの段階的導入といった「使い勝手を損なわない制度設計」を並行して進めるのが現実的です。
原価逆転は単なるコスト問題ではなく、「支払いのわかりやすさ」「事業者の負担」「公共コスト」のバランス調整の課題です。生活者にとっての納得感を軸に、小さな見直しを積み重ねることが、結果的に大きなコスト削減につながります。