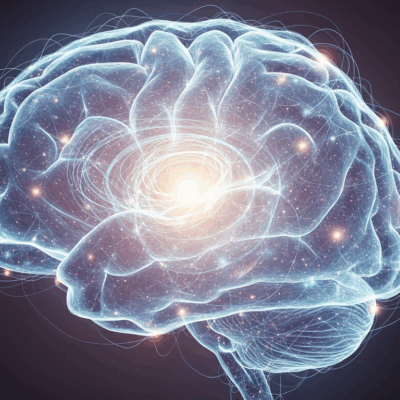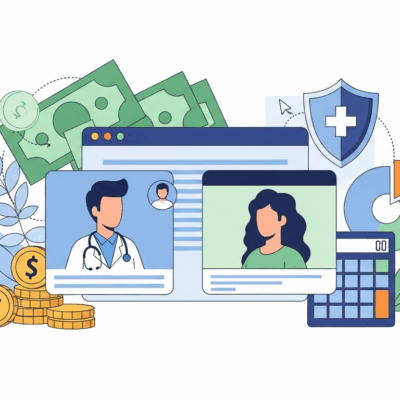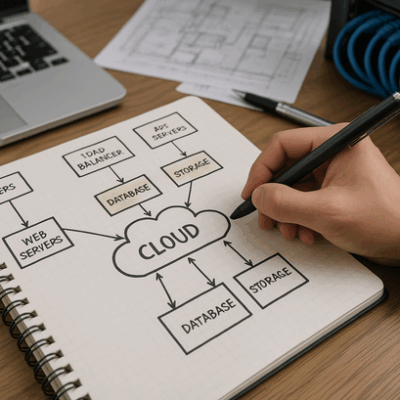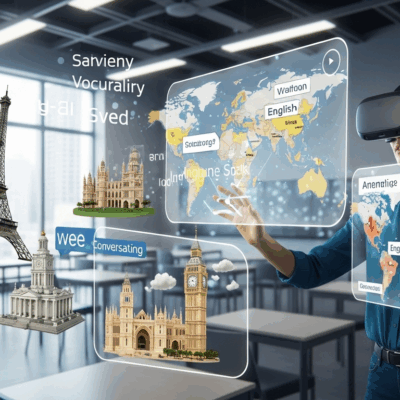住宅ローンを選ぶとき、つい「最安金利」だけに目が向きがちです。しかし実は、団体信用生命保険(団信)の健康告知や金利上乗せの条件こそ、家計に効く“落とし穴”。告知でつまずいて借入条件が変わったり、思ったより高い特約を付けて総支払額が膨らむケースもあります。本稿では、よくあるつまずきと回避のコツを、専門用語をなるべく避けて整理します。
団信の基本と「金利上乗せ」の正体
多くの銀行ローンは、基本的な死亡・高度障害の団信保険料が金利に含まれています。一方、がん・三大疾病・就業不能などの“手厚い特約”は、金利に0.1〜0.3%(商品によっては0.5%前後)を上乗せするのが一般的です。フラット35は団信が任意で、別建ての保険料(特約料)を払う仕組みです。つまり、同じ金利表示でも、どの保障が含まれているかで実質コストは変わります。
健康告知でつまずくポイント
団信は「健康状態の自己申告」が前提です。次のような点で、意外にひっかかることがあります。
- 過去の病歴・投薬歴:完治済みでも、一定期間内(例:過去5年)の通院・服薬は告知が必要。
- 健康診断の指摘:要再検査・要精密検査の放置は、未告知とみなされやすい。
- メンタルヘルス:うつ・適応障害などは審査が厳格。就業不能特約の対象外になる場合も。
- 基準の違い:銀行や保険引受会社で告知項目・判定が微妙に異なる。
「大したことない」と自己判断して未告知にすると、万一のときに契約解除や保険金不払いのリスクがあります。迷ったら、事前に金融機関へ確認しましょう。
審査に落ちたら?取れる選択肢
- ワイド団信(引受緩和型):健康条件がゆるい代わりに、金利上乗せが0.3〜0.5%程度になるのが一般的。
- フラット35+任意団信:団信を別建てにして組み立てる。体況に合わせた商品を選びやすい。
- 団信なし×別の保険でカバー:銀行が団信を必須としない場合に限り、定期保険などで残債相当を準備する方法。
- 借入計画の見直し:返済負担率を下げる、連帯債務で分散するなど、審査通過の余地を作る。
どの道を選ぶにせよ、「金利×借入期間」で総コストがどう変わるかを必ず試算しましょう。
特約の“効く範囲”を必ず確認
三大疾病・就業不能などの特約は心強い反面、適用条件に注意が必要です。
- 所定の状態の定義:一定期間の入院・働けない状態が連続して必要、など条件が細かい。
- 免責・待機期間:契約直後の一定期間は保障対象外となることがある。
- 対象外の傷病:精神疾患・持病の悪化が対象外のことも。
- 保障の範囲:返済期間中のみ有効。完済後は保障も終了。
“万一なら必ず支払われる”とは限りません。パンフレットの見出しだけでなく、約款の該当箇所を確認しましょう。
いくら高くなる?金利上乗せのざっくり感覚
例えば3,500万円を35年返済、特約で金利を0.3%上乗せした場合、総支払額は数十万円〜100万円超ほど増えることが多いです(元利均等・金利水準や繰上返済の有無で差が出ます)。「安心の上乗せ」が家計に見合うか、同額の保険料で代替できないか、比較して決めるのがコツです。
申し込み前のチェックリスト
- 告知書のサンプルを取り寄せ、該当しそうな項目を洗い出す。
- 最新の健診結果・通院記録・服薬状況を整理。再検査は済ませておく。
- 標準団信で難しければ、ワイド団信やフラット35の選択肢を同時に検討。
- 特約は“必要最小限”。就業不能と三大疾病など、重複保障に注意。
- 夫婦で借りるなら、どちらにどの保障を付けるか(収入・家事育児の役割も含め)配分を考える。
- 総支払額を比較試算し、将来の繰上返済や金利上昇の影響も想定。
まとめ:金利だけでなく、団信条件を“同じ土俵”で比べる
団信は住宅ローンの実質コストと安心度を大きく左右します。健康告知のつまずきや金利上乗せの仕組みを理解し、早めに情報をそろえて比較することが、ムダのない借り方につながります。見出しの良さだけで決めず、約款・告知・総支払額という“同じ土俵”で、あなたの家計に合う設計を選びましょう。