「壁芯」と「内法」って、どっちが本当の広さ?
マンションの専有面積には「壁芯(へきしん)」と「内法(うちのり)」という2つの表記方法があります。物件サイトやパンフレットを見比べると数字が微妙に違い、「あれ、どっちが正しいの?」と迷う方も多いはず。結論から言えば、どちらも“正しい”のですが、数え方が違うため面積が変わって見えるのが落とし穴。この記事では、違いをやさしく整理し、比較や内見のときに役立つチェックポイントを紹介します。
まずは定義をシンプルに
- 壁芯表示:住戸を囲む壁の中心線までを含めて測る方法。壁の厚みの半分が面積に入るため、数字は大きくなりがち。
- 内法表示:壁の内側の実際に使える床面だけを測る方法。実感に近いが、数字は小さめになる。
一般に、広告やパンフレットは壁芯で、登記簿の専有面積は内法で記載されることが多いです(広告ではどちらの方式かの表示が求められます)。
数字が違うと何が起こる?
壁芯のほうが広く見える分、価格や資金計画の印象にも影響します。例えば「70㎡(壁芯)」と書かれていても、内法では約2〜4%小さく、物件や壁厚によっては5%以上差が出ることも。ざっくり例を挙げると、
- 壁芯70.0㎡ → 内法約67.5〜68.5㎡(目安)
同じ「70㎡」表記でも、内見時に「思ったより狭い?」と感じるのはこの差によるものです。
広く見える広告のカラクリ
- 壁厚・柱型:角部屋や耐震壁が多い住戸は壁厚がしっかりしており、壁芯との差が広がりやすい。
- 共用部分との境界:玄関やパイプスペース周りは壁が厚く、面積の見え方に影響。
- バルコニー:専有面積には含まれません(共用部分の「専用使用」)。広告で“バルコニー面積○㎡”と別記されるのはそのため。
「数字が大きい=広い」ではなく、「どの方式で、どこまで含んでいるか」を確認するのがコツです。
比較のコツ:カタログと登記を“そろえて”見る
- 表示方式を確認:図面やサイトに「壁芯」「内法」の記載があるかチェック。なければ仲介担当に質問を。
- 坪単価の落とし穴:価格÷面積を計算するときは、同じ方式同士で比較。壁芯と内法を混ぜると割高・割安の判断を誤ります。
- 登記簿の専有面積:最終的な契約・登記では内法が基準になるため、ローン審査や保険などの数字とも整合を取っておくと安心。
- 実寸の確認:家具配置や通路幅は図面寸法(有効寸法)で判断。特に冷蔵庫やベッドの搬入・設置はミリ単位の差が効きます。
「体感の広さ」は数値以上にレイアウトで決まる
同じ内法面積でも、廊下が長い、柱の出っ張りが多い、扉の開き勝手が悪い、というだけで体感は大きく変わります。逆に、動線が素直で収納が壁面にきれいに収まっている間取りは、数字以上に使いやすく感じます。内見時は以下をチェック。
- 柱や梁の出っ張りが家具配置に干渉しないか
- 廊下と居室のバランス(居室率)が高いか
- 洗濯・料理・掃除の動線が短いか
- クローゼットの奥行・有効幅が実用的か
中古マンションで差が出やすいポイント
- リフォーム履歴:間仕切り移設で有効面積の使い勝手が改善・悪化している場合あり。
- 配管スペース:古い物件はPS(パイプスペース)が大きめで、壁芯との差が広がることも。
- 角部屋:人気ですが、壁厚由来で壁芯表示が“見かけ上”大きくなりやすい点に注意。
まとめ:自分基準の「広さ」を手に入れる
マンションの専有面積は、「壁芯は大きく見えやすい」「内法は実用に近い」という前提を知っておくと、広告の数字に振り回されにくくなります。表示方式をそろえて比較し、最終判断は実寸と動線で。面積の“差”に気づければ、価格・住み心地・将来の売却時の見え方まで、より納得のいく選択ができるはずです。





















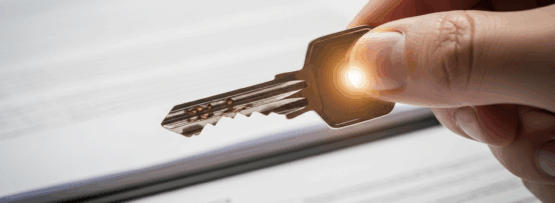










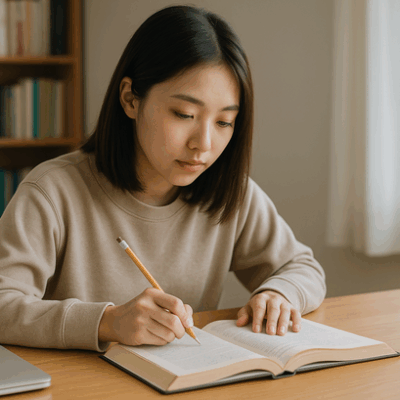





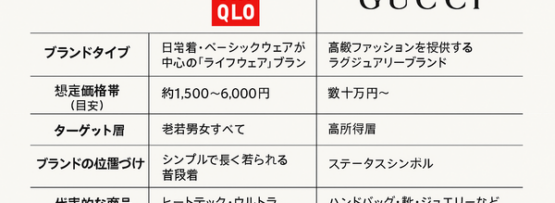

この記事へのコメントはありません。