お葬式や法要で「焼香は何回?」と迷う声は多く、宗派や地域で微妙に作法が違うため、正解がひとつではありません。本稿では、よく用いられる回数の目安と、その背景にある考え方、そして迷ったときの実践的な対処法をわかりやすく整理します。結論から言えば、基本は故人(喪家)の宗派に合わせ、会場の案内に従うのが最優先。わからない場合は「一回」を静かに丁寧に行えば無難です。
焼香の基本の流れ
会場や形式によって細かな違いはありますが、一般的な流れは次の通りです。
- 焼香台の手前で遺族・祭壇に一礼。
- 抹香を親指・人差し指・中指で少量つまむ。
- 宗派により「額にいただく」かは判断(後述)。
- 香炉に静かに落とす(これを宗派の回数で行う)。
- 合掌・黙礼(短い祈りの時間をとる)。
- 一礼して席に戻る。
動作はゆっくりと静かに。音を立てず、手元を大きく動かしすぎないのがコツです。
宗派別の回数と特徴(目安)
- 天台宗:1回または3回。いただくのが一般的。
- 真言宗:3回が多い。しっかりいただく。
- 浄土宗:1回が基本(地域で3回も)。いただく。
- 浄土真宗 本願寺派(お西):1回。いただかない。
- 浄土真宗 大谷派(お東):2回。いただかない。
- 曹洞宗:2回が多い。いただく。
- 臨済宗:1回が多い。いただく。
- 日蓮宗:1回が基本(地域差で3回も)。いただく。
同じ宗派でも寺院や地域で運用が異なることがあります。会場の掲示や司会・僧侶の案内があれば、それに従うのが最優先です。
回数の由来と意味
焼香は、香りで場と心を清め、故人と向き合う時間を作る所作です。回数には象徴的な意味づけがあり、例えば3回は「仏・法・僧(三宝)」や「身・口・意の三業」を整えることに由来するといわれます。1回は「一心に念ずる」ことを表し、2回は「仏・法への供養」など宗派内の伝承が背景にあります。いずれにせよ、数そのものよりも、静かな所作と真心が大切です。
迷ったときの判断基準とマナーのコツ
- 最優先は「喪家の宗派に合わせる」:案内表示・式次第・司会の説明を確認。
- 不明なときは「一回で静かに」:もっとも無難で失礼が少ない選択。
- いただくかどうか:浄土真宗はいただかないのが基本、その他はいただくのが多い。
- 量は少なめに:つまみすぎず、香炉にそっと落とす。
- 所作は簡潔に:長く滞在せず、合掌は短く心を込めて。
- 身だしなみ:数珠を持ち、香りの強い香水は控える。
シーン別のポイント(立礼・座礼・回し焼香)
立礼焼香(立って行う)では、前後の人との間隔を保ち、一礼を忘れずに。座礼焼香(座ったまま行う)では、隣席の方に配慮して動作を小さく。回し焼香(香炉が回ってくる)では、受け渡しは両手で、香炉を傾けないように注意します。いずれも、先導役や前の方の所作に合わせると安心です。
地域差と家ごとのしきたり
焼香の作法は、宗派だけでなく地域・寺院・家のしきたりでも変わります。「うちではこうしている」と伝えられることも珍しくありません。故人や遺族の意向を尊重する姿勢が何より大切です。迷ったら、その場の案内に従う、あるいは係の方に小声で確認しましょう。
まとめ:数よりも、心を整える時間に
焼香の回数は宗派で目安があるものの、現場の案内が最優先で、わからないときは「一回・静かに・丁寧に」が基本。所作を簡潔にし、心を込めることが何よりの供養です。数にとらわれすぎず、静かな呼吸で手を合わせるひとときを大切にしましょう。






















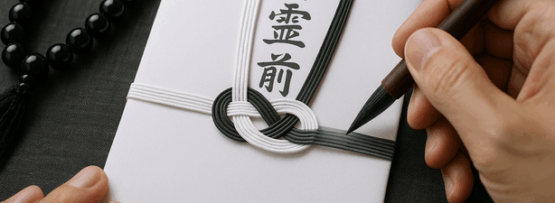
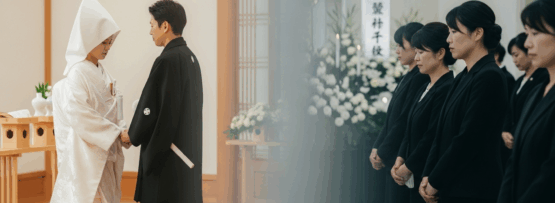










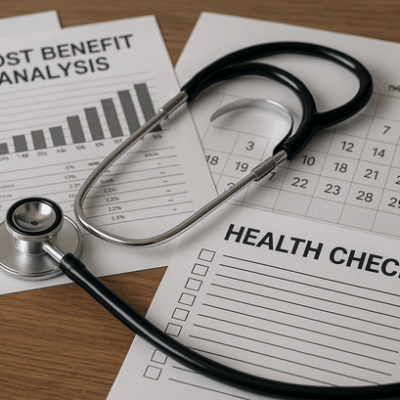

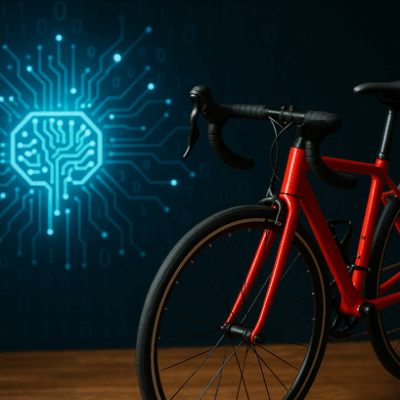




この記事へのコメントはありません。