病室のカーテンが床に届かず、少しだけ“すき間”が空いているのを不思議に思ったことはないでしょうか。プライバシーを考えると、床までしっかり隠したほうが良さそうに感じます。しかし、この小さなすき間には、衛生・防火・ケアのしやすさといった複数の配慮が重なっています。本稿では、その理由をわかりやすく整理し、私たちができる気づきや日常への応用のヒントも紹介します。
病室のカーテンが床に届かない、いちばんの理由
もっとも基本的な理由は「汚れや水分を拾わないため」と「病室の空気の流れを妨げないため」です。床はもっとも汚れやすい場所で、清掃や手指衛生が徹底されていても、靴底や機器の車輪、落ちた水分などが集まりやすいエリア。カーテンの裾が床に触れると、目に見えない汚れを拾い、上部へと広がるリスクが増えます。また、床から少し空間を開けることで、室内の換気やエアフローが安定し、においや湿気の滞留を防ぎやすくなります。
衛生面:床は「最も汚れる場所」
病院の清掃は細やかに行われていますが、床に触れやすいものほど汚れをもらいやすいのも事実。裾が長すぎるカーテンは、モップがけの邪魔になったり、拭き残しの原因にもなりえます。床から数センチ上げる設計は、清掃作業の効率と仕上がりを助け、カーテン自体の洗濯頻度や生地の持ちにも良い影響を与えます。さらに、医療機器の配線や点滴スタンド、ストレッチャーの車輪が多い環境では、裾が短いほど絡まりにくく、つまずきや引っ掛かりを減らす実用面の利点もあります。
防火・安全:燃え広がりと避難の配慮
医療用カーテンの多くは防炎加工が施されていますが、可燃物は少ないほど安心です。床まで届く長尺の布は、仮に火がつくと燃え広がる面積が増えます。裾に空間を設けることで、延焼のリスクを抑え、スプリンクラーや空調の気流が働きやすい環境を保ちやすくなります。また、足元がわずかに見えることで、スタッフが移動時の障害物や機器の位置、配線の這い回りを確認しやすく、動線の安全にも寄与します。
プライバシーとのバランスとスタッフの観察性
「裾が短いと中が見えそう」と感じるかもしれませんが、実際には視線が通るのは足元程度。座位やベッド上の様子は隠せる設計が一般的です。むしろ足元が少し開いていることで、スタッフは転倒の兆し、ベッドからの離床、機器のケーブルの状態などを素早く察知できます。プライバシーと観察性のバランスを保つ工夫、と考えると納得しやすいでしょう。
家庭や介護の場で生かせるヒント
家での介護や在宅ケアでも、カーテンは床からやや上げると、掃除がしやすくカビやほこりの付着を減らせます。浴室や洗面所など湿気がある場所では、特に裾を長くしすぎないことが快適さにつながります。プライバシーが必要な場所では厚手や二重にするなど、長さだけに頼らない工夫でカバーするのがおすすめです。
まとめ:小さな“すき間”に大きな工夫
病室のカーテンが床に届かないのは、見た目の問題ではなく、衛生・防火・安全・作業性を総合して最適化した結果です。足元のわずかなすき間が、清掃のしやすさ、空気の流れ、機器の取り回し、スタッフの観察性を支えています。次に病室でカーテンを目にしたときは、その小さな設計の背景にある多層的な配慮に、ほんの少し思いを巡らせてみてください。日常の暮らしにも応用できる発想が、きっと見つかるはずです。




















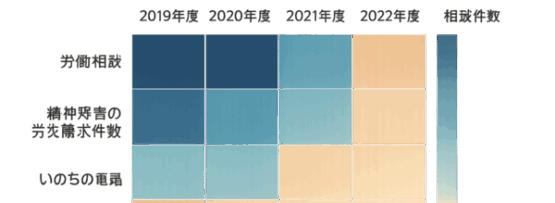













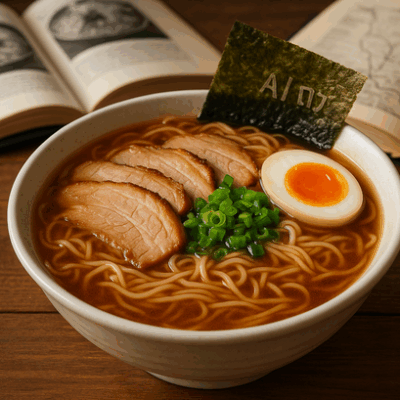





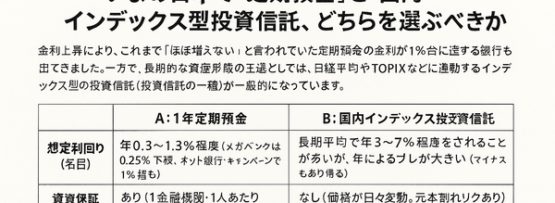
この記事へのコメントはありません。