病院エレベーター鏡の役割は「安全」と「安心」を同時に支えること
病院のエレベーターにある大きな鏡。「身だしなみを整えるため?」と思いがちですが、実は安全設計や心理的な安心のために重要な役割を担っています。本稿では、日常では気づきにくい鏡の意外な働きと、その活用のヒント、さらに今後の改善提案をわかりやすく整理します。
鏡の意外な主役機能:死角を減らし、動きやすくする
エレベーター内は狭く、ドアの開閉や人の出入りで死角が生まれがちです。鏡があることで、
- 背後や側面にいる人・物の位置を一目で確認できる
- 車いすやベビーカーがバックで出入りしやすくなる
- ストレッチャーや医療機器の搬送時に接触を避けやすくなる
といったメリットが生まれます。鏡は「見える情報」を増やし、動線の重なりをほどくための装置なのです。
安全設計への貢献:接触トラブルを未然に防ぐ
混雑時、降りる人と乗る人が同時に動くと小さな接触が起こりやすくなります。鏡があれば、互いの動きを早めに察知して「先にどうぞ」と譲り合いがしやすくなります。また、エレベータードアの近くに立つ人や点滴スタンドなど、低い位置の物体も映り込みで気づきやすくなり、つまずきや引っかかりの予防につながります。
心理効果:閉塞感をやわらげ、不安を軽くする
鏡は空間を広く見せる効果があり、閉所の圧迫感をやわらげます。ゆったり感が生まれると、待ち時間の体感も短くなることがあります。さらに、鏡越しに周囲の人の位置や表情が分かると、次にどう動けばよいか見通しが立ち、緊張が少し和らぎます。人によっては、鏡をじっと見続けると不安が強まることもあるため、過度に視線を固定せず、「周囲の確認に使う」程度がちょうどよい使い方です。
ユニバーサルデザインの視点:誰にとっても使いやすく
病院では、身長や姿勢、体調、利用補助具などが多様です。鏡の下端を低く、幅を十分に確保すると、車いすの方や子どもでも視認しやすくなります。少し柔らかい反射(強すぎない映り)にすると眩しさが抑えられ、低反射の表面処理は照明の映り込みを軽減します。照明は白すぎる光より、目に優しい色温度にすると視認性と安心感の両立が期待できます。
ちょっとしたマナーと活用のコツ
- ドアが開く前に鏡で人の位置を確認し、先に降りる人を優先
- 入口前のスペースは空け、車いす・ベビーカー・搬送を優先
- 鏡越しに軽く目線を合わせ、譲り合いの合図に使う
- 身だしなみチェックは短時間で。混雑時は周囲の安全確認を優先
小さな配慮が、全員の動きをスムーズにし、安心感を共有することにつながります。
これからの改善提案:見やすさと配慮のアップデート
- 位置とサイズの最適化:車いす使用時に後方が十分映る高さ・幅の検証
- 低反射・防汚コーティング:指紋や照明の映り込みを抑え、手入れも簡単に
- 案内との連携:鏡の近くに分かりやすいピクトグラムを配置し、動きのルールを視覚で共有
- 角度の微調整:ドア付近の死角を狙って減らすよう、フロアごとの混雑傾向に合わせて調整
- 使い心地の検証:患者さん・来院者・スタッフの声を定期的に反映し、継続的に改善
鏡は単なる装飾ではなく、安心・安全・快適を支える「情報の窓」です。病院という環境に合わせた工夫を重ねることで、誰にとってもやさしい移動空間が育っていきます。




















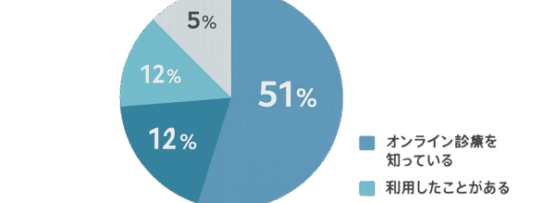







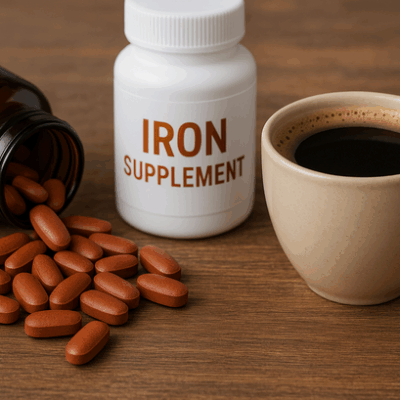




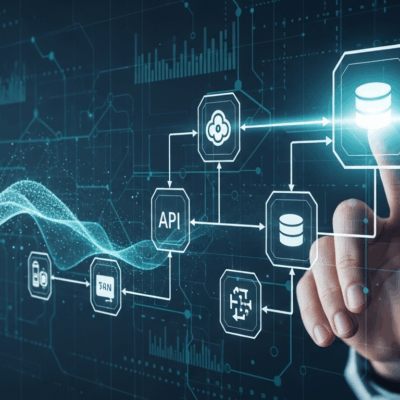






この記事へのコメントはありません。