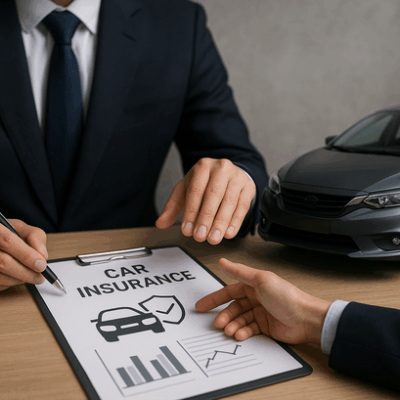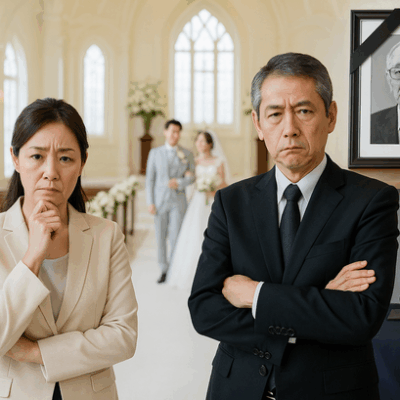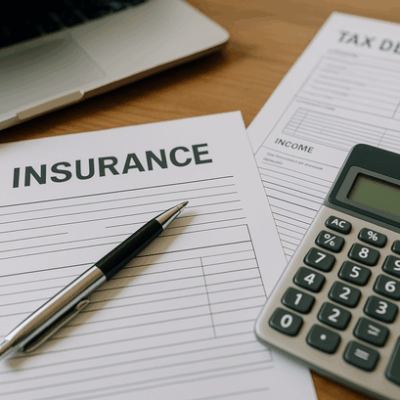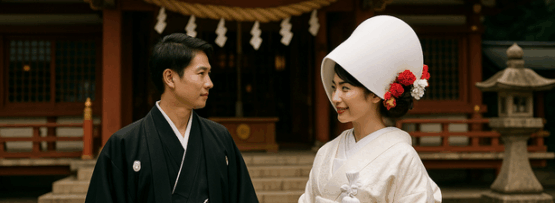在庫をデータ化する発想とスコアリング
冷蔵庫の在庫を「品目・量・状態・残存日数」として構造化し、調味料を含む全材料を同一テーブルで管理する。重量や個数だけでなく、切りかけ・下味の有無・開封後経過日数を属性に持たせ、劣化曲線をベイズ更新で推定する。アルゴリズムは各食材に「消費優先度スコア」を付与する。これは賞味期限までの残日数の逆数、開封後経過日数、におい・変色などのセンサー入力(簡易化すればユーザー入力)を特徴量にし、季節要因や家庭内消費頻度を重み付けして算出する。
味の評価は「嗜好モデル」と「普遍的調和モデル」を混在させる。前者は過去の実食ログから学習した個人化スコア、後者は素材と調味の化学的親和性(アミノ酸・糖・酸・脂の相互作用)と地域料理の共起統計に基づく。両者を0〜1で正規化し、在庫消費率と調理時間ペナルティを加えた合成目的関数を用意する。
最短でうまい一品を導く探索アルゴリズム
候補レシピは「味の接続グラフ」から生成する。ノードを食材、エッジを調理技法と味の接続強度とし、冷蔵庫在庫をシードに幅優先で展開、3〜7ノード程度の連結成分を候補とする。各候補に対し、整数線形計画で分量を最適化する。目的は味スコア最大化と在庫消費率最大化、制約は塩分・脂質の上限、火口数や器の制限、可処分時間の上限、そして「使い切り優先」の閾値。
調理時間は手順グラフのクリティカルパスで見積もる。刻む・下茹で・炒め・蒸すを並列化し、器具資源制約つきでスケジューリングする。A*探索のコスト関数は「段取り時間+加熱時間×エネルギー単価−同時進行ボーナス」。結果として、同等の味スコアなら行程が短い案が前に出る。
余りゼロに寄せる量調整と代替戦略
最小残量問題はナップサックに類似する。容量を「今夜の一品で使える総重量」、アイテムを各食材の分割可能量として、端数が出る場合は「サイド用途」を同時に立てて吸収する。例として卵1個分の端数はスープのとじ、キャベツ芯は千切りサラダのベースに回し、同じ味系統で統合する。代替はジャッカード類似度で評価し、長ねぎ⇔玉ねぎ、鶏もも⇔豚こま、みりん⇔砂糖+酒といったペアを確率的に置換。置換時は水分活性と油脂量の差を補正する係数を分量に掛ける。
安全性と品質を担保するガードレール
在庫優先でも衛生基準は上書きされる。加熱が必要な食材は中心温度基準(鶏肉75℃1分など)を満たす工程を必須制約に追加。再加熱回数は最大1回、冷蔵庫放置時間が閾値を超えた炊飯米や加熱済み惣菜は候補から除外。酸や塩を用いたマリネ・塩蔵は日持ち補正を与えるが、塩分過多を避けるため味の最適化における健康ペナルティを強化する。
ケーススタディ:平日の10分、火口ひとつ
在庫例:豚こま180g、キャベツ1/4、卵2、しめじ1/2株、味噌、マヨネーズ、酢、しょうゆ、ごま油。残存日数が短い順にキャベツ、しめじ、豚こま。火口1・10分の制約下で、候補は「味噌マヨ豚キャベツ炒め+卵とじ一体化」。
最適化での分量は、豚こま180g、キャベツ250g、しめじ80g、味噌小さじ2、マヨ大さじ1弱、酢小さじ1/2、しょうゆ小さじ1/2、卵2。マヨは油脂と乳化の役、味噌はうま味核、酢は後味のキレを付与。工程は、1) キャベツは繊維に直交で太め千切り、しめじはほぐす。2) 冷たいフライパンにマヨを入れ弱め中火で豚を広げて焼き色を付ける。3) しめじ→キャベツの順で投入し、しょうゆで軽く下味。4) 味噌を少量の湯で溶いて回しかけ、全体を強火で絡める。5) 溶き卵を周囲から回し、半熟で火を止め、ごま油数滴と酢を最後に。洗い物はフライパンひとつ、在庫はゼロ。
味のスコアは脂のコク×味噌のうま味×卵のまろみで高く、酢で後口を軽くすることで飽和を抑制。キャベツ芯も薄切りで投入し、食感差をアクセントにして廃棄を回避する。
評価指標とフィードバック学習
家庭内では「重量廃棄率=(廃棄重量/購入重量)×100」「即時消費率=購入から72時間以内の消費割合」「段取り効率=実測時間/見積時間」が機能する。食後に5段階評価と自由記述を記録し、分量誤差と味の乖離を回帰で学習、次回の塩分や油脂の推奨を微調整する。香味野菜の端材を翌朝のスープへ誘導するなど、時間軸を越えたメニュー連鎖も強化学習で最適化される。
家庭実装の現実的ワークフロー
入力はカメラと音声で簡略化し、スマートスケールがあれば重量を自動取得。定番調味料は残量を容器重量から推定し、閾値で自動補充リストへ送る。提案は3案までに絞り、所要時間・器具・塩分相当を併記。開始ボタンで手順が逐次配信され、同時進行の合図とタイマーが同期する。途中で食材が不足しても代替候補を即時提示し、最終味に影響する偏差も見える化する。
地域性と季節性の組み込み
地域の価格データと旬カレンダーを統合すると、在庫起点でも「次に買うべきもの」が味とコストの両面で最適化される。春は香りの強い山菜に脂を合わせ、夏は酸味と水分で軽く、秋は糖化の進む根菜でロースト、冬は発酵調味でコクを深める。味の接続グラフに季節パラメータを乗せることで、在庫を減らしつつ季節感のある献立が自動的に立ち上がる。
経済と環境へのインパクト
家庭の食品ロスは年間1人当たり約数十kgとされ、在庫駆動型レシピの最適化で重量廃棄率を10〜30%相対改善できる可能性がある。調理時間短縮はエネルギー消費の低減にも寄与し、同時進行最適化と短時間加熱の組み合わせでガス・電気使用量を5〜15%削減した事例が報告されている。味覚満足とサステナビリティを同一目的関数として扱う発想が、家ごはんの新しい標準になりつつある。