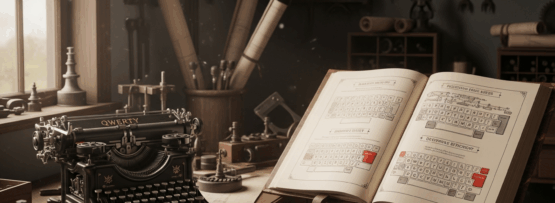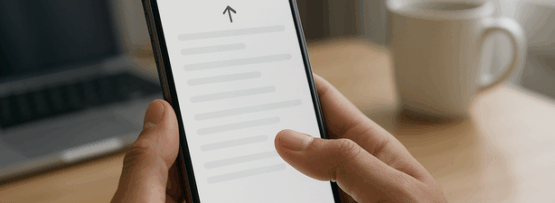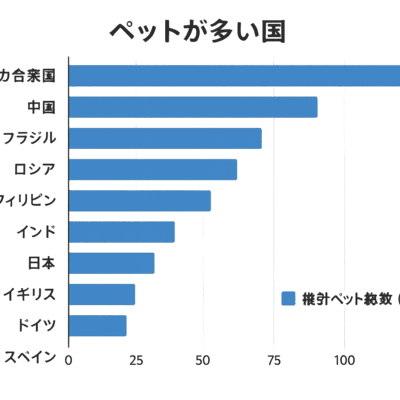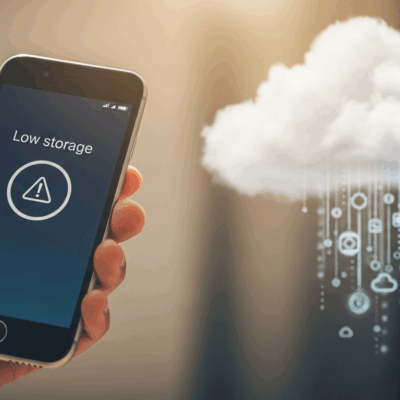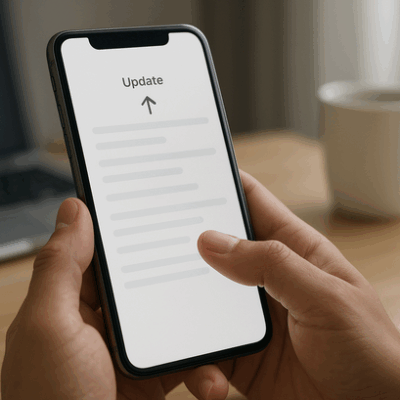アプリ内AIエージェントのアーキテクチャ最新潮流
生成AIを核に据えたアプリ内エージェントは、プランナーとエグゼキューターの二層構造が主流となりつつある。前者が目標分解とツール選択を担い、後者が関数呼び出しや外部APIを介して具体的な操作を実行する。構造化出力(JSON/スキーマ拘束)を前提とした関数呼び出し、RAGによる知識グラウンディング、短期メモリ(対話状態)と長期メモリ(ユーザープロファイル・履歴)の分離が標準設計だ。ワークフローは状態機械やオーケストレーターにより再現可能性を確保し、プロンプト・ツール・データのバージョン固定が運用の基本要件となる。
レイテンシ要件はP95での体感性能に集約され、オンデバイス小型モデルとクラウド推論のカスケード、ストリーミング応答と介入(中断・修正)の併用が普及する。観測性はトレース(モデル推論・ツール実行・I/O)単位で記録し、コスト・遅延・成功率を同一タイムラインで相関分析できる設計が求められる。
タスク自動化の実装パターン
単発回答型から多段推論・実行型へと進化し、計画→検証→実行→要約のループを持つ実装が増加している。実行前プレビュー(ドライラン)と差分提示、可逆操作の優先(撤回・リトライ)、不可逆操作は人的確認を必須とする二段承認がリスク低減に有効だ。ツールは最小権限のスコープ設計、期限付きトークン、機能単位のレート制限を組み合わせ、失敗時は冪等性キーと指数バックオフで再試行する。
決定性を高めるため、文法制約デコードやスキーマ検証、候補生成と合意形成(self-consistency)を取り入れる事例が目立つ。専門エージェントを用途別に用意し、ルーターがコンテキストに応じて委譲するマルチエージェント構成は、道具選択の誤りや幻覚実行を抑制する。個人化はローカルプロフィールと機密属性の分離保管、フェデレーテッドな重み更新や特徴量キャッシュでプライバシーと精度の両立を図る。
安全制御とリスク管理
脅威モデルは、プロンプトインジェクション、データ流出、過剰権限の濫用、幻覚による誤操作、バイアス拡大を含む。入力段階ではコンテンツ整形と機密検出・マスキング、出力段階ではポリシールールと安全モデルの二重フィルタを適用する。外部知識参照を必須とするグラウンディング検査、出典と根拠の提示、許可済みツールのホワイトリスト化が侵害面積を縮小する。
ツール実行はOAuth類似のスコープ宣言と時間制限、上位権限の昇格には明示 consent とジャストインタイム承認を要求する。監査は不可改ざん性を重視し、操作ログのハッシュ連鎖化、PIIの選択的保存、鍵の端末隔離を行う。安全評価は自動レッドチーム(攻撃プロンプトコーパス)による継続検証、シミュレーション環境での破壊的テスト、ポリシーカバレッジと偽陽性率のモニタリングを軸に据える。
評価指標とオブザーバビリティ
ビジネス成果と安全性を両立するため、複合指標の導入が不可欠だ。主要KPIは以下に集約される。
- タスク成功率(一次完了率、ステップ数、完了までの時間)
- ユーザー介入率・取り消し率・再実行率
- 安全関連:ブロック率、偽陽性/偽陰性、ヒヤリハット率
- グラウンディング率・出典被覆率・幻覚検出率
- レイテンシ(P50/P95)、コスト/解決、トークン効率
- ツール呼び出し失敗率、回復率、サーキットブレーカ発火回数
評価手法は、人手採点とモデル採点のハイブリッドが実務的で、明確なルーブリックを用いたペアワイズ比較、ゴールデンデータによる回帰試験、再生実験(リプレイ)とカナリア/段階的ロールアウトを組み合わせる。観測性はプロンプト・データ・モデル・ツールのバージョン固定、決定因子の記録(乱数種・温度・スキーマ)、データドリフト検知、機能フラグの切替履歴を一元管理する。
運用フェーズの継続改善とガバナンス
本番運用では、シャドーモードでの行動学習、評価ゲートを通過した変更のみを反映するリリース基準、異常時のキルスイッチが重要となる。プロンプトやポリシーをコードとして管理し、レビューとテストを経る変更管理を徹底する。法規制面ではデータ最小化、保持期間の明確化、データ主体の要求対応、トレーニング禁止領域の明示が求められる。コスト最適化は、キャッシュ、スペキュレーティブ/早期打切りデコード、モード切替(検索優先→生成)、蒸留・ルーティングによるモデル選択で達成する。
近未来の技術トピック
推論過程の検証可能性を高めるためのプログラム合成と形式的制約、計画器と検証器の二段構え、ツールコールの型安全性向上が注目される。小型オンデバイスモデルとクラウド高性能モデルのハイブリッド、マルチモーダル入力による状況理解、リアルタイム制御と対話の統合がユーザー体験を変える。ナレッジのプロヴェナンス管理、因果グラフやメモリグラフの導入により、説明可能性と再現性が強化される見通しだ。さらに、自己改善ループと自動評価パイプラインの常設により、品質・安全・コストの同時最適化が実装レベルで実現されつつある。