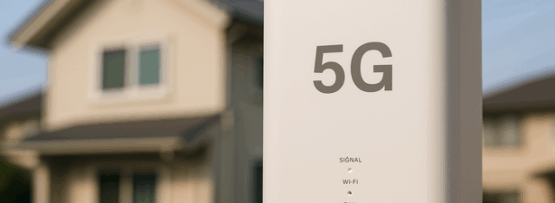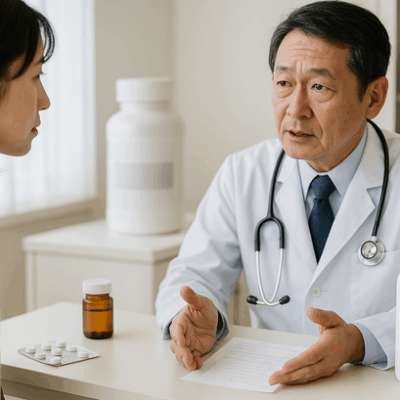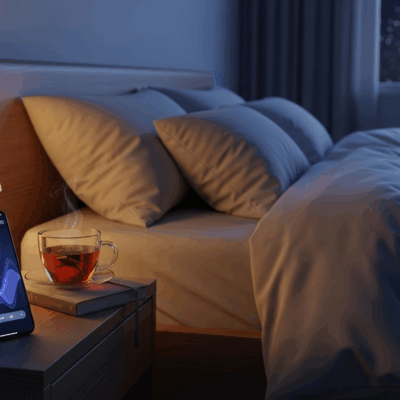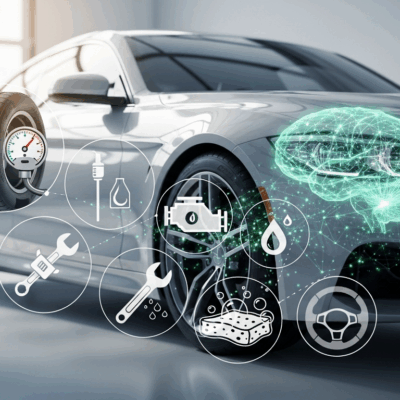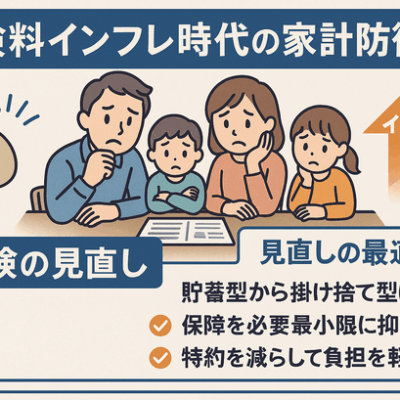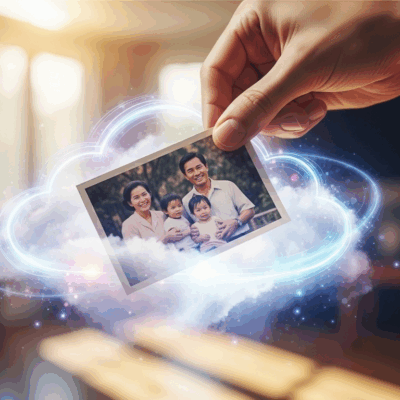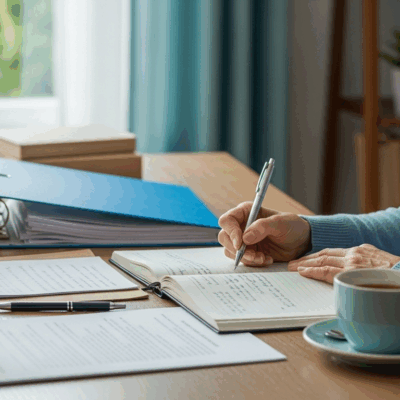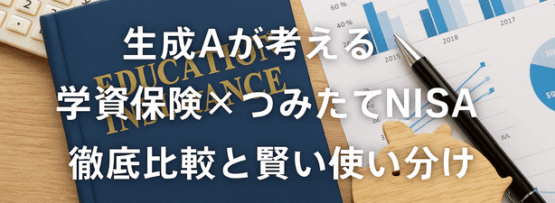ネット回線の「遅い」は、体感の主因が異なる三層—遅延、輻輳、無線—の合成として現れる。帯域の数字だけを追っても行き止まりになりやすい。最短で効く解は、この三層を短時間で切り分け、律速段を一点突破で外すことに尽きる。AIの推奨は、測定と構成変更を最小化しつつ、効果の出やすい順に介入する決定木を採る方針に収れんする。
遅さの正体は「遅延×輻輳×無線」の三層で決まる
体感速度は平均スループットではなく、往復遅延(RTT)と揺らぎ(ジッタ)、負荷時の遅延悪化(バッファブロート)、さらに無線品質(RSSI/SNRとチャネル占有)に強く支配される。ピーク帯域の不足は動画の初期バッファや大容量転送の時間にのみ反映されるため、リモート会議やゲームの「重さ」は主として遅延側の現象だ。宅内の電波条件、回線側の輻輳、家庭用ルータのバッファ制御という別々のボトルネックを、同じ指標で語らないことが近道になる。
30分で完了する切り分けの軸
最小手順は三点に収束する。第一に、端末を有線で直結し、同一LAN内iperf3で端末対ルータの線内速度を計って宅内の物理ボトルネックを排除する。第二に、負荷時遅延テスト(例:アップロードしながらのping、HTTPアップロード同時のジッタ確認)でバッファブロートの有無を確認する。平常時10ms台が負荷で100ms超へ跳ねるならキュー制御が原因だ。第三に、時間帯別の外部計測(速度テストとmtr/traceroute)で、夜間のみ悪化か終日悪化かを分ける。夜間のみでPPPoE区間の遅延が増えるならISP輻輳、終日なら宅内か無線が主因である可能性が高い。DNS応答時間の偏りはCDN到達性の問題を示す。
最短解の優先順位
短時間で改善幅が大きい順は次の通りになる。1) PPPoE運用の場合のIPv6 IPoE化(v6プラス/transix/OCNバーチャルコネクト等)による輻輳回避。IPv4はMAP-E/DS-Liteでカプセル化され、夜間のPPPoE集中を避けられる。2) ルータのSQM有効化(CAKE/FQ-CoDel)と上り帯域の正規化設定により、負荷時遅延を1/10程度に抑制。テストで得た実効上りの85–90%を整流値に置くのが定石だ。3) 無線の即効策—5GHz/6GHzへの移行、チャネル幅80MHzの適正化、干渉の少ないチャネルへの固定。4) 物理層の整備—平ケーブルや古いCat5eの排除、ONUからルータ間をCat6A以上に、必要なら2.5GBASE-T対応に更新。5) DNS最適化とHTTP/3(QUIC)の有効化により、権威・CDN近接性とコネクション確立時間を短縮。
宅内の即効改善は「有線化・電波設計・配置」
端末がノートPC・スマートフォン中心でも、作業用端末一台は有線で接続し、そこを基準点とするのが早い。Wi‑Fiは5GHz/6GHz帯を主経路とし、2.4GHzはIoTに限定する。80MHz幅の過剰な争奪がある環境では40MHzへ狭めた方が実効が上がる。アクセスポイントは目線より高い位置、遮蔽物を避け、電子レンジやBluetooth機器との干渉を遠ざける。DFS帯は空いているがレーダー検出でチャネル退避が発生するため、切断許容度によって固定チャネルを選ぶ。Wi‑Fi 6E対応端末がある場合は6GHz帯での分離が混雑回避に直結する。
回線とISPの律速を外す鍵はIPoE化と経路品質
フレッツ系で顕著な夜間低速はPPPoE網終端の混雑が典型例となる。IPoEへ移行すると、網の経路と輻輳点が変わり改善する確率が高い。IPv4はトンネル化されるため、既存アプリも透過的に動作する。ISPは同一IPoEでも事業者によってIXやトランジットの設計が異なり、行き先CDNとのピアリング品質が体感に響く。複数社のトライアル期間で夕方〜夜のRTTとジッタを比較すると、最短解の見極めが早い。企業VPN利用が多い家庭では、回線側よりもVPN装置の暗号化スループットが律速となることがあり、WireGuardなど軽量プロトコルで遅延・ジッタが安定する。
遅延を支配するのはキュー制御とMTU
バッファブロートは「速いのに重い」を生む主犯で、上り帯域の小さな家庭回線で特に顕在化する。CAKEやFQ‑CoDelを備える民生ルータでSQMを有効にし、上り・下りの整流を実効帯域の8–9割へ設定すると、アップロード中の会議・ゲームの破綻が止む。MAP‑E/DS‑Liteではカプセル化オーバーヘッドを考慮してMTU/MSSを調整すると、断片化と再送が減少する。多端末環境では、古典的なQoSでアプリごとに帯域を切るより、フェアキューイングで遅延を均す方が効果と運用コストのバランスが良い。
アプリ層の近道はQUICとDNSの最適化
HTTP/3はコネクション確立と輻輳制御で優位性があり、ブラウザ・アプリが対応していれば自動的に恩恵を受ける。DNSはキャッシュ一体型リゾルバの利用で往復を削減しつつ、応答の地理最適化が得られる経路を選ぶ。ISPのローカルリゾルバがCDN最短経路を返さない場合、DoH/DoQで汎用パブリックDNSへ向けた方が初期遅延が縮む事例がある。ただし地域CDNの接続方針と相性があるため、時間帯別に実測して採否を決めるのが合理的だ。
混雑時間帯と代替経路の即効策
集合住宅や学生寮では、宅内の施策だけでは夜間輻輳を解消できないことがある。モバイル5G/4GのFWAをサブ回線としてデュアルWAN化し、会議アプリのみを代替経路へ逃がすポリシールーティングは所要時間に対する効果が大きい。衛星系の低軌道サービスは下り帯域に強いが上り遅延が一定のため、用途選別が前提となる。小規模オフィスや在宅勤務用途では、上りの安定が最重要で、対費用効果は「IPoE化+SQM+5GHz/6GHz一本化」の組み合わせが最短経路として再現性が高い。