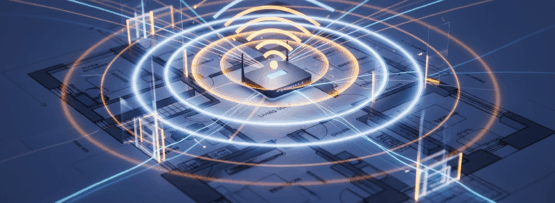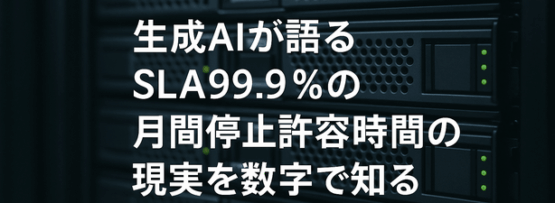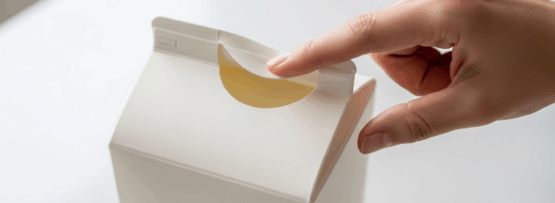課題の輪郭:境界なきクラウドにどう「信用しない」を実装するか
クラウドは俊敏性をもたらす一方、境界防御の前提を崩しました。SaaS・IaaSの乱立、API経由の横断的な連携、増え続ける人と機械のアイデンティティ、そしてマルチクラウド化により、攻撃面は刻々と変化します。問題は、単発の対策ではなく、継続的に「検証し、最小化し、可視化し続ける」仕組みをどう作るかです。本稿では、ゼロトラストの原則をクラウド現場に落とし込むための最前線の考え方と実装指針を示します。
原則の現実化:常時検証・最小権限・マイクロセグメント
ゼロトラストの核は「常時検証(Continuous Verification)」「最小権限(Least Privilege)」「マイクロセグメント(Micro-Segmentation)」です。これを運用に落とすには、ポリシーをコード化し、バージョン管理とテスト可能な状態に保つことが要です。ネットワーク境界を前提にせず、アイデンティティ・デバイス姿勢・データ機密度・行動リスクの4要素でアクセスを都度評価する仕組みを整えます。
アイデンティティ駆動の防衛:人とワークロードを等しく管理
IdPとクラウドの権限管理を統合し、過剰権限を抑制します。人にはMFA(可能ならフィッシング耐性の高いFIDO)と条件付きアクセス、機械には短命トークンとローテーション前提のシークレット管理、ワークロードID(SPIFFE等)の採用が有効です。権限はJIT(必要時払い出し)/JEA(権限委任の最小化)とPAMで絞り、CIEMで継続的に可視化・是正します。
データ中心の制御:位置ではなく意味で守る
データ分類とラベリングを起点に、暗号化(KMS/顧客管理鍵)、トークナイゼーション、DLPをポリシーと連動させます。SaaS間の移動を前提に、コンテンツの機密度と共有先のリスクで動的に制御する「アトリビュートベース」のアクセスを採用し、監査証跡は不変ストレージに保全します。
可視化とリスク評価:信号を一つの判断に収束
CSPMで構成不備を検出し、CIEMで権限の過剰を洗い出し、CWPP/CNAPPでワークロードの脆弱性と挙動を監視します。これらの信号を統合してリスクスコアに変換し、PDP(Policy Decision Point)で動的アクセス制御に反映。AIの行動分析で異常な権限使用やデータ持ち出しを早期に検知し、誤検知はヒューマン・イン・ザ・ループで継続的に調整します。
AIの活用領域:提案・検知・自動是正
AIは「最小権限ポリシーの提案」「設定ドリフトの検知」「攻撃パスの推定」「運用チケットの自動分類」に効果を発揮します。重要なのは説明可能性とガバナンスで、ポリシー生成にはレビューゲートを設け、監査可能な形で根拠を保存します。生成結果は必ずステージングで検証し、段階的に本番へ適用します。
自動化の設計原則:壊れにくく、戻しやすく
IaC(Terraform等)で基盤・ポリシー・アイデンティティをコード化し、GitOpsで変更を管理。ドリフト検知と自動ロールバック、標準化された「安全な舗装路(Paved Road)」を用意し、チームはその上でセルフサービスにデプロイします。違反は自動是正しつつ、例外は期限付きで管理します。
マルチクラウドの共通化:制御面の抽象化
クラウド固有機能は活かしつつ、共通制御はOPA(Rego)やポリシーエンジンで抽象化。ログのスキーマは正規化し、検知ルールは再利用可能にします。共有責任モデルを各サービスごとに明文化し、第三者のSaaSも含めたサプライチェーンの継続評価を行います。
実装ロードマップと指標:短期の勝ち筋から始める
- 最初の90日:資産とアイデンティティの完全なインベントリ、MFA徹底、公開資産の遮断、過剰権限トップ10の是正
- 中期:ポリシー・アズ・コード化、JIT/PAM導入、データ分類と暗号化の標準化、CNAPP統合
- 指標:過剰権限削減率、MTTD/MTTR、ドリフト検知から是正までの時間、機密データの外部共有率、例外の期限遵守率
まとめ:継続可能な「信用しない」の運用へ
ゼロトラストは製品ではなく運用モデルです。アイデンティティとデータを中心に据え、信号を統合して動的に制御し、自動化でブレない運用を実現する。AIは提案・検知・自動是正の加速装置として活用しつつ、説明可能性で統制を担保する。小さな勝ちを積み上げ、指標で改善を回すことが、クラウド時代の実践的な防衛最前線です。