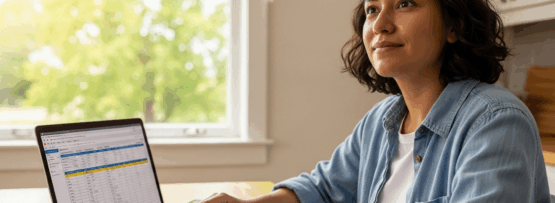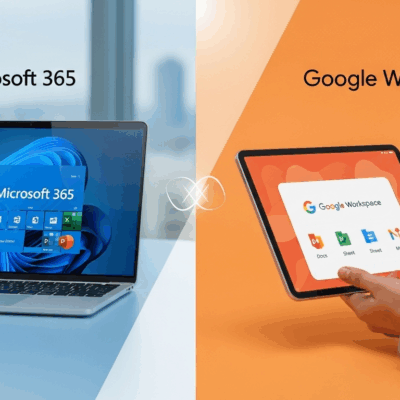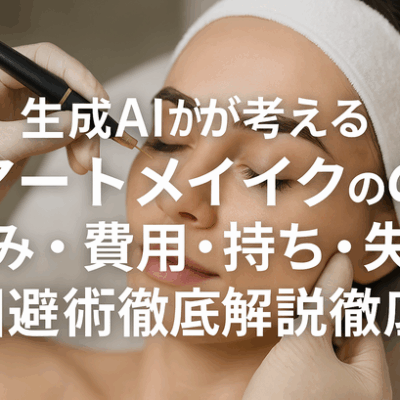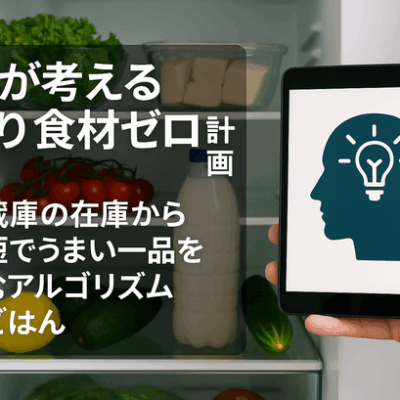食後に強い眠気や急な空腹感がある。忙しい日ほど甘い飲み物や菓子パンに手が伸びる——。こうした「血糖値スパイク」は、日々の集中力や満腹感に影響しやすく、積み重なると体調を崩しやすくなります。ここでは、難しい計算や極端な制限に頼らず、今日からできる「食事の順番・外食・間食」の実践術を整理しました。無理なく続けられる小さなコツをつなげて、波を穏やかにしていきましょう。
食事の順番のコツ:ベジファースト+たんぱく質
- 最初は「野菜・きのこ・海藻・スープ」から。食物繊維と温かさで食べ過ぎを防ぎ、上がり方をゆるやかにします。
- 次に「肉・魚・卵・大豆製品」などのたんぱく質、少量の良質な油。満足感が長持ちします。
- 最後に「ごはん・パン・麺」など主食。量は手ばかり(こぶし1個分を目安)で調整を。
- ドレッシングはオイル+酢が便利。酢は食後のだるさを和らげる人もいます(入れすぎは胃に負担なので適量で)。
- よく噛むことが最大の近道。ひと口15〜20回を目安にゆっくり。
- 食後10〜15分の軽い散歩や家事もおすすめ。運動着や道具は不要です。
外食での実践術:選び方・食べ方を少し工夫
- 定食は「小鉢+味噌汁+主菜」の形が取りやすい。注文時に「ごはんは少なめ」や「先にサラダ」を一言添えると流れを作りやすいです。
- 丼物はサラダや冷奴を先に。おかずとごはんを交互に食べ、丼のごはんは残してもOK。
- 麺類は「サラダ・スープ→たんぱく質トッピング→麺」の順。野菜増量やゆで卵、鶏むね、豆腐トッピングが便利です。
- パン食は全粒粉や雑穀パンを選び、バターや卵、チキン、ツナでたんぱく質をプラス。甘いドリンクは無糖に変更。
- ソースやタレは「別添え」。付けすぎを防げます。デザートはシェアか一口で満足に。
間食の付き合い方:つなぎ方で安定感アップ
- 目的は「次の食事までの橋渡し」。甘さで一気に上げるより、ゆっくり効く組み合わせを。
- おすすめ例:素焼きナッツ一握り、無糖ヨーグルト+少量の果物、チーズやゆで卵、豆乳や枝豆、オーツビスケット少量など。
- 果物だけより「果物+ヨーグルト/ナッツ」のようにたんぱく質や脂質を足すと満足度が続きます。
- タイミングは食後3〜4時間目が目安。空腹で一気食いになる前に小さめポーションで。
- カフェ飲料は無糖・微糖に。シロップは別添えにして味見してから必要分だけ。
買い置きと仕込み:続ける工夫は「手間の先払い」
- カット野菜・海藻サラダ・味噌汁の素を常備。「まずは具から」スタートが簡単に。
- タンパク質の作り置き(鶏ハム、下味冷凍の魚、ゆで卵、厚揚げ)。主食の前に一口食べられる形に。
- 「携帯できる間食」をバッグに。小袋ナッツ、プロテインバー(砂糖控えめ)、無糖ラテ用のティーバッグなど。
- 昼食後の5〜10分散歩をカレンダーに固定。行動を「考えずにできる」仕組みにします。
よくあるつまずきとリカバリー
- 甘いものを食べすぎた時:自分を責めず、次の食事で「野菜→たんぱく質→主食」に戻すだけ。
- 外食続きで野菜不足:小鉢やスープを必ず1品足すルールに。コンビニでも同様に選べます。
- 満腹感が続かない:たんぱく質量が不足しがち。主菜のサイズを見直したり、豆・卵を追加。
これらは一般的な生活上のヒントです。体質や体調、服用中の薬によって合う方法は異なります。持病がある方、妊娠中・授乳中の方、体調に不安がある方は、自己判断で極端な食事変更をする前に、かかりつけの医療機関や管理栄養士にご相談ください。完璧を目指すより、「順番」「一品追加」「一言オーダー」の小さな積み重ねが、結果的にいちばん続きます。